合唱コンの練習 時間が長い問題
合唱コンクールへの練習って、気づけば授業の時間を食ってしまってストレスになることもあるよね。
練習の時間、放課後や朝練、さらに週末まで。学校生活が合唱練習で埋まると、授業や部活、塾との両立が大変になる。
「授業中に居眠りしそう…」なんて声も。
そこで今回は、なぜ「練習時間が長くなるのか」を明らかにしつつ、授業や部活を圧迫しないようにする対策を考えていこう!

合唱コン練習が授業を食う本当の理由をまず解体する
合唱コンクールの練習って、気づいたら授業の予定を押しのけて入ってくるよね。
でも、なぜそんなことが起きるんだろう。
理由をちゃんと分解してみれば、先生も生徒も納得できる方法が見えてくるはずだよ。
ここでは「時間が長すぎるのはなぜか」をカジュアルに分解していくね。

時間の見積り甘すぎ問題を可視化する
合唱の練習って「まぁ30分で仕上がるでしょ」みたいなノリで始まることが多いんだよね。
でも実際は、発声で10分、パート練習で20分、合わせに30分、本番想定でさらに30分とか、どんどん膨れあがる。
結果、気づけば授業1コマが吹っ飛んでることもある。
学校って年度ごとに予定がパンパンだから、時間の読み違いが積み重なると大きなストレスになるんだよ。
生徒の側からしても「今日は早く帰れると思ったのに」って気持ちになるし、先生からしても「また授業が押すのか」とため息。
時間管理を甘く見積もるのは、合唱コンあるあるだよね。
指揮 伴奏 パート決めの初動が遅いと全部が遅れる
「指揮者どうする?」、「伴奏者だれやる?」って決めるのに1週間かかるクラス、けっこうあるんだ。
決めるのが遅れると、練習そのものが立ち上がらない。
さらにパート分けで「ソプラノ行きたい」、「いやアルトにして」ってモメると、そこでまた時間ロス。
結局、スタートが遅れた分を取り戻そうとするから、授業や放課後に負担が集中しちゃう。
早い段階で役割を確定してしまうだけで、時間のロスは劇的に減るんだよね。
完璧主義と早く帰りたい派のせめぎ合いを言語化する
クラスの中には「もっと合わせよう」、「もう一回やろう」って言う完璧主義派と、「もう帰ろうよ」、「塾あるんだよね」っていう早く帰りたい派が必ず存在する。
どっちも間違ってはいないんだけど、そのせめぎ合いで練習が長引くんだよ。
特に3年生なんかは「最後の合唱コンだから」と気合い入りすぎることもある。
逆に1年生は「え、なんでこんなにやるの」って温度差が大きい。
だからこそ、この違いを言葉にして「今日はここまで」って線を引かないと、延々と終わらないんだよね。
担任 音楽科 学級委員の三角関係を整理して役割を固定する
練習の時間をめぐって一番もめるのが、担任の先生と音楽科の先生、そして学級委員。
担任は「授業進度が気になる」、音楽科は「曲の完成度を上げたい」、学級委員は「クラスの団結を優先したい」。
この三角関係が整理されてないと、誰かの意見で練習が長引いたり、逆に削られたりするんだよね。
役割をはっきり決めて、「ここまでは音楽科の指導」、「ここからは担任の判断」みたいに分ければ、余計な延長がなくなる。
生徒だってそのほうが安心するんじゃないかな。

授業と練習のタイムシェアをルール化するだけで漏れが減る
授業も練習もどっちも大事。
でも、その時間をはっきり区切っておかないと「いつのまにか練習が授業を侵食してる」って状態になる。
ルール化するっていうとちょっと堅苦しいけど、シンプルに「いつ・どの科目をどれくらい削っていいか」を最初に決めるだけでかなり違う。
クラス全体の予定表に落とし込めば、生徒も先生も見通しが立って気が楽になるよ。
週内練習時間表 科目×曜日×休み時間を先に確定する
「とりあえず今日の授業つぶして練習する?」っていう場当たり的な判断はストレスのもと。
先に1週間分の練習時間表を作って、国語や数学の授業にどこまで食い込むか、休み時間をどこで使うかを見える化するんだ。
たとえば「水曜の6時間目は半分練習にする」、「金曜の朝は発声練習に固定」みたいにルールをはめてしまうと、先生の都合も生徒の予定も調整しやすくなる。
学級単位で決めて掲示しておくと「今日はどっち?」みたいな混乱もなくなるよ。
延長の上限ルールと延長コストの合意を作る
「もう1回!」、「いやあと2回!」っていう声で練習がズルズル延びるのは合唱コンクールあるある。
だからこそ、延長は最大で10分とか15分までってルールを作っておくのがいい。
さらに「延長した分は翌日の練習を削る」みたいなコストを設定すれば、むやみに延長しようとする人も減る。
生徒も先生も「今日は限界ここまでだよね」って線が引けるから、ストレスが減るんだ。
休み時間15分練習の黄金比 声出し 合わせ 振り返り
休み時間の15分って、案外バカにできない。
「声出し5分+合わせ5分+振り返り5分」って黄金比を守るだけで効率が全然ちがうんだよ。
ただし、休み時間全部を練習に使うと疲れ切っちゃうから、やりすぎは逆効果。
短い時間でメリハリをつけて練習する方法を身につけると、授業への集中力も落ちにくい。
学校って体力勝負だから、休憩も大事なんだよね。
練習ログ 誰が何を何分 のミニKPTで改善を回す
練習がダラダラ終わるのは「どこに時間を使ったか」が分かってないから。
そこでおすすめなのが練習ログ。
「ソプラノ音取り10分」、「合わせ20分」、「休憩5分」みたいに記録して、最後にKPT(Keep・Problem・Try)で振り返る。
この習慣があると「昨日は無駄に通しを3回やったね」、「今日はここを短くしよう」って改善ができる。
練習の質が上がれば、時間の量を減らしても仕上がりが落ちないんだよ。

部活と塾の板挟みを解く交渉テンプレと役割分担
合唱コンクールの練習が長引くと、一番困るのが部活と塾との板挟み。
「部活サボったら顧問に怒られる」、「塾に遅れたら親に文句言われる」って、どっちを優先していいかわからなくなるんだよね。
ここでは、生徒自身がちょっとした交渉や工夫でストレスを減らせる方法をまとめるよ。
クラス全体で役割を分担すれば、誰かひとりが犠牲になる必要もなくなるんだ。
顧問 コーチに出す練習計画1枚紙の要点
部活の顧問やコーチにとって一番イライラするのは「今日は急に練習に来ませんでした」っていう事後報告。
だからこそ、あらかじめ1枚紙で「この週は合唱練習が長引く予定です」って伝えておくのが大事だよ。
内容はシンプルに「日時・理由・帰宅時間」の3点セットで十分。
先生の立場からしても、理由が見えると理解しやすいんだ。
言い訳っぽくならずに、ちゃんと説明するだけで印象がぜんぜん違う。
試合 大会週の免責スロットをあらかじめ確保する
部活にとって大会や試合の週は死守したい大事な時間。
そこに合唱の練習をねじ込むと、どうしても不満が爆発するよね。
だから最初から「大会週は部活優先」、「その分、合唱は前後で調整」って免責スロットを確保しておくんだ。
これを決めておくだけで、後から「なんで今?」ってケンカになるのを防げる。
生徒にとっても安心材料になるから、練習に集中できるよ。
塾 家庭への連絡文テンプレ 保護者向け 生徒向け
「今日は練習が長引いて帰りが遅いです」って親にLINEするだけだと、なんとなく不信感を持たれることがあるよね。
だからこそ、塾や家庭に向けた“公式っぽい”連絡文テンプレを持っておくと便利。
「〇日まで合唱コンクール練習のため、帰宅時間が30分遅くなります」みたいにシンプルで事実だけを伝える。
保護者からしても「ちゃんと把握できてるな」と思えるし、生徒も余計なストレスを抱えなくて済むんだ。
部活勢の時短メニュー 家でできる無音トレとパート別課題
「部活あるから歌えません」ってゼロ参加にするより、時短メニューを作って少しでも合唱に関わるのが賢いやり方だよ。
たとえば、家でできる無音トレ。
歌詞を口パクで練習するだけでも口の形やリズム感は鍛えられる。
さらにパートごとに「今日はここの小節だけ練習」って課題を出しておけば、短時間でも効果が出る。
全部を完璧にやろうとしないで、工夫でカバーすることが大事なんだよね。

練習の質を上げて量を減らす短時間集中の設計図
「時間が足りない」と嘆く前に考えたいのが、練習の“質”を上げること。
長くやれば上手くなるわけじゃない。
むしろ、ダラダラ歌ってると声が枯れるし集中力も切れて、逆に下手になることもあるよね。
ここでは、短い時間でも成果を出すための集中メニューを紹介するよ。
30分メニュー 発声5+問題小節10+接続10+通し5
ダラダラ2時間やるより、30分の中でギュッと集中するほうが効率的。
まずは発声練習を5分で切り上げる。
次に一番つまずいている小節を10分集中で練習。
そこから前後の流れを10分でつなげる。
最後に通しを1回だけ5分。
これだけでちゃんとした1セッションになる。
先生や生徒の負担も少ないから、部活や授業の時間も守れるんだ。
詰まる小節だけをループするセクショニング術
合唱練習でよくある無駄が「頭から最後まで毎回通す」こと。
これだと時間がいくらあっても足りないよね。
セクショニング術は「問題小節だけ切り出してループする」やり方。
例えば“ここからここまで”を10回繰り返す。
すると短時間で音程やリズムが体に染みつく。
効率が跳ね上がるし、集中力も続くんだよ。
音取りの内製化 ピアノ頼みを卒業するボカロイドやアプリ活用
音取りを全部伴奏者や先生に頼ってると、それだけで時間が消える。
そこで役立つのがアプリやボカロイドの音源。
パート別に音を流して、生徒が各自で事前に耳に入れておくんだ。
これで「音取りだけで練習が終わった…」みたいな悲劇が減る。
学校でもスマホやタブレットが使える場面はあるし、家庭学習にも使える方法だよね。
本番ホール想定のダイナミクス指示を先に決めておく
練習の途中で「ここはもっと強く歌おう」、「ここは静かに」って議論を始めると、あっという間に時間が過ぎちゃう。
だから、最初から本番ホールを意識したダイナミクス指示を決めておくのがコツ。
たとえば「Aメロは弱め、Bメロは全力、最後は溜めてから大きく」みたいに。
ルールを最初に設定するだけで、練習中の迷いがなくなるんだよね。

本番前の詰め込み地獄を回避する逆算ロードマップ
合唱コンクール直前になると「まだ完成してない」、「もう一回やろう」って詰め込み地獄に突入するクラス、多いよね。
でも、本番前にやりすぎると逆に仕上がりが崩れることもあるんだ。
だからこそ、逆算で練習を組むのがコツ。
計画的にゴールへ近づければ、授業や部活を犠牲にしなくても余裕を持って仕上げられるよ。
D-21で仕上げ7割 D-14で表現 D-7で体調と声量にシフト
大会の3週間前、つまりD-21で曲の完成度を7割まで持っていくのが理想。
そこから2週間前のD-14でハーモニーや表現に集中。
そして1週間前のD-7は体調と声量の管理フェーズにシフトする。
この逆算スケジュールを守るだけで、本番前の「間に合わない!」って焦りを減らせる。
授業をつぶして詰め込む必要もなくなるんだ。
前日やりがちNG 通し連発 大声 長時間立ちっぱなし
前日の練習でやりがちなのが、通しを何度も繰り返すこと。
「最後だから気合い入れよう」って思うんだけど、実は逆効果。
声が枯れて本番で力が出せなくなるし、長時間立ちっぱなしで体力を消耗してしまうんだ。
前日は軽く声を出して確認するくらいで十分。
大切なのは本番に体力と集中を残すことなんだよね。
マイクなし環境想定の投射 placement とブレス配分
学校の体育館やホールって、基本的にマイクなしで歌うよね。
そのときに大事なのが声の投射、つまりplacement。
「遠くの壁に声を飛ばすイメージ」で歌うと、客席の最後列まで届くんだ。
さらにブレス配分も重要。
息切れしないように、どこで吸うかをあらかじめ決めておくと、直前でバタバタ練習しなくても安定するよ。
反省会は翌週1回だけ 終わりを決めて燃え尽きを防ぐ
本番後の反省会をその日のうちに延々やると、疲れすぎて「もう合唱なんていいや」って燃え尽きちゃうんだ。
だから反省会は翌週に1回だけにするのがおすすめ。
「次はもっとこうしよう」っていう前向きな振り返りになるし、クラスの雰囲気も保てる。
終わりの区切りを決めることが、次の学校行事にうまくつなげるコツだよ。

保護者 塾 顧問への根回しで時間の摩耗をゼロにする
合唱コンクールの練習って、クラスだけの問題じゃなくて家庭や部活ともつながってるよね。
「なんでこんなに帰りが遅いの」、「塾に間に合わない」って不満が出ると、板挟みでつらい。
だからこそ、保護者・塾・顧問の先生に最初から根回ししておくことが大事なんだ。
時間の摩耗をゼロにするためのちょっとした工夫を紹介するよ。
目的 期間 頻度 延長上限を載せた通知テンプレ
「なんで今日だけ練習が長いの?」って言われると困るよね。
そこで役立つのが通知テンプレ。
内容はシンプルでOK。
「目的:合唱コンクール練習」、「期間:10月◯日まで」、「頻度:週3回」、「延長は最大15分」みたいにまとめるだけ。
この情報をプリントや学年だよりで共有すれば、親も塾も「なるほど」と納得してくれるんだ。
欠席 早退の扱いを先に決めるQAリスト
練習って全員そろわないと成立しない部分があるけど、欠席や早退は必ず出てくる。
そのときに「どうするの?」って毎回もめるのは時間の無駄。
だから、先にQAリストを作っておくんだ。
「塾で遅れる人は2番目の合わせから参加」、「体調不良で休んだ人は録音を聞いて復習」みたいに決めておくとスムーズ。
生徒も安心して調整できるよね。
内申 評定への影響説明を事実ベースで
合唱練習が長引くと「成績下がったらどうするの」って心配する保護者も多いんだよね。
でも実際には、合唱コンは評価の対象になることもあるし、内申にプラスに働く場合もある。
そのへんを先生が事実ベースで説明してあげると、不安はかなり減る。
「学校全体の行事だから安心してください」って伝えるだけでも印象は大きく変わるよ。
クラスだより 学年だよりで練習の見える化
クラスだよりや学年だよりを使って「今週はここを練習しました」って伝えると、家庭とのギャップがなくなる。
見える化すると「どこまで仕上がってるのか」がわかるから、親も安心できるんだよ。
生徒からしても「ちゃんとやってるって伝わってる」って気持ちになるからモチベも上がるんだ。
時間のロスをなくすためには、情報の共有がいちばん効く方法だよね。

声変わりや喉トラブルと時間配分 歌えない時間の活かし方
合唱コンクールの練習で意外に大きいのが「声変わり」と「喉のトラブル」。
特に男子は3年生くらいになると声が安定せず、歌うのがつらい時期になるよね。
でも「じゃあ歌わなくていいよ」って切り離すと、クラスの一体感が崩れるんだ。
歌えない時間をどう活かすかが、クラス全体の完成度につながるよ。
ミュート練習 口形 リズム 発音 で参加感を切らさない
声が出しにくいときは、無理に大声を出す必要はない。
口形だけで歌ったり、リズムや発音を合わせたりする“ミュート練習”でも十分に役立つんだ。
これをやると声変わり中の男子も「自分もクラスの一員だ」って気持ちを持ち続けられる。
ただの見学にするよりずっと効果的だよ。
コンディショニング 睡眠 水分 湿度 アイシングの基礎
喉のトラブルを減らすには、基本のコンディショニングが重要。
睡眠をしっかりとる、水分をこまめにとる、教室や家庭で湿度を保つ、そして炎症があればアイシングで冷やす。
こうしたケアを習慣にするだけで、喉の調子はかなり安定するんだ。
体調管理は、合唱の実力を底上げする見えない武器なんだよね。
パート再配置とオクターブ下を勇気ある選択にする
声変わりで高音が出ない男子を無理にソプラノやアルトに残すのは逆効果。
むしろ、勇気を持ってパートを再配置したり、オクターブ下で歌わせたりするほうが全体のハーモニーが整う。
「声が出ないから戦力外」じゃなくて「別の方法で貢献する」って考えることが大事だよね。
録音レビュー係 譜めくり係など代替貢献タスクを準備する
歌えない時間を完全に無駄にする必要はない。
録音してレビューする係や、伴奏の譜めくりをする係など、代替タスクを準備しておけばいい。
そうすれば歌えない子もチームの一員として参加できる。
合唱って「全員でやる」ことが大切だから、役割をうまく配ることがクラスの雰囲気を守るんだよ。

デジタルで練習短縮 アプリとAIで音取りを爆速に
最近はアプリやデジタルツールを使って練習を時短する学校も増えてきたよね。
授業や部活を削らなくても、家や移動時間で効率よく準備できる。
デジタルを味方につければ、時間の問題はだいぶ解消できるんだ。
MIDIやMuseScoreでパート別音源を配布する
先生や伴奏者が一つずつ音を弾いて教えると時間がかかる。
そこで便利なのがMuseScoreなどの無料アプリ。
パート別に音源を配布すれば、生徒は自分で事前に練習できる。
学校の練習は合わせだけに集中できるから、効率が段違いになるんだよ。
スマホ録音+波形でズレを見せて議論を短くする
「今ズレてたよね?」、「いや合ってたよ」って口論に時間を使うのはもったいない。
スマホで録音して波形を見れば、一目でズレがわかる。
これなら議論が短縮できて「じゃあ次どう直すか」にすぐ移れるんだ。
メトロノーム チューナーは全員インストール前提にする
テンポや音程がバラバラなのは“あるある”だけど、実はアプリでかなり解決できる。
メトロノームやチューナーを全員が持ってる状態にしておけば、基準がそろうんだ。
練習時間のロスも減るし、家で自主練もしやすいよ。
連絡はクラスルームやLINEオープンチャットの固定メッセ運用
「明日の練習時間なんだっけ?」って毎回質問が飛ぶのも時間のムダ。
GoogleクラスルームやLINEのオープンチャットを使って、予定を固定メッセで掲示しておけば、連絡が一発で済む。
練習に集中できる時間を増やす工夫は、こういう地味なところにもあるんだよね。

まとめ 勝つより壊さない 時間と関係を守る設計が最強
合唱コンクールで一番大事なのは「勝つこと」じゃなくて「クラスを壊さないこと」かもしれない。
授業・部活・家庭を犠牲にしてまでやると、どこかで不満が爆発してしまう。
時間の設計をちょっと工夫するだけで、関係も成績も守れるんだよ。
先に決める 数える 短く区切る 三原則で摩擦を減らす
練習の時間配分は「先に決める」、「時間を数える」、「短く区切る」この三原則で摩擦が激減する。
場当たり的にやると絶対に長引くから、最初から線を引いておこう。
役割を分散して善意の一極集中を回避する
「指揮者が全部やってくれる」、「学級委員が回してくれる」って状態は続かない。
役割を分散して、善意の一極集中を避けるのがクラスを守る方法だよ。
量より質 詰まる箇所を特定して集中的に潰す
練習は長さより中身。
特に詰まる部分を特定してそこだけ潰すと、全体の完成度は一気に上がる。
時間が少なくても「仕上がった感」が出せるんだ。
本番1週間前からは体調>仕上げで走り切る
最後の1週間は「歌の仕上げ」じゃなくて「体調管理」に集中しよう。
風邪や喉トラブルで欠けたら元も子もない。
体調を整えて本番を迎えるのが、いちばん大事なんだよね。
※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。




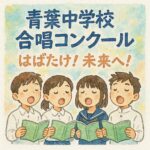


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません