合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!
- 1. これが勝てそうな選曲リスト2025(中1・中2・中3)
- 2. 中学1年
- 3. 中学2年
- 4. 中学3年
- 5. 選曲極意①:「導入から心わしづかみ!」
- 6. 選曲極意②:「人気曲ランキングを鵜呑みにするな」
- 7. 選曲極意③:「定番曲こそ侮るな!」
- 8. 選曲極意④:「先生&生徒の“本音”センサーを使え」
- 9. 選曲極意⑤:「勝ち曲13+αからのセレクト」
- 10. 音域や人数に応じた“本当のおすすめ曲”は?
- 11. 伴奏がピアノだけでも映える曲とは?
- 12. 練習のしかたはこうしよう!
- 13. 音をそろえるシンプル練習
- 14. 合唱コン、勝つより“伝える”を狙え
- 15. 実は知りたい:上手い人と下手な人の歌い方の差
- 16. 合唱の「並び」の基本:まずは定番フォーメーションを把握
- 17. 緊張するのってダメなことじゃない
- 18. 本番前に知っとこ!合唱コンの髪型でやっちゃいがちなミス
- 19. 鉄板人気!合唱コンクールの定番ヘアスタイル4選
- 20. なぜ男子は合唱コンの練習でふざけてしまうのか
- 21. 合唱コン練習 時間が長い問題
- 22. 練習期間が短くても間に合う“勝負曲”って?
- 23. 表紙は「テーマ先行」が勝ち筋。まず“伝えたい一言”を決めよう
- 24. 合唱コンクールで刺さる四字熟語、まずは王道から
- 25. 合唱コンの「紹介文」って結局なに書けばいいの?
- 26. 感想文を書くまでが合唱コンだ!
- 27. まとめ
これが勝てそうな選曲リスト2025(中1・中2・中3)
合唱コンクールで勝ちを狙うなら、曲選びは戦略の半分以上を占めるんだ。
学年ごとに声の伸びや表現力は違うから、中1は歌いやすさを優先するのがいいんだよ。
中2ではハーモニーの厚みが勝負を分ける。
中3では感動を引き出す重厚な曲が評価につながるんだよ。
課題曲は基礎を固めやすい定番を選ぶと安心。
自由曲はドラマティックに盛り上がる曲のほうが審査員の心をつかみやすい。
歌いやすさだけじゃなくて「聴き映え」「メッセージ性」「盛り上がりどころ」がある曲ほど勝ち筋になるんだ。
このリストは人気と実績に裏打ちされた“勝てる選曲”をまとめたものだよ。
※「課題曲」は学校指定の想定、「自由曲」はクラス選択の想定です。
中学1年
| 課題曲(学校指定) | 自由曲(クラス選択) |
|---|---|
|
|
中学2年
| 課題曲(学校指定) | 自由曲(クラス選択) |
|---|---|
|
|
中学3年
| 課題曲(学校指定) | 自由曲(クラス選択) |
|---|---|
|
|

選曲極意①:「導入から心わしづかみ!」
合唱コンクールでみんなの心にガツンと刺さる“神曲”を探してる?
最初の出だしで“おっ”と目を引いて、最後まで鳥肌じわり、優勝も夢じゃない。
中学生のキミが、ピアノの音、伴奏、歌詞、ハーモニー、パートごとの工夫まで全部意識して選曲するだけで、ぐっと表現力アップだよね。
“なんでこの曲?”って審査員に思わせるセンスと、“みんなで歌えば最高だよね!”のバランスこそが、勝ちへの近道になるって、覚えておいてだよ。
声質にフィットする選曲法
声の高さや女声・男声のバランスは、合唱の肝。
中学生だから声変わりもあるし。
自分たちのクラスの声質をちゃんと見極めて、歌いやすさを優先するのって、意外と勝敗を左右するコツでもあるんだ。
たとえば高すぎるメロディーは“あれ?できない…”って雰囲気になるかもね。
逆に低すぎると“伴奏ピアノが厚すぎて埋もれる”こともあるし。
そこで、自分たちの音域にぴったりな合唱曲を選ぶと、響きや表現力が増して、“このクラス、うまいぞ”ってなるよ。
転調や構成で“ドラマ”を作る
合唱曲の転調部分、特にサビ前後で“グッと”上がる感じ、あれはドラマ。
“え?ちょっとウルっ”ってなる瞬間ね。
転調や構成がしっかりしている曲は、聴く人に“おっ”と思わせられる。
伴奏やメロディーが“ドラマ仕立て”だと、最後のサビで鳥肌立つこともあるし。
そこを練習で丁寧に表現できれば、“ただの課題曲”が“心に残る演奏”になるかもね。
構成の起承転結を意識して、メリハリある演出、価値あり。
誰もが知ってるけど敢えて選ぶ効果
定番の“COSMOS”や“旅立ちの時”みたいな曲って、みんなに親しみあるよね。
“あ、知ってる!”があると、聴いてる人がすぐ心に入ってきやすい。
で、“定番なのに新鮮に聞こえるアレンジ”を加えると、怪我しないセーフティーゾーンで勝負できる。
知られてる安心感、そこにちょっと意表をつく構成の工夫を加えると、“お、なんか違うぞ?”って思わせられるのがいいところ。
リズムの変化、掛け合いパート、アカペラ部分……ちょっとした工夫で、定番が魅力的になるよ。
伴奏やアレンジとの相性で決める
合唱と言えばピアノ伴奏、これ大前提。
ピアノの音質やアレンジ次第で曲の雰囲気ってガラリと変わる。
指揮者や伴奏者とのコンビネーションも、合唱の印象を左右する大切な部分。
“ピアノだけでも映える曲”を選ぶと、伴奏が弱くても大きな効果になるかもだし。
編曲に工夫があると、単調じゃない雰囲気になるしね。
自分たちの練習環境にピッタリなアレンジを選ぶのが賢い選択だよ。

選曲極意②:「人気曲ランキングを鵜呑みにするな」
“合唱コンクール 人気曲ランキング”で検索して、上から順に選ぶ……それ、ちょっと危険。
確かに『正解』『僕のこと』みたいな人気合唱曲は流行に乗っていて盛り上がるけど、必ずしも自分たちのクラスに合ってるとは限らない。
大事なのは“流行に飛びつくか”“永遠の定番でいくか”、その判断力。
YouTubeをチェックしつつ、ただのランキング依存じゃなく、“なぜこの曲を選ぶのか”を考えることが勝ちへの第一歩だよ。
流行VS永遠、どっちを狙う?
流行りの曲は注目を集めやすい。
『正解』とか『僕のこと』はYouTubeでも紹介されてる。
でも流行曲は審査員に“またこの曲か”と受け取られるリスクもあるんだよね。
一方で“永遠の定番曲”は安定感がある。
中学校の合唱コンなら、審査員も安心して評価しやすい部分もあるよ。
どっちに転ぶかは、クラスの雰囲気や歌詞との相性で決まることもあるんだ。
鉄板曲の裏をかくリスクとリターン
ランキング上位を避けて、あえて別の曲を選ぶと“お、意外!”ってなることもある。
ただし、その曲が難易度高すぎて崩壊する危険もあるんだよな。
リターンは“個性的で魅力的な合唱”をアピールできること。
リスクは“練習時間が足りずに中途半端”になること。
鉄板から外れるなら、メンバー全員が“これを歌いたい”と感じる熱量が必要になるよね。
生徒の共感を呼ぶキーワード選び
歌詞に“未来”“夢”“仲間”みたいな言葉が入ってると、中学生の心にスッと入ってくるんだよね。
流行曲でも定番曲でも、共感できるキーワードがあるかどうかが大事。
審査員だって、人間だ。
歌詞に引き込まれると評価も変わることがある。
だから“歌ってて気持ちが乗るかどうか”を重視すると、クラス全員がひとつになりやすいよ。
アレンジの自由度を見逃すな
同じ曲でも、編曲次第でまるで違う印象になるんだ。
掛け合いを強調したり、アカペラ部分を入れたり、ピアノ伴奏の雰囲気を変えたり。
自由度のある曲なら、自分たちのクラスだけの表現に仕上げやすいんだよね。
“単なるランキング上位曲”から“一生の思い出に残る合唱曲”に進化させる可能性がある。
工夫次第で勝ち曲になるって、面白いよね。

選曲極意③:「定番曲こそ侮るな!」
“定番曲=つまらない”と思ったら大間違い。
『ほらね、』『虹』『BELIEVE』みたいな定番合唱曲は、ネットでも繰り返し紹介されている“王道”。
馴染みのフレーズが安心感を与え、歌いやすさとメロディーの魅力が共存してる。
大切なのは“定番をどう自分たち流に輝かせるか”。
普通に歌えば“普通”で終わるけど、工夫を加えれば“定番なのに最高”って評価になることもあるんだ。
「ほらね、」「虹」「BELIEVE」定番の強み
この3曲は多くの中学生に歌われ続けてきた“安心のブランド”だ。
歌いやすさ、メロディーの美しさ、そして歌詞の普遍性。
ネットでも繰り返し取り上げられてる理由はそこにある。
誰でも知ってるし、先生も指導しやすいし、クラス全員が乗りやすい。
“王道曲”には王道の理由があるんだよ。
馴染み深いフレーズが持つ安心感
サビや出だしで“あ、このメロディー!”ってなると、観客や審査員もリラックスする。
安心感があるからこそ、ちょっとした表現の差が評価につながるんだよ。
全員が自信を持って歌える安心感、それ自体が“強み”になってくる。
難易度が極端に高い曲より、定番でしっかりハーモニーを響かせたほうが“心に届く”ということもあるよね。
歌いやすさ vs 印象に残る難しさのバランス
歌いやすい定番曲はまとまりやすいけど、逆に“凡庸”と見られる危険もある。
そこでちょっとした難易度を加えて“印象に残る仕上がり”を狙うのがコツだ。
テンポを工夫したり、リズムに変化をつけたり。
難しさと歌いやすさの絶妙なバランスが、クラスの魅力を最大限に引き出すんだよ。
想い入れが勝敗を左右することも
最後はやっぱり“この曲を歌いたい!”って気持ち。
曲への想い入れが強いと、表現力が自然に出るんだよね。
審査員は音楽の技術だけじゃなく、“熱量”も見ている。
勝てるかどうかの境目は、想い入れの差で決まることだってあるんだ。

選曲極意④:「先生&生徒の“本音”センサーを使え」
選曲を決めるとき、“先生が推す曲”と“生徒が歌いたい曲”がズレること、多いよね。
でも、そのズレこそがチャンス。
ネットにある先生の人気曲ランキングには“歌いやすく審査員ウケもいい曲”が潜んでいる。
一方、生徒発の自由曲は想定外の熱量を生むことも。
どっちの声も拾って、バランスよく決めるのが勝てるクラスの秘密だよ。
先生人気曲ランキングの罠と宝
先生が好む曲は、指導しやすくて評価基準に合いやすい。
たとえば『Let’s Search For Tomorrow』『大切なもの』なんかは安定の人気。
ネットの記事でもよく挙がる“定評ある合唱曲”だよ。
ただしキミたちが“これ退屈じゃない?”と思うならもう一度考えるべき。
宝でもあり、罠でもある選択肢なんだ。
自由曲での意外なヒット曲
“自由曲”は、実は勝ち筋が隠れている。
『地球星歌』『明日へ』『ほらね、』みたいに、メッセージ性のある歌詞と壮大なハーモニーが「歌いたい!」という心を動かすんだよ。
自由曲は難易度もあるけど、成功すれば“圧倒的なアピール”につながるよね。
「勝ちたい」から「歌いたい」への転換の魔力
“勝つため”に選んだ曲より、“歌いたい”と感じている曲のほうが本番で強い。
生徒が主体的に歌うと、自然に表現力が上がるんだよ。
その空気感こそ審査員に伝わる。
勝ちたい気持ちを“歌いたい”に変えた瞬間、合唱は魔法みたいに変わるんだ。
生徒の声に耳を澄ませる選曲術
「これ歌いたい!」という声を無視しないこと。
本音を拾うと練習の雰囲気も変わるし、モチベーションも爆上がり。
クラス全員で納得して決めた曲は、練習の熱量も別格になる。
先生も歩み寄って、“勝てる合唱コンクール曲”を一緒に探すのが大事なんだ。

選曲極意⑤:「勝ち曲13+αからのセレクト」
“勝ち曲リスト”って聞いたことある?
YouTubeやえすたの合唱ノート、ONTOMOでも紹介されている“定番中の定番”。
『旅立ちの時~Asian Dream Song』『時の旅人』『COSMOS』など、全国の中学校で歌われ続けた鉄板。
黄金リストの中から選べば大ハズレはしない。
でもそのまま歌うと凡庸に聞こえるリスクもある。
大事なのは、“リストの中から選ぶ”+“自分たちの工夫で光らせる”の二段構えだよ。
黄金リスト
『旅立ちの時』『時の旅人』は合唱史に残る王者級の作品。
YouTubeでも演奏動画が多数アップされていているよ。
教育音楽ONLINEでも解説されるくらい、完成度の高い曲なんだよね。
鉄板リストの中から選ぶのは、安心と信頼の選択だよ。
“演奏しやすさ”と“聴かせる部分”の共存
勝ち曲は“歌いやすさ”と“聴かせどころ”の両立ができてる。
メロディーが美しくて難易度がちょうどいい。
その中にサビやハーモニーで一気に魅せられる部分がある。
“やりやすいのに評価される”っていうのが勝ち曲の条件なんだ。
転調や構成のドラマ性を活かすコツ
『COSMOS』なんかは転調がドラマチック。
本番でそこを思い切り表現すると“鳥肌ゾーン”に入るんだよね。
構成の盛り上がり部分をどう演出するかが、勝てる合唱に直結するんだ。
指揮者&伴奏者とのチームプレイ重視
いくら曲が良くても、指揮者や伴奏と噛み合わなきゃ意味がない。
指揮の合図、ピアノのリズム、クラス全体の呼吸。
この“チームプレイ”が決まると、本番で一気に仕上がる。
勝ち曲を選んだなら、指揮者・伴奏との練習に時間を割くのがマストだよ。
音域や人数に応じた“本当のおすすめ曲”は?
クラスによって男声・女声の人数が偏ることあるよね。
女声が多いなら透明感あるハーモニー重視の曲。
男声が多いなら力強い低音が映える曲。
音域に無理があると練習でもストレスになるし、本番で崩れる原因になる。
“人数と音域に合った曲”を選ぶのが実は一番大事。
無理に流行曲を追うより、クラス編成に合わせるほうが優勝の可能性は高まるよ。

伴奏がピアノだけでも映える曲とは?
全部の学校に豪華な編曲や楽器があるわけじゃない。
でも大丈夫。
ピアノ伴奏だけでも“映える曲”はいっぱいある。
『BELIEVE』『時の旅人』『大切なもの』なんかはピアノ一本でも十分に壮大さを出せる。
逆に伴奏に頼りすぎる曲は避けたほうが無難。
“ピアノだけで勝負できるか”を基準にすると、安定感ある演奏になるんだ。

練習のしかたはこうしよう!
基礎作りから始める
いきなり通し練習をしても雑になりがちなんだよね。
まずは発声やブレスを整えるところからスタートすると安定するんだ。
毎回同じ手順で声出しをすれば、体も心も「合唱モード」に切り替わるってわけ。
ピアノ伴奏に合わせて音階をそろえ、リズム感を共有するだけで全体の響きが変わるんだ。
基礎を軽視すると本番で声が固まったり、ハーモニーがばらついたりする可能性もあるよね。
部分練習で弱点を直す
曲を通すよりも、短いフレーズを徹底的に磨くほうが効果的なんだよ。
たとえばサビのハーモニーがズレやすいなら、そこだけを何度も繰り返したほうがいいよね。
男声と女声で分けて確認し、最後に合わせると安定感が出る。
掛け合いの場面では、先に入る声部をはっきりさせて、出だしを迷わないようにすると安心だよ。
部分ごとに完成度を高めていくと、通し練習の精度がぐんと上がるんだ。
指揮者と伴奏者の連携
練習の中心は指揮者と伴奏者ってことになる。
合図のタイミングやテンポの揺らぎは、何度も合わせて感覚を共有したほうがいいんだよね。
本番で「指揮と伴奏がズレた」となれば合唱全体が崩れるリスクが高い。
だからこそ、練習からしっかりアイコンタクトを取り、出だしと終わりを統一することが大事なんだ。
伴奏がピアノだけでも、息を合わせれば十分に迫力ある演奏になるんじゃない?
本番を意識した仕上げ
仕上げ段階に入ったら、立ち位置や入退場も含めて通し練習をしたほうがいいんだ。
本番の雰囲気を再現することで緊張に慣れるってわけ。
ただし直前に何度も通すと声が疲れてしまう。
前日は一度だけ通して、細かい修正に集中するほうがベターかもね。
体調管理も練習の一部と考えて、睡眠や水分補給を欠かさないことになるよ。
最後は「歌いたい」という気持ちを込めて歌えば、審査員の心を動かせるよ。

音をそろえるシンプル練習
合唱で一番むずかしいのは、声をひとつにまとめること。
同じ合唱曲を歌っていても、音程やリズムがそろっていないとバラバラに聞こえるよね。
音楽は「ひとつの和音」として響いたときに一番気持ちよくなる。
だからこそ、日常の練習ではシンプルに「同じ音を合わせる」ことが必要なんだ。
初心者でもできる簡単な方法を続けるだけで、驚くほど合唱団全体のレベルが上がるんだよ。
ここでは「音をそろえるためのコツ」を紹介するから、ぜひイメージしながら試してみてほしい。
みんなで同じ音を歌う「ド」の確認
一番シンプルなのは、みんなで「ド」を歌う練習。
ピアノで鳴らした基準音に合わせて全員が「ドー」と発声するだけなんだけど、これが意外と難しい。
音程のわずかな違いが分かるようになるまで練習を重ねる必要がある。
和音を作る前に、同じ音を合わせる経験を積むことが大事なんだ。
初心者でも効果を実感しやすい練習方法で、コツは隣の人の声をよく聞くこと。
周りとの違いを感じながら歌うと、自分の音のズレに気づけるようになる。
これが合唱上達の最初のステップなんだよ。
ピアノやアプリで基準音を決める
基準音を決めないと、合唱団全体で音がふらついてしまう。
だからピアノやスマホアプリを使って、常に正しい音程を確認する習慣が必要なんだ。
特に初心者は、自分の耳だけで音を合わせようとするとズレやすい。
楽器の助けを借りながら、音程を体にしみこませる方法が効果的だよ。
ピアノを使うとフレーズのイメージもつかみやすいし、アプリなら練習のご利用もお手軽。
便利なツールをうまく使うことで、初心者でも安心して合唱練習を進められるんだ。
隣の人の声をちょっとマネしてみる
音をそろえるためには、周りの声を聞く感覚を磨くことが大事だ。
自分の声ばかり気にしていると、パート全体から浮いてしまうんだよね。
そこでおすすめなのが、隣の人の声をちょっとマネすること。
発音や音色を意識して寄せてみると、自然と響きがまとまる。
もちろんコピーしすぎる必要はないけど、「周りと一緒に歌う」経験を積むのは効果的。
音楽って一人で作るものじゃない、合唱団全体で表現するものだってことを体で理解できる方法なんだ。
録音して聞き返すお手軽チェック
練習のときに録音して聞き返すと、自分たちの音程や発声の違いがよく分かる。
歌っているときは気づかない部分も、録音を聞けば「ここずれてるな」って一目瞭然なんだよね。
しかも録音なら何度でも聞き直せるから、直すポイントを具体的に見つけられる。
ピアノの伴奏と合わせて確認すると、リズムやブレスのタイミングもチェックできる。
こういう小さな方法が、合唱の上達を大きく後押ししてくれる。
初心者でもすぐできるシンプルなコツだから、練習にどんどん取り入れるといいよ。
※くわしくは「合唱コンで勝てるコツ 優勝するクラスがやっていること」
合唱コン、勝つより“伝える”を狙え
「うまく歌う」より「心に残す」。
それが本当の目標かもしれない。
練習の前に、“伝える”ってどういうことかを、少し考えてみよう。
歌詞を読んで“主人公の気持ち”を想像してみる
歌詞って、ただの文字じゃないんだ。
そこにいる主人公の気持ちを想像してみる。
誰に向かって歌ってるのか、どんな感情でその言葉を口にしてるのか。
想像すると、自然に声のトーンも変わる。
たとえば切ない歌なら、ほんの少し息を混ぜる。
「伝わる」って、そういう小さな工夫の積み重ねだよね。
曲に出てくる「山」と「谷」を見つける
歌の中には、必ず気持ちの“山”と“谷”がある。
静かなところ、盛り上がるところ。
全部を全力で歌うより、強弱の差をつけた方がずっと響く。
“谷”を丁寧にして、“山”で心を解き放つ。
まるで波みたいに、緩急があったほうが心地いい。
聴く人の心を“つかむ”最初の一行をつくる
歌い出しって、合唱の「第一印象」みたいなもの。
最初の一音で、聴く人の耳をつかむ。
ほんの少し間を置くとか、息を吸う音を生かすとか。
たったそれだけで、空気が変わる。
はじまりの一歩を大切に。
自分たちの“らしさ”をテーマにする
上手いクラスはたくさんある。
でも、「あのクラスらしい」って思わせたら、それが一番の勝ち。
優しい声、力強い声、温かい空気。
どんな色でもいい。
“らしさ”が出ると、合唱に命が宿るんだ。
※くわしくは「合唱コン 練習のポイントは勝つより伝える!」

実は知りたい:上手い人と下手な人の歌い方の差
合唱をやっていると「この人うまいな」「ちょっと下手かも」って差を感じることがあるよね。
その違いはセンスや才能だけじゃなくて、練習方法や発声の工夫にあるんだ。
ポイントを見ていこう。
音程感覚の違いが如実に出る
歌が上手い人は、音程を正確に取る耳が育っている。
周りの声に合わせる力もあるんだよね。
逆に下手に聞こえる人は、音が少し外れていたり、合唱曲の高さに対応できなかったりする。
音程感覚は練習すれば改善できるから、初心者でも毎日のレッスンで伸ばせる部分なんだ。
呼吸の安定が歌の安定を決める
上手い人は腹式呼吸がしっかり身についていて、長いフレーズも楽に歌える。
下手に聞こえるのは息が足りなくなって途中で音が揺れてしまうとき。
合唱団での演奏では特に息を長くコントロールする力が大切になる。
ボイトレや発声練習で鍛えれば誰でも改善できるよ。
声の響きにある「抜け感」と「こもり」
響きのある声は、それだけで聴いている人を惹きつけるよね。
上手い人の声はスッと前に抜けて、ホールの後ろまで届く感じがある。
逆に下手な人は声がこもってしまい、周りに埋もれることが多い。
響きは口の開け方や共鳴の工夫で大きく変わるから、意識して練習するとよくなるんだ。
表情と感情の乗せ方の差
歌は声だけじゃなくて表情でも伝わるんだよ。
上手い人は歌詞の意味を理解して感情を込めるから、聴く人に届く。
下手に聞こえるのは、ただ音を追いかけているだけで気持ちが乗っていないとき。
合唱でも一人一人が感情を込めることで全体の演奏が輝くんだ。
ここは勉強や練習で身につけられる部分だよね。
※くわしくは「合唱の歌い方 他との違い」

合唱の「並び」の基本:まずは定番フォーメーションを把握
本番の合唱コンクールで“勝ち”を狙うなら、まずは定番のフォーメーションをマスターしよう。
合唱団のパートをきちんと意識して、指揮者から見た並び順を理解すれば、音程もハーモニーもバッチリ整うかもね。
安定した配置は演奏の土台になるし、客席に届く響きにも差が出るんだよ。
だって、正しい位置取りが合唱の合格点を左右する“秘密兵器”になることだってあるじゃない?
SATBの王道:指揮者から見て左高声・右低声でシンプルに
SATBとは、合唱でよく使われる4つのパートの略称なんだ。
Sはソプラノで高い女声を担当し、メロディを歌うことが多い。
Aはアルトで低めの女声、内声を支えて全体のハーモニーを安定させる役割がある。
Tはテノールで高めの男声。ソプラノやアルトとバスをつなぐ大事な橋渡し役になる。
Bはバスで低い男声。合唱の土台を作って、音楽全体を支える存在だ。
この4つを組み合わせることで、合唱の響きは立体的になり、豊かなハーモニーが生まれる。
だから学校の合唱コンクールや合唱団の練習でも、一番スタンダードな編成として使われるんだよ。
場合によっては、男声が少ないときにSABにしたり、女声だけのSSAや男声だけのTTBBなどに変えることもある。
つまりSATBは、合唱の基本フォーマットであり、演奏を組み立てる出発点になるんだよ。
そして、合唱の基本中の基本といえば、SATB並び。
ソプラノとアルトを左側、テノールとバスを右側に置く方法。
この配置は合唱団でもっとも多く使われるオーダーで、指揮者も音部のバランスを取りやすいんだ。
前列に女声、後列に男声という並び順にすれば、見た目もきれいにそろうし、音楽的な解説もしやすい。
メリットはハーモニーが自然にまとまりやすいこと。
一方でデメリットもあって、前列の声が強すぎると後列の演奏が埋もれる可能性があるんだよね。
でもシンプルでわかりやすい並びだから、中学生の合唱コンクールでも安心して使える定番なんだ。
STBA/SA–TBの交差:男声でサンドしてバランス安定
もちろん、SATBだけが合唱の答えじゃないんだよね。
STBAとかSA–TBの交差並びは、男声を真ん中や両サイドに入れて“サンドイッチ”みたいにする方法。
こうするとソプラノやアルトの声が埋もれにくくて、全体のハーモニーが安定するよ。
とくにテノールが真ん中に入ると、音程の橋渡し役になって音楽がまとまりやすい。
逆にバスを中央寄せにすると、低音が真ん中から支えるから迫力が増すんだよ。
この配置は指揮者にとっても便利で、真ん中に男声がいることで音部ごとの響きが確認しやすい。
合唱コンクールで「うちの男声がちょっと弱い…」と悩む合唱団にもおすすめの配置なんだ。
半円・斜角・ブロック:会場の響きに合わせて音を飛ばす
また、まっすぐ並ぶだけが合唱じゃない。
半円にすると音が自然に前へ飛びやすくて、客席にまんべんなく届く。
斜角にすれば指揮者が全員を視認しやすくて、演奏の安心感もアップするんだ。
さらにブロック型、つまりパートごとに固めると、練習のときに音程が合わせやすい。
ただし声の混ざりが少なくなるデメリットもあるんだよな。
体育館や教室だと響きが死にやすいから、半円や斜角の方が有利ってこともある。
会場の性質を考えて、柔軟に並び順を変える工夫が勝敗を分けるんだよ。
段あり/段なしの列数と密度:人数と舞台で最適化する
合唱団の並びで意外と重要なのが段差。
ステージに段があると、後列のメンバーの顔や口が見えるから、表情や子音も客席に届きやすい。
段がない場合は密度を工夫するしかなくて、横幅を広げたり前後の間隔を詰めたりする必要があるよ。
列数を増やせば音が立体的になるけど、その分つられやすくなるリスクもあるよね。
逆に列数を減らせば安定するけど、迫力や厚みが減ってしまう。
だから「人数」「舞台の広さ」「曲の性格」を考えた配置こそが正解。
つまり、万能の並び順は存在せず、毎回オーダーメイドで決めるのが一番なんだ。
※くわしくは「合唱コンでの並び方 勝てるのはこれ!」
緊張するのってダメなことじゃない
緊張するのは、むしろ自然なことだよね。
「なんで自分だけ?」って思うかもしれないけど、合唱コンに出る人のほとんどがドキドキしてる。
だから、緊張そのものを敵にしても仕方ない。
まずは「緊張の構造」を知って、手なずける方向へマインドを変えていこう。
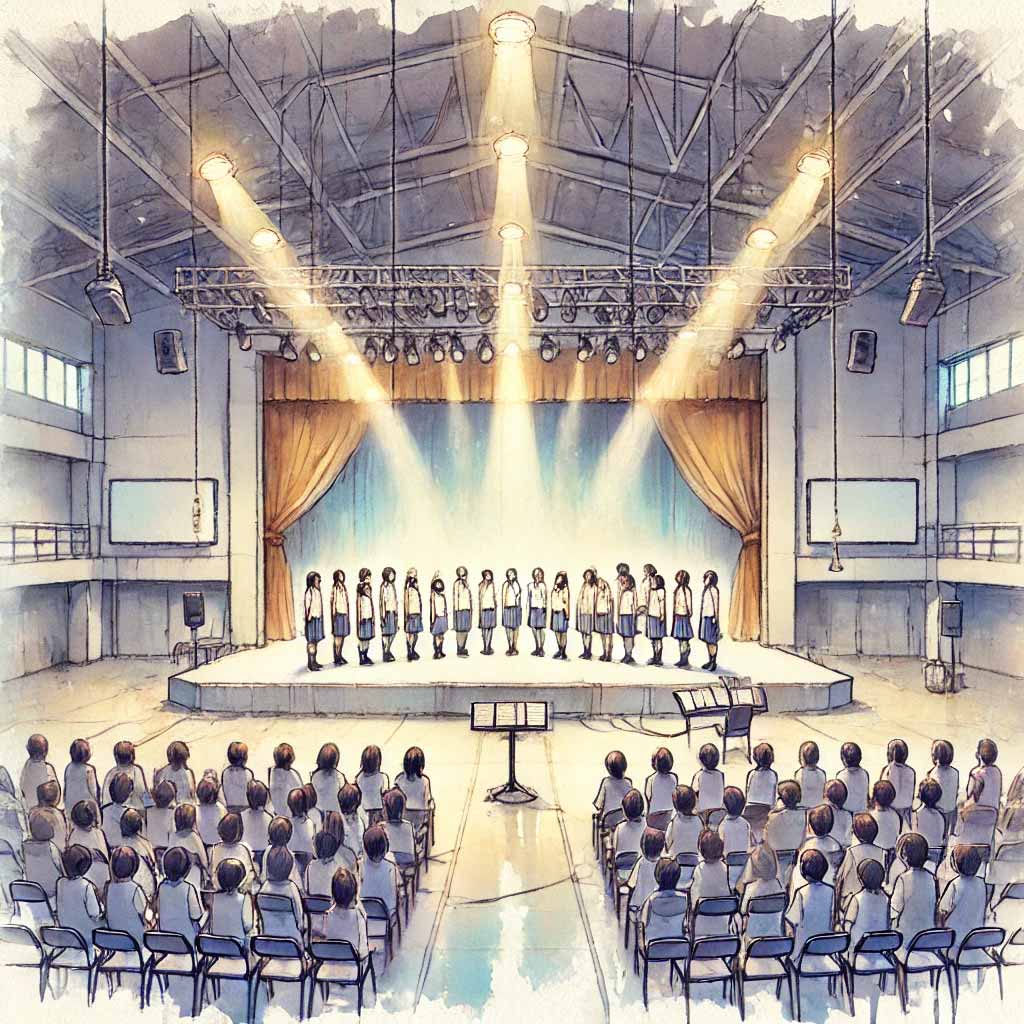
緊張=体の防衛反応。つまり“真剣スイッチ”
緊張って、体のセンサーが「今、重要な場面だぞ!」って警報を鳴らす反応なんだ。
心拍が速くなる、汗をかく、筋肉がちょっとこわばる、これ全部“防衛反応”なんだよ。
危険じゃないんだけど、体が準備モードに入ってしまってるだけ。
だから、緊張=失敗の前兆じゃなく、「本気出すよ」っていう体のスイッチって思えると気がラクになる。
「ヤバい…」って思うと余計ヤバくなる理由
「ヤバい、声出るかな…」「間違えたらどうしよう…」って思い始めると、脳は“警告モード”になるんだ。
そうすると注意力が散る、呼吸が浅くなる、筋肉が固くなる、音程が揺れる…という悪循環が始まる。
緊張がヤバいと感じるほど、緊張が強まるっていうパラドックス。
だから、最初に「ヤバいな」と感じた時点で、小さくブレーキをかける言葉を自分にかけよう。
緊張を消すより、“使う”って発想にチェンジ
緊張をゼロにしようとするのは、まるで心配性な親を無理やり黙らせるようなもんだ。
代わりに「この緊張、いいエネルギーとして使おう」って考えたほうが実は強い。
例えば、「このドキドキを合唱への集中力に変えよう」「今日はいつもより声が乗るはずだ」って前向きに受け止める。
“緊張を糧にする”という視点があれば、恐怖より味わいを感じられるかもね。
ドキドキの正体を知ると、ちょっと安心するんだ
「自分だけドキドキしてる」「どうしよう」って孤立感が強まると不安になる。
でも、ドキドキには名前があって、ちゃんとメカニズムがあると知ると、「ああ、これは体の仕様なんだな」って冷静になれる。
医学的な話だと、ストレス反応でアドレナリンが出て、交感神経が働くからこうなるっていう説明もある。
そういう事実を頭の片隅に入れておくの、案外心強いよ。
※くわしくは「合唱コン 緊張しない方法」
本番前に知っとこ!合唱コンの髪型でやっちゃいがちなミス
「髪型は気にしなくても平気かな」と思う気持ち、少しわかるよ。
でも、顔が隠れたり、飾りが目立ちすぎたり、ピンが外れたりすると、せっかくの歌に集中しにくくなるんだ。
きまりの範囲で、整えていこうね。

顔が隠れて声が通らない問題
前髪やサイドが目にかかると、表情が見えにくくなる。
耳の後ろで毛束を軽く留めて、トップは指先でふんわり整えると、顔まわりが明るくなって声も届きやすくなると思う。
後れ毛は少なめにすると、やわらかな雰囲気のまま歌いやすさも保てるよ。
「整えたつもり」なのに浮くやつ
編み込みや盛り髪は素敵だけれど、クラスの統一感から少し離れてしまうと目立ち方が強くなることもあるんだ。
小さめのリボンや細いカチューシャで色を合わせると、やわらかくまとまって写りもきれいだよ。
ティアラや派手なカラーは、きまりの確認をしてからにしよう。
本番でピンが飛ぶ悲劇
ピンは毛流れと反対向きに入れて、もう一本を交差させると留まりやすくなるよ。
後頭部の骨に沿わせると位置も安定しやすい。
ゴムは髪色に近いものをえらび、結び目は丁寧にぎゅっと。
高い位置のポニーは特に、結び目のゆるみを一度チェックすると安心だね。
そもそも“自分らしさ”が消えてる
全員まったく同じだと、ちょっと“作られた感じ”に見えることもあるよね。
同じスタイルでも、毛先のカールをそっと整えたり、細いリボンの素材を選んだりすると、ほどよい個性が残って雰囲気がやさしく仕上がるよ。
鉄板人気!合唱コンクールの定番ヘアスタイル4選
時間内に整えやすく、崩れにくくて、学校の場にも合う四つを集めたよ。
ポニーテール、ツインテール、ハーフアップ、シニヨン。
どれも“清楚さ”と“歌いやすさ”を両立しやすいから、まずはここから試してみよう。

ポニーテールは最強説
高い位置のポニーは元気な印象に。
耳より少し下のローポニーは落ち着いた雰囲気になるよ。
毛先を軽く内側に整えると、写真でのまとまりがよくなるんだ。
トップは指先でほんの少しだけふくらませると、やわらかな小顔見えになるよ。
ツインテールの清楚アップデート
耳のうしろで左右を同じ高さに結ぶと、シルエットが整って上品に見えるね。
毛束はやや細めにすると幼さが出にくい。
細いリボンのワンポイントや透明ゴムの重ね使いで、やさしい仕上がりにできるよ。
ハーフアップで「きちんと×かわいい」両立
耳より上だけをまとめて後頭部で留めると、顔まわりが明るくなって歌いやすいんだ。
ボブやミディアムでもきれいに決まりやすいのが長所だよね。
くるりんぱや細い三つ編みをそっと加えると、上品さがほんの少しアップするよ。
お団子ヘアで“ザ・ステージ感”を出す
低めのシニヨンは動いても崩れにくく、後頭部の丸みがきれいに見えるよ。
毛先をネットで包むと、長時間でも安心。
高すぎる団子や玉ねぎ結びは、学校によって印象が強く見えることもあるから、先生に一度たずねてみるといいかもね。
※くわしくは「合唱コンクールの“映える”髪型!!」
なぜ男子は合唱コンの練習でふざけてしまうのか
男子は「真面目にやるのは恥ずかしい」って気持ちがまず勝つこともあるし、本当は歌いたい気持ちもあるのに、みんながふざけてるとつい合わせちゃう。
照れ、プライド、声変わり、コンプレックス、そういったいろんな要素が絡み合ってるんだろうね。
照れとプライドが先に立つ
真面目に歌うと「女子にどう思われるかな」って気になって、声を出すよりも笑ってごまかすほうがラクに思うみたいだよね。
恥ずかしいというより、「真剣なのはダサい」って感じが勝っちゃうかも。
歌うのは「ダサい」という空気
合唱コン=「歌ってる自分がカッコ悪く見える場所」みたいな空気があると、男子ほどそれを強く感じちゃうかもね。
まわりが真面目に取り組むほど、その緊張感からふざけたくなる。
同調圧力でふざける流れに乗る
クラスで一人ふざけると、その空気が広がっちゃって。
「ああ、みんなそうしてるなら楽だな」って流れに乗っちゃうんだよね。
授業や練習で「合唱は得意じゃない」と言われると、まとまりづらくなるかも。
声変わりや音痴のコンプレックス
ちょうど声変わりの時期だから、自分の声に自信がなくて歌うのをためらう男子も多そう。
音痴気味なのも気になるし、「歌いたくないけどどうする?」って感じで、ふざけてごまかしちゃうこともあるよね。
※くわしくは「男子が合唱コンで真面目に歌わない理由」

合唱コン練習 時間が長い問題
合唱コンクールの練習って、気づいたら授業の予定を押しのけて入ってくるよね。
でも、なぜそんなことが起きるんだろう。
理由をちゃんと分解してみれば、先生も生徒も納得できる方法が見えてくるはずだよ。
ここでは「時間が長すぎるのはなぜか」をカジュアルに分解していくね。
時間の見積り甘すぎ問題を可視化する
合唱の練習って「まぁ30分で仕上がるでしょ」みたいなノリで始まることが多いんだよね。
でも実際は、発声で10分、パート練習で20分、合わせに30分、本番想定でさらに30分とか、どんどん膨れあがる。
結果、気づけば授業1コマが吹っ飛んでることもある。
学校って年度ごとに予定がパンパンだから、時間の読み違いが積み重なると大きなストレスになるんだよ。
生徒の側からしても「今日は早く帰れると思ったのに」って気持ちになるし、先生からしても「また授業が押すのか」とため息。
時間管理を甘く見積もるのは、合唱コンあるあるだよね。
指揮 伴奏 パート決めの初動が遅いと全部が遅れる
「指揮者どうする?」、「伴奏者だれやる?」って決めるのに1週間かかるクラス、けっこうあるんだ。
決めるのが遅れると、練習そのものが立ち上がらない。
さらにパート分けで「ソプラノ行きたい」、「いやアルトにして」ってモメると、そこでまた時間ロス。
結局、スタートが遅れた分を取り戻そうとするから、授業や放課後に負担が集中しちゃう。
早い段階で役割を確定してしまうだけで、時間のロスは劇的に減るんだよね。
完璧主義と早く帰りたい派のせめぎ合いを言語化する
クラスの中には「もっと合わせよう」、「もう一回やろう」って言う完璧主義派と、「もう帰ろうよ」、「塾あるんだよね」っていう早く帰りたい派が必ず存在する。
どっちも間違ってはいないんだけど、そのせめぎ合いで練習が長引くんだよ。
特に3年生なんかは「最後の合唱コンだから」と気合い入りすぎることもある。
逆に1年生は「え、なんでこんなにやるの」って温度差が大きい。
だからこそ、この違いを言葉にして「今日はここまで」って線を引かないと、延々と終わらないんだよね。
担任 音楽科 学級委員の三角関係を整理して役割を固定する
練習の時間をめぐって一番もめるのが、担任の先生と音楽科の先生、そして学級委員。
担任は「授業進度が気になる」、音楽科は「曲の完成度を上げたい」、学級委員は「クラスの団結を優先したい」。
この三角関係が整理されてないと、誰かの意見で練習が長引いたり、逆に削られたりするんだよね。
役割をはっきり決めて、「ここまでは音楽科の指導」、「ここからは担任の判断」みたいに分ければ、余計な延長がなくなる。
生徒だってそのほうが安心するんじゃないかな。
※くわしくは「合唱コンの練習 時間が長い問題」

練習期間が短くても間に合う“勝負曲”って?
練習時間が足りない……そんな状況でも間に合う曲はある。
例えば『虹』『COSMOS』は歌いやすさがあるから短期間でも仕上げやすい。
逆に難易度が高すぎる自由曲は、練習期間が少ないと破綻のリスク大。
限られた時間なら“定番でまとまりやすい曲”を選ぶのが正解。
練習で磨きやすい部分を強調すれば、短期決戦でも十分勝負できるよ。

表紙は「テーマ先行」が勝ち筋。まず“伝えたい一言”を決めよう
ひょっとしたら合唱コンのパンフの表紙を描いてって頼まれた人がいるかもしれないね。
合唱コンサートの顔となる表紙は、まずテーマからスタートするのが正攻法。
どんな想いを、余すことなく伝えたいのか、一言でズバッと決めると話が先に進むんだ。
みんなの気持ちが伝わるメッセージを一言で形にしよう。
スローガン→キービジュアル化:愛=ハート、平和=鳩、絆=手と手
例えば「愛」ならハート、「平和」なら鳩、「絆」なら手と手をつなぐモチーフにする、っていうのは黄金パターンだよね。
合唱も学校の雰囲気も、“表紙”というイラストを通して一目で伝わるようになるよ。
人を描くのが苦手なら、モチーフに逃げるのも大アリだぞ。
だれを想定?ペルソナ設定とクラス内アンケで方向決め
ペルソナっていうのは「この表紙を見てほしい相手を、ひとりのキャラとして想像すること」だよ。表紙は見る人を想定するのが肝心なんだ。
ペルソナっていう言い方が難しければ、「応援に来る家族」「友達」「後輩」などをイメージしてみて。
クラス内でアンケートをして、「何にぐっとくる?」「好きな色は?」なんて聞いて決めるのもいい感じじゃない?
季節感&学校カラーを味方に:春や秋の空気も描き足す
合唱コンクールの開催時期が春なら桜や新緑、秋なら紅葉や秋空を背景にちょっと入れるだけで、“学校らしさ”がアップするよ。
学校のカラー(校章やユニフォームカラー)もさりげなく使えば、全体に統一感が出て“イラスト”が学校そのものを語り出すかも。
これはNG?著作権・校則に触れそうなモチーフ早見表
有名キャラやCDジャケット、そのままのロゴを使うのは基本アウト。
教室に貼るポスター用でも、SNSで使うときはNGの可能性があるから気をつけて。
フリー素材を使うなら、クレジット表記が必要かどうか確認しよう。
校則もチェックだよ?
※くわしくは「合唱コンの表紙絵はテーマ先行で考える!」

合唱コンクールで刺さる四字熟語、まずは王道から
合唱コンなどの学校行事で定番なのが「スローガンを作る」こと。
キミも頭を抱えているかもしれないね。
実はそんな時に頼りになるのが四字熟語。
深い意味とおさまりのいい4文字というのがスローガンにピッタリなんだ。
団結で押す(一致団結/一心同体/和衷協同/戮力協心)
合唱コンクールで一番に思い浮かぶのはやっぱり「団結」だよね。
一致団結や一心同体なんて言葉は、まるで合唱専用に作られたかのようなピッタリ感がある。
クラスがまとまって声を出す時、この四字熟語が壁に貼ってあるだけで雰囲気が締まるんだ。
和衷協同とか戮力協心なんて、ちょっと難しいけど響きがカッコいいし、大人からの評価も高めだろう。
表現力を上げるには、まずは心をひとつにすること。
スローガンを掲げると、自然と気持ちもまとまるものだ。
粘りと成長(切磋琢磨/百折不撓/不撓不屈/奮励努力)
練習って地味でつらい時もあるけど、そういう場面に力をくれるのが「切磋琢磨」みたいな熟語だ。
互いに磨き合う姿勢は、音をそろえる合唱の基本でもある。
百折不撓、不撓不屈なんて言葉は「練習がキツいときもやめない!」という気持ちを支えるよね。
奮励努力ってシンプルだけど、コツコツやるしかない合唱練習のリアルを映している。
粘り強さこそクラス全体の成長に直結するんだ。
気迫と格(威風堂々/意気軒昂/真剣勝負/全身全霊)
本番の舞台に立つときって、練習の雰囲気と全然違うよね。
緊張感の中でも気迫を出すには「威風堂々」なんか最高の言葉だ。
意気軒昂は「俺たちまだまだやれるぞ」って空気を作る。
真剣勝負とか全身全霊はストレートで、応援団のようにパワーを前に押し出す感じ。
クラスの表現力が爆発する瞬間に、この手の熟語が背中を押してくれるんだ。
多様性をハモる(桜梅桃李/十人十色/和気藹々/明鏡止水)
合唱の面白さは「声が違う人たちがそろう」ことにある。
桜梅桃李や十人十色は、その違いを肯定して輝かせる熟語。
和気藹々は「楽しくやる」って雰囲気づくりにぴったりだし、明鏡止水は逆に静けさと集中を意識させる。
多様な個性をうまく調和させるのが合唱の真骨頂。
スローガンがそこを表現していたら、先生も観客も納得しちゃうんじゃない?
※くわしくは「合唱コンクール スローガンの四字熟語 使える100!」

合唱コンの「紹介文」って結局なに書けばいいの?
観客も審査員も、最初に耳に入るのは紹介文だ。
クラスの空気、曲の見どころ、練習で生まれた物語、そして今の意気込み。
この四点がそろえば、合唱の世界にすっと連れていける。
長く語るより、要を射る。
時間は短く、印象は濃く。
だれ・どのクラス・何を歌うの三点セットで土台づくり
冒頭は名乗りと曲名で一発明快に行く。
「二年三組、担任は山田先生。
私たちが歌うのは『旅立ちの日に』!」のように、基本情報を一文で並べる。
そこで迷うと以後が崩れる。
クラス名と曲名の言い間違いは練習で必ず矯正する。
テンポよく言い切れば、歌声が始まる前から空気が締まるんだ。
クラスの空気が伝わるエピソードを一口サイズで
「元気」「仲良し」だけでは伝わらない。
休み時間の合唱自主練で出たアドバイス、先生の一言で静まった瞬間、音取りで泣きそうだった同級生を支えたハナシ。
事実を十五秒で。
固有名詞を一つ入れると情景が立つ。
内輪ウケは避けつつ、私たちらしさを小皿で出すのがコツだよね。
歌詞の要旨と見どころを30秒で切り出すコツ
歌詞は物語の芯だ。
「別れと再会を歌う曲で、サビ前の弱声から一気に広がるハーモニーが聞きどころ」のように、テーマ+聴き所を二文で。
音程や強弱の山を一か所だけ指定すると、客席の耳がそこへ向く。
合唱は流れの芸術。
流れのどこに光を当てるかを示してあげよう。
ラストは意気込みでビシッと締める
最後は視線を前に上げて、短く強く。
「私たちは今日の練習の全てをここに置いていく。
どうぞ聴いてください」
順位ハックよりも、届けたい姿勢。
審査員も観客も、人の気持ちに動かされる。
言い切る。
それが開幕のスイッチだ。
※くわしくは「合唱コン 紹介文の書き方 絶対ウケるキラーな一文100!」

感想文を書くまでが合唱コンだ!
合唱コンが終わると、感想文を書くことが最後のイベントになる学校が多いよ。
感想文では「行事を通じてどう成長できたか」を書くと完成度が上がる。
先生や保護者はここを読むと「この子はよく考えてる」と思ってくれるんだ。
自分が気づかなかった変化を掘り出すのがコツ。
次の4つの着眼点を意識してみよう。
人前で声を出す度胸がついた
合唱コンクールは大勢の前で声を出す練習の連続だ。
「最初は恥ずかしかったけど、最後は堂々と歌えた」と書けば、度胸がついた成長を表現できる。
学校生活で人前に立つ経験は少ないから、そこで得た勇気は大きい。
「緊張したけど乗り越えた」と正直に書くと感動につながるんだ。
友達との距離がぐっと縮まった
練習を通して友達と近づけた話もおすすめだ。
「声を合わせるうちに仲良くなった」「ケンカもあったけど信頼できるようになった」など、人間関係の変化を書くといい。
感想文に友情を絡めると温かみが出るし、クラス全体で一生懸命取り組んだ雰囲気が伝わる。
保護者や先生も「人間的に成長した」と受け取ってくれる。
緊張を味方にできるコツを覚えた
「緊張したけど、それを力に変えられた」と書くのもポイント。
「手が震えたけど深呼吸したら落ち着いた」「ドキドキが声を大きくしてくれた」など具体的に書くと伝わる。
緊張をネガティブに書くだけじゃなく、プラスに変えたことを強調すれば、読み手に前向きな印象を与えられる。
これは来年にも活かせる成長になるよね。
「次はもっとやれる」と思えた瞬間
感想文の締めには「次につながる意欲」を入れるときれいに終われる。
「来年はもっと声を出したい」「次は指揮をやってみたい」など、自分の未来につなげる視点だ。
学校生活の行事は毎年あるから、挑戦の気持ちを書けば先生も喜ぶ。
「合唱コンで自分が成長したから、次も頑張りたい」と書けば、ポジティブなラストになるんだ。
※くわしくは「合唱コンクールの感想文 書き出し例100選!」

まとめ
合唱コンクールで勝てる曲は、ランキングや流行だけじゃなく、自分たちの声質、人数、練習時間、そして“歌いたい気持ち”に合わせて選ぶことがポイント。
定番曲もアレンジや工夫で輝くし、自由曲には爆発力がある。
最後はクラスの熱量とチームワーク。
審査員や観客の心を動かせば、それが一番の“優勝”になるんだよね。

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。


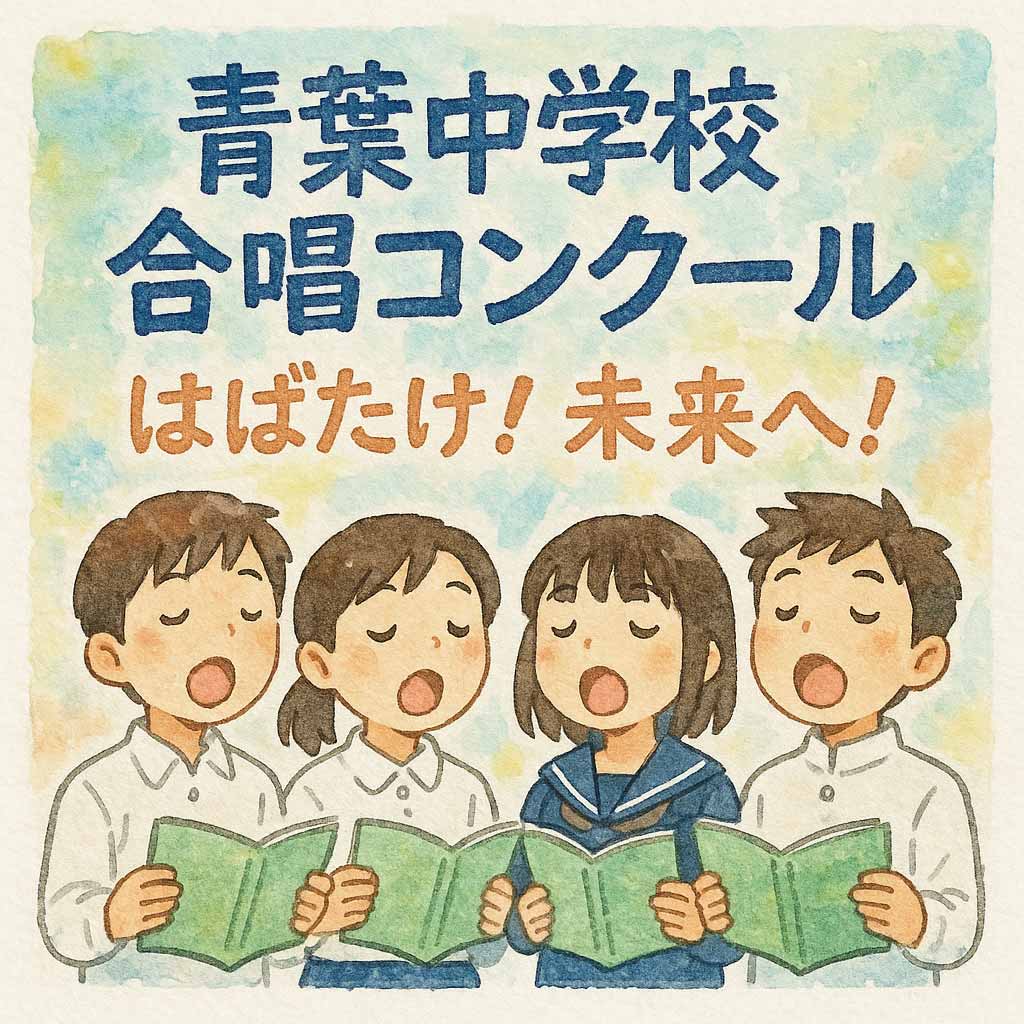

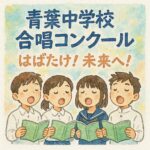
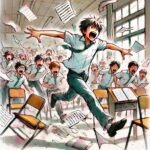


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません