生徒会の役割 各役員は何をするの?
- 1. 生徒会ってそもそも何してんの?一年のざっくりロードマップ
- 2. 毎週やってるアレコレ—地味なのに超大事な定番仕事
- 3. 生徒会の役職
- 4. 副会長ってどんなポジション?
- 5. 生徒会会計ってどんな役職?—お金の番人だけじゃない!
- 6. 会議とメンバーの動き方—「総会」とかって何?
- 7. 行事のウラ側—文化祭も体育祭も準備がカギ
- 8. 広報とお金の管理—掲示物から予算まで全部やる
- 9. 生徒会のやりがい:自分の意見で学校がちょっと変わる達成感
- 10. アニメの生徒会と現実の差—意外と地味?でも面白い
- 11. 生徒会と勉強、ケンカさせないコツ
- 12. 忙しさのリアル—授業や部活とどう両立?
- 13. 選挙で勝つコツ—演説・公約・ポスター作り
- 14. 立候補の“きっかけ”を面白く言おう
- 15. そもそも公約って何?
- 16. 良い公約の条件とは?
- 17. 「公約が浮かばない…焦りがちなあなたへ」
- 18. スピーチが苦手じゃ生徒会は無理?
- 19. 生徒会選挙演説の全体像—“当てにいく型”で勝ちにいく
- 20. 「投票してもらえる生徒会ポスター」って何?
- 21. 実は気になる③ 生徒会で得られるスキル—将来にも役立つ!
- 22. まとめ
生徒会ってそもそも何してんの?一年のざっくりロードマップ
生徒会は学校生活を楽しくスムーズに動かす司令塔だ。
会長副会長書記会計などの役員と本部メンバーが各委員会と協力して全校の声を拾い行動に変えていく。
行事を動かすだけではなく環境を整えるために計画準備実行振り返りのサイクルを一年中回している。
山場を見据えて少しずつ仕込みを進めるのがコツになる。

年間カレンダーで見る「ここが山場!」なイベントたち
春は新入生歓迎会と委員会の立ち上げと総会準備でいきなり忙しい。
夏から秋は文化祭や体育祭が続き学校全体が一つの大きな舞台になる時期だ。
冬は反省会と次年度への引継ぎそして役員選挙で締めくくる。
それぞれの山場に向けて逆算し小さなタスクに分けて動くと失敗しにくいよ。
学期ごとの仕事の濃さと“人手足りない問題”
一学期は顔合わせとチーム作りとルール確認が中心で土台づくりの季節。
二学期は行事ラッシュで放課後に準備が続き時間のやりくりが勝負になる。
三学期は資料整理と引継ぎがメインで期末との両立が意外と大変だ。
どの学期でも人手不足は起きるので部活動やクラスに応援を頼む段取りが鍵になる。
会議の種類と「早く終わらせる」小ワザ
総会、評議会、委員会、定例ミーティングと会議は多い。
議題を事前に絞る、発言は簡潔にする、決定はその場で記録するという三点を守ると短時間でも成果が出るよ。
終了前に宿題と担当を確認して次回へつなげると仕事が止まらないで済むんだ。
公約から反省会までの“生徒会サイクル”を翻訳するとこうなる
選挙で掲げた公約を企画に落とし込み、全校に告知して準備を進め、本番を動かす。
終わったら、良かった点と改善点を反省会で整理して、次へ活かす。
この回転を繰り返すほど、活動の質も学校の雰囲気もレベルアップしていくんだ。

毎週やってるアレコレ—地味なのに超大事な定番仕事
華やかな行事は年に数回で日常は地味だけど欠かせない定例業務の積み重ね。
この基盤がしっかりしているほど大きな企画もうまく回るよ。
朝礼・表彰・式典でスベらないための下準備
台本を読み込む、声量と速度をチェックする、マイクと放送設備を事前テストする。
導線と合図を先生と確認して本番の不安を減らす。
これら準備の丁寧さが全校の集中を生むんだよ。
あいさつ運動/校内パトロール/備品チェックの裏技
昇降口の明るい挨拶は空気を変える即効薬だ。
廊下、トイレ、掲示を見回り、問題は委員や先生へすぐ共有する。
備品リストで破損や不足を早期発見して、行事当日の混乱を減らそう。
生徒会だより・掲示・SNS…ネタ切れしない発信術
季節と行事に合わせてテーマを決め、写真と短文と見出しで読みやすくする。
委員会や部活動から素材を集めればネタは循環して増えていくはず。
SNS可の学校では短い動画も効果的だよね。
目安箱や相談の声を“放置しない”ためのさばき方
受け付けたことをまず全校に伝えるのが信頼の第一歩。
対応できない案件でも理由と代替案を説明すれば納得が得られるはずだよ。
進捗を掲示で見える化すると声が集まりやすくなるんだ。
※くわしくは「生徒会の活動 具体例を挙げてみる」

生徒会の役職
生徒会って、何をするのか分からないまま「なんかやる」というイメージだけある人も多いかもね。
でも、実際は学校行事の企画や委員会との連携、代表として生徒の声をまとめて管理すること、そして選挙の運営までやっているんだ。
中学生のみんなが「ちょっと役に立ってる」と感じる企画を考えて、学校生活をもっと面白くするのが生徒会の仕事だよね。
こうした活動には、会長や副会長、書記・広報、会計・監査など、いろんな役員が関わっている。
次に、それぞれの役割を詳しく見ていくよ。
会長—生徒会のボス…というよりみんなのまとめ役
会長はボスというより、みんなの声を集めて、学校や先生と話し合いをまとめるリーダーだよね。
問題が起きたときに「こうしたらいいかも」と思ったら、その提案を実現する中心になる。
責任が重い分、選挙に当選したときの達成感はすごいかもね。
副会長—会長の相棒で、困ったらすぐフォローする人
副会長は、会長が困ったときにすぐ助ける裏方のまとめ役だよ。
忙しい会長にかわって、会議を仕切ったり、全校イベントの準備をサポートしたりする感じだ。
縁の下の力もちってやつで、副会長なしでは生徒会が動かないことも多いかもね。
書記・広報—やったことをちゃんと形に残す&広める担当
書記は議事録を書いたり、どんな話が出たかをまとめる役だよね。
広報はそれをポスターにしたり、放送委員会やSNSで伝えたりして、みんなに参加を呼びかける人だ。
せっかくいい企画があっても、知らせなければなかったことになるから超重要だよ。
会計・監査—お金と数字の守護神
生徒会のお金を管理するのが会計の役割だ。
監査はその収支をチェックして、おかしなことがないか見張る人になる。
予算を考えてイベントを実行するためには、この管理がゆるいと全部破たんすることもあるから、マジ大事だよね。

副会長ってどんなポジション?
会長の相棒ポジ—右腕であり影武者
副会長は生徒会長の右腕だよね。
会長が忙しい時や欠席の時に代理で前に立つ影武者でもある。
学校の活動が止まらないように段取りを回す仕事。
生徒や先生に説明して納得を作る役割。
地味だけど実現の要。役職の重さを体で知る経験になる。
みんなの橋渡し—クラス・先生・委員会ぜんぶ
副会長は生徒の声と先生の意見をつなぐ橋渡し。
クラス代表や委員会メンバーの要望を整理して回答の道筋を作る。
感情のぶつかりをほどく潤滑油。書記や会計など他の役員とも手を取り合う。
学校全体を見渡す視点が育つよね。
ピンチの火消し役—トラブル前にも動く
文化祭の準備が遅れた、告知が伝わらない、役員の予定が合わない。
そんな時に副会長が早めに芽を摘む。
原因の仮説を出し、具体案を並べ、関係者を小さく集めて意思決定。
火事になってから慌てない。先回りの設計がうまいと強いだろう。
黙って裏方—準備も後片付けもこなす
副会長は目立つ演説だけじゃない。
資料づくり、議事録、タイムテーブル、備品の配置、片付けまで淡々と回す。
誰かが気づく前に動くから騒ぎにならない。
拍手は少ないけど、終わった時の達成感は大きい。影の実力者って感じだよね。
※くわしくは「生徒会 副会長ってなにするの?」

生徒会会計ってどんな役職?—お金の番人だけじゃない!
会計は生徒会のお金の番人だけどそれ以上に学校の活動をつなぐ調整役だよね。
予算の管理や書類の作成や先生との確認や役員への回答など実務が多い。
会長や副会長や書記や監査や各委員と動きながら行事の支出を安全運転にする。
代議員(クラス代表)からの相談に耳を傾けて必要な手順を案内するのも仕事だ。
裏方だけど影響は大きいという現実を知っておこう。
会計の一日ルーティン—登校から下校までにやること
登校したらまず前日の領収書をファイルに入れて出納の数字を確認する。
朝の会で先生に今日の手続きが必要な支出を共有。
休み時間は委員や部活の予算相談を受けて必要書類を案内する。
昼は副会長や書記と申請の抜け漏れチェックをして会長に要点を報告だ。
放課後は見積や申請のスタンプ確認と保管場所の整理で締める。
なかなか気が抜けない仕事なんだよね。
会計がいないと学校行事はこうなる—リアルな困りごと
会計が不在だと物品が買えなかったり、領収書が集まらなかったり、予算オーバーの理由が説明できなかったりという三重苦になる。
文化祭や体育祭の準備が止まり、会長と副会長が先生へ苦い説明をする羽目になる。
部活の大会費や交通費も遅れが出て、活動予定に支障が出るよね。
つまり、資金の流れが止まると生徒会の活動そのものが止まる。
会計は見えないところで全体を動かす潤滑油だ。
会長や副会長との関係性—仲良し?それともビジネスライク?
会長や副会長との関係性は、仲良しにもなれるし、完全にビジネスライクにもできる。
学校によって雰囲気は違うが、基本は仕事の話をていねいに、短く、正確に伝えることだ。
数値や期日、根拠を先に示すと、会長や副会長、生徒会長の判断が速くなる。
雑談は仲を深める潤滑油だけど、お金の話は感情抜きで、事実から入るのが安全だ。
信頼が付くと、予算提案が通りやすくなるよね。
お金以外にやってる意外な仕事
お金以外にも、会計には意外な仕事がたくさんある。
たとえば、備品の在庫チェック、行事の買い出しへの同行、委員会で回すお知らせ文の作成や、説明用の図やポスターづくりなど、制作系の作業も多い。
体育祭や文化祭などの本番当日に備えて、教室や体育館の机・椅子の配置や、延長コードなどの配線図を作っておき、当日の混乱を防ぐこともある。
また「代議員」と呼ばれる、各クラスの代表生徒からの質問や要望にすぐ答える窓口になることも多い。
つまり会計は、お金を管理するだけでなく、学校行事や日常運営の裏側を知り尽くしている立場でもあるのだ。
※くわしくは「生徒会 会計って何するの? 数学が苦手でも大丈夫?」

会議とメンバーの動き方—「総会」とかって何?
生徒会の活動って、実は会議なしでは成り立たないんだよね。
学校生活の中で生徒会がやることは、ほとんどが企画や問題の解決に関わることだから、話し合いの場は超重要だ。
ここでは総会や評議会、委員会とのコラボ、そして顧問の先生とのやり取りまで、会議の実態をざっくり見ていくよ。
生徒総会—全校生徒でワイワイ話して決める場所
生徒総会は、全校生徒が集まって意見を出し合う一大イベントだよね。
年度の活動方針や予算案、学校行事の計画などを、みんなで確認して承認する場になる。
普段は意見を言わない生徒も、この日ばかりは発言してくることもあるから、準備はぬかりなくやる必要があるよ。
評議会—委員長や学級代表が集まる作戦会議
評議会は、各クラスの代表や委員長が集まって話す作戦会議だ。
ここで決まったことはクラスや委員会に持ち帰って、具体的な行動に落とし込むことになる。
会長や副会長にとっては、全体を動かすための重要な接点になるよね。
委員会とのコラボ—体育・文化・生活…みんなで分担
生徒会の執行部だけじゃなくて、体育委員会や文化委員会、生活委員会、放送委員会などと連携するのが基本だよ。
行事の実行委員会を立ち上げることも多く、それぞれの専門性を生かして動くことで、大きなイベントが成功するんだ。
お互いの仕事を理解して協力することが、結果的に学校全体を盛り上げることになるんだよね。
顧問の先生とのやり取り—ここを間違えると全部ストップ
生徒会には必ず顧問の先生がついていて、活動を支えてくれるよ。
でも、何でも自由にできるわけじゃなくて、学校としてのルールや予算の使い方は先生と相談しないと動かせない。
提案や企画書はきちんと作成して説明するのがマナーだし、信頼を積み重ねることが活動をスムーズにする近道になるんだ。

行事のウラ側—文化祭も体育祭も準備がカギ
生徒会の仕事って、学校行事の裏方として動くことがかなり多いんだよね。
文化祭や体育祭みたいな大イベントはもちろん、式典や地域との合同イベントだって、生徒会の手が入っていることが多い。
華やかな表舞台の裏で、実は地味だけど大事な準備が山ほどあるんだ。
年間スケジュール作り—行事がカブらないようにパズルゲーム
年度の最初に、生徒会は年間の学校行事スケジュールを作成するよ。
これは、体育や文化系のイベントが重ならないようにするパズルみたいな作業だ。
クラブ活動や委員会の予定とも調整しないといけないから、意外と頭を使う作業なんだよね。
企画書とかの紙仕事—めんどくさいけど未来の自分が助かる
行事をやるときには、必ず企画書や予算案、当日の運営計画を作る必要がある。
これはめんどくさい仕事だけど、しっかり作っておくと先生に説明しやすいし、来年の実行委員会にも資料として残せる。
去年こうだったから今年はこうしようと改善できるのは、この紙仕事があるおかげなんだ。
当日の動き方—タイムテーブルを制する者が行事を制す
行事当日は、タイムテーブルを見ながら人員配置を指示したり、進行状況をチェックするのが生徒会の役目だよ。
体育祭なら競技ごとの準備、文化祭ならステージや模擬店のスケジュール管理。
これをミスると全体が止まっちゃうから、責任重大だよね。
ふりかえり—「次はもっと楽しく!」のためのメモ
行事が終わったら、その日の反省点や良かった点をまとめる。
これは次の年度のための宝物みたいな情報になる。
参加した生徒からの意見も集めておくと、次回の企画や改善にめちゃくちゃ役立つんだよね。

広報とお金の管理—掲示物から予算まで全部やる
生徒会の活動は、広報とお金の管理がないと回らないんだよね。
どんなに面白い企画や行事でも、みんなに伝わらなければ参加者ゼロになるし、予算が足りなければ実現すらできない。
だから、この二つは地味だけど超重要な役割なんだ。
広報のキホン—誰にいつどうやって伝えるかが命
広報は、誰に、いつ、どの方法で情報を届けるかを考えるところから始まるよ。
ポスターや校内放送、SNS、クラスでの説明など、方法はいろいろ。
タイミングを間違えると、参加者が集まらないという悲しい事態になることもあるんだ。
予算の決め方—お金が足りないときは優先順位バトル
予算は年度初めに決めることが多いけど、行事や企画が増えると足りなくなることもあるよね。
そんなときは何を優先するかをみんなで話し合う必要がある。
学校生活の中で一番効果があるものから順に配分するのが鉄則だ。
会計&監査—レシートと数字のにらめっこ
会計は、生徒会のお金の出入りをすべて記録する仕事。
監査は、その記録に間違いがないかをチェックする役割だよ。
細かい数字を扱うから大変だけど、これがしっかりしていないと学校や先生からの信頼がガタ落ちになるんだ。
トラブル回避—お菓子の差し入れも実はルールあり
寄付や差し入れも、生徒会が受け取るときはルールがあることが多い。
お菓子や飲み物でも、事前に先生の許可が必要な場合があるんだ。
これを知らずに受け取ると規則違反になることもあるから、注意が必要だよね。
生徒会のやりがい:自分の意見で学校がちょっと変わる達成感
自分の「こうしたい」が、ちゃんと学校に届くってうれしいよね。
小さな提案でも、現実が少し動いた瞬間に「おお、やった!」ってなる。
そんな経験をしたら、生徒会の楽しさが一気にわかると思う。

日常の「小さな改善」が積み重なる快感
「廊下の掲示をもうちょい見やすくしたい」。
「図書室の本をもっと使いやすくしたい」。
そんな小さな提案が実現しただけで、テンションが上がる。
それを何回か積み重ねていくと、「学校って自分たちの力で変えられるんだ」って思えてくる。
自分の声が形になるって、けっこう気持ちいいよ。
校則や施設提案、先生との交渉ストーリー
校則や施設のことを先生に相談するとき、ちょっと緊張するよね。
でも、ちゃんと理由を考えて話せるようになると、先生たちも真剣に聞いてくれる。
思いどおりにならなくても、「次はこう言えばいいかも」ってわかってくる。
話し方とか伝え方が上手くなるのも、生徒会ならではの成長だと思う。
改善が形になるまでのドラマと壁
計画して、話し合って、準備して、やっと完成。
その間には、意見がぶつかったり、時間が足りなかったり、うまくいかないこともある。
でも、最後に「できた!」って瞬間を迎えたときの感動といったら…。
ちょっと泣けるレベル。
「私がやったんだ」感のメンタル効用
自分の提案で学校がちょっと変わったとき、「これ、自分が関わったんだ」って思える。
その感覚が自信になる。
他のことも頑張ってみようかな、って気持ちに自然になるんだ。
生徒会って、実は“自己肯定感アップ装置”でもある。
※くわしくは「生徒会の仕事 4つのやりがい」

アニメの生徒会と現実の差—意外と地味?でも面白い
アニメやドラマに出てくる生徒会って、やたら権力があって、学校の全部を動かせるみたいに描かれること多いよね。
でも、現実の生徒会はもっと地味で、できることにはちゃんと限界があるんだ。
とはいえ、工夫次第で学校生活を確実に良くできるし、やりがいもあるんだよね。
校則って変えられるの?—意外とハードル高め
生徒会長になったら校則変えられるんじゃないと考える人もいるけど、そんなに簡単じゃない。
校則は学校全体の方針や地域の教育委員会の意見も絡むから、変えるには長い時間と根拠が必要だ。
でも、小さなルール改善から始めることは十分できるよね。
先生との交渉ワザ—「私」じゃなく「みんな」を主語にする
先生にお願いを通すときは、自分がやりたいじゃなくて全校生徒のためになるという形で話すのがコツだよ。
そうすると、先生もじゃあやってみようかという気持ちになりやすい。
これは生徒会の役員だけじゃなく、社会に出ても使える交渉術になるんだよね。
小さな改革—備品直したり、目安箱つくったり
いきなり大きな改革は無理でも、小さな改善ならすぐにできることも多い。
壊れた備品を修理したり、要望を集める目安箱を置いたりするだけで、学校生活がちょっと便利になるよ。
そういう積み重ねが、生徒会の存在感をじわっと高めていくんだ。
外部とつながる—地域イベントで学校アピール
地域の清掃活動や祭りに学校として参加する場合、生徒会が中心になることも多いよ。
こういう活動は地域とのつながりを深めるチャンスだし、学校のイメージアップにもなる。
外との交流は、普段の学校生活では味わえない経験になるんだよね。
生徒会と勉強、ケンカさせないコツ
生徒会も勉強も大事。
でも、どっちも本気で頑張るとぶつかることがあるよね。
そんなときは「どちらかを削る」じゃなくて、「うまく共存させる」考え方をしてみよう。
自分の時間を整理してあげるだけで、ちょっと気持ちが軽くなるよ。

時間が全部吸われる!? 自分の1日の“使い道”をちゃんと見える化しよう
まずは、朝から夜まで何に時間を使ってるかを書き出してみて。
授業、部活動、生徒会、スマホ、SNS。
一度見える形にすると、「意外とスマホタイム長いな」とか「ここに勉強入れられそうだな」って発見がある。
時間は“見つける”より“作る”もの。
その意識を持つだけで、日々の焦りが少し減るよ。
「やるべきこと」と「やりたいこと」を分けるだけで超ラクになる
生徒会って、やろうと思えばいくらでも仕事があるよね。
でも、全部に手を出すとどこかで限界がくる。
「これは絶対やる」「これは余裕があればやる」って分けておくと、気持ちが軽くなるよ。
“全部やらなきゃ”じゃなく、“できる範囲でベストを尽くす”。
それで十分なんだ。
放課後・昼休み・通学中を“ちょい勉タイム”に変える裏ワザ
まとまった時間が取れなくても大丈夫。
放課後の10分、昼休みのすき間、通学中の5分。
そういう“小さな時間”を集めて勉強すれば、1日でけっこうな量になる。
単語カードをめくるだけでもいいし、プリントを眺めるだけでもOK。
「今ちょっとやった自分、えらいな」って思える瞬間が増えるよ。
「それはムリっす」と言える勇気を持つのも生徒会スキルのひとつ
全部引き受けるのはやさしいけど、ちょっと危険。
疲れたときは「今週は他の仕事が多くて…」って、正直に伝えていいんだよ。
頼ることも、立派なチームプレー。
自分を追い詰めすぎず、余白を残してあげよう。
※くわしくは「生徒会と勉強は両立できる? 無理ゲーにしない生徒会」

忙しさのリアル—授業や部活とどう両立?
生徒会って、華やかなイメージのわりに裏ではかなり忙しいんだよね。
授業も部活もある中で、会議や行事準備をこなすから、時間管理は必須スキルになる。
ここでは、生徒会役員のリアルなスケジュール感と、両立のコツを見ていくよ。
週の動き方—定例会議+臨時対応=意外と忙しい
生徒会には、週に一回以上の定例会議があることが多い。
さらに行事が近づくと、臨時会議や準備作業が増えてくる。
突然の問題に対応することもあって、思ったより放課後がつぶれることもあるんだよね。
テスト前—最低限やることだけ残すサバイバル術
テスト前は、生徒会活動も最低限に絞ることが多い。
大事な会議だけ出席して、細かい準備は後回しにすることもあるよ。
勉強とのバランスを崩すと本末転倒だから、この時期は潔くセーブするのも大事だね。
部活との両立—顧問同士で相談して免除もあり
部活と生徒会を両方やっている人は、行事や会議のときにどちらを優先するかが悩みどころ。
場合によっては、顧問の先生同士が話し合って免除をくれることもある。
無理して両方全力だと体力も成績も落ちちゃうから、うまく調整するのがコツだよね。
ブラック化防止—仕事は抱え込まずシェア!
生徒会の役員って、真面目な人ほど仕事を抱え込みがち。
でも、それだと疲れ果ててしまうから、他のメンバーや委員会にも頼るべきだよ。
仕事を見える化して分担すれば、活動もスムーズになるし、学校生活も楽しくなるんだ。

選挙で勝つコツ—演説・公約・ポスター作り
生徒会役員になるには、まず選挙で勝たないといけないよね。
でも、ただやりたいですと言うだけでは票は集まらない。
ここでは、勝つための公約の作り方や演説のポイント、告知の工夫までまとめるよ。
勝てる公約—小さくてもみんなが喜ぶやつ
公約は、大きなことを言えばいいってもんじゃない。
実現できそうで多くの生徒にメリットがあることがポイントだよ。
例えば体育館の空き時間を使えるようにする、とか、図書室の開放時間を延ばすみたいな身近な案が効果的だね。
演説テンプレ—自己紹介→課題→提案→お願い
演説は流れが大事だ。
まずは自己紹介で場を和ませて、次に学校生活の課題を提示する。
それから改善案を提案し、最後に投票お願いしますで締めるのが鉄板の流れだよね。
告知のやり方—ポスター+口コミ+SNS
選挙期間中は、とにかく名前と顔を覚えてもらうことが重要。
廊下や教室前のポスターだけでなく、友達経由で口コミを広げるのも効果的だよ。
学校によってはSNSも活用できるから、情報発信の手段は多いほどいいよね。
落選しても大収穫—人脈と経験は残る
選挙に落ちても、それで終わりじゃない。
選挙活動で得た人脈や発信力は、その後の学校生活や別の委員会活動で生きてくる。
むしろ、その経験が次のチャンスにつながることもあるんだよね。

立候補の“きっかけ”を面白く言おう
演説のオープニングで一番刺さるのは、立候補の理由だよね。
ありがちな言い方だけだと生徒の耳からスルーされがちになる。
だから少しユーモアを混ぜて強調し、短い例文でも記憶に残すのがコツになるよ。
先生やクラスの聴衆が「おっ」となる言葉選びで、最後まで聞いてもらえる流れをつくろう。
①憧れの先輩を超えたいから、というのもアリだよね?
「去年の会長がカッコよかったから、超えたい」と言い切る挑戦心。
活動の経験や失敗談も添えて、「同じ企画を進化させます」とビジョンを提示。
役割の継承と改良を約束する言葉は、候補として信頼を集めやすいよね。
②“なんとなく”で生徒会?いや、それでいいじゃん!
「正直、なんとなく始めた」が逆に誠実さになることもある。
ただし「やるなら最後まで責任を持つ」と締めて、仕事への覚悟を表現しよう。
自然体の自己紹介は共感を呼ぶし、演説全体が柔らかくなるんだ。
③先生に「向いてるよ」と言われたから素直に来ました!
自分では気づかなかった長所を先生に見抜かれたエピソードは強い。
「副会長に向いてる」と背中を押され、立候補を決意した流れを丁寧に提示。
推薦の言葉は信頼の裏づけになり、役員としての適性アピールにもなるよ。
④“自分を変えたい”ダジャレよりアツく語っちゃおう
人見知り克服や発表が苦手など、弱みを成長テーマに変換する。
「会長だけに、会を明るく調える」みたいな軽いダジャレで場を温めつつ、本気の決意で締める。
等身大の理由は、中学生の聴衆に刺さるよね。
※くわしくは「生徒会 立候補理由の例文要約20 役職別!」

そもそも公約って何?
生徒会の選挙で耳にする「公約」という言葉。
これは立候補した候補者が「当選したらこれを実現します」という約束のことだ。
言葉だけなら簡単に聞こえるけれど、その中身は学校生活や活動内容に直結する大事な部分なんだよね。
中学校でも高校でも、生徒会長や副会長、役員が掲げる公約は、学年や委員会、先生たちとの調整が必要になる。
選挙のときに掲げる企画や活動は、単なる願望ではなく、実現可能な目標であることが求められる。
だからこそ、準備や必要な時間、参加する生徒や役員の協力など、細かい部分まで考えたうえで言葉にしないと、活動が始まってから困ることになるよね。
ここではまず、公約がどんな意味を持ち、なぜ重要なのかを見ていこう。
公約の基本的な意味と役割
公約とは、候補者が選挙のときに「当選したらやること」を生徒や先生に対して約束することだ。
ただの思いつきや願望じゃなく、実際の活動や設置、開催にまで落とし込む必要があるんだよね。
学校生活における公約は、イベントの開催、施設の改善、活動の新設など、具体的な動きに直結する。
だから、生徒たちにとっては「この人が当選したら、学校がどう変わるのか」を判断する材料になる。
役員や委員会にとっては、年間の活動計画や予算の配分に影響する大事な指針にもなるんだ。
選挙で公約が重要な理由
選挙では、候補者の人柄や学年での人気も大事だけど、公約の内容が票を動かすことも多い。
面白くて実現可能な企画を出せば、同じ学年はもちろん、他学年の生徒からも「参加してみたい!」という反応がもらえるんだよね。
逆に、あいまいで抽象的な言葉だけの約束だと、「結局何をするのか分からない」という回答が多くなる。
だからこそ、立候補する生徒会長や副会長は、自分の活動内容を具体的に示し、必要な準備や先生との相談も事前に済ませておく必要があるんだ。
この差が、当日の演説や放送での説得力にも直結するよ。
生徒会公約と政治家の公約の違い
政治家の公約は国や自治体レベルで法律や予算を動かす大きな約束だよね。
それに比べて、生徒会の公約はスケールは小さいけど、実現までのスピード感があるのが特徴だ。
中学校や高校の公約は、企画から実施までが年間スケジュールで動くことが多く、立候補して当選すればすぐ活動を始められる場合もある。
ただし、学校の場合でも、委員会や先生の許可、予算の確保など、必要な手続きは避けて通れない。
そのため、生徒会公約は「学校生活をより良くするための現実的な約束」という点で、政治家の公約よりも具体的で身近なものになることが多いんだ。
実現できない公約のリスク
公約を掲げた以上、それを実現できなければ信用を失う可能性がある。
たとえば、「体育館に最新の冷房を設置します」と宣言しても、予算や工事の制限で叶わないこともあるよね。
そうなると、生徒からは「約束を守らなかった」という評価がつく。
また、先生や役員からも次の企画や活動での信頼が薄くなるかもしれない。
だからこそ、立候補の段階で、実現できるかどうかをしっかり検討することが必要なんだ。
実現性を無視した言葉は、選挙では響いても、その後の活動で重荷になるということもあるよね。

良い公約の条件とは?
良い公約って、一言でいえば「やってほしいし、できそうだし、面白そう」なものだよね。
立候補した生徒会長や副会長が掲げる約束がこの3つを満たすと、生徒も先生も「それなら応援する!」となる確率が高いんだ。
逆に、この条件が欠けると、どんなに話し方や見た目が良くても票が伸びないこともある。
ここでは、良い公約に必要な4つの条件を具体的に解説していくよ。
予算や時間の範囲内にあり、実現可能であること
どんなに面白い公約でも、予算や時間の壁を越えられなければ実現しない。
例えば「学校にプールをもう1つ作る」とか「毎週金曜日は全校でカラオケ大会」なんていう企画は、聞いてる分には楽しいけど、現実的じゃないよね。
生徒会の活動内容は、学校の年間予定や行事スケジュールの中で動く。
だから、先生や委員会に事前に相談して、必要な予算や許可が取れるかを確認しておくことが大事だ。
「できること」と「やりたいこと」のバランスを見極める力が、候補者には求められるんだよ。
誰にとってもメリットがあること
公約は立候補した自分のためだけじゃなく、学校全体のためにあるべきだよね。
特定の学年や部活だけが得をする公約だと、ほかの生徒からの支持を得にくい。
例えば「放課後にゲーム部屋を作る」なら、ゲームをしない生徒にも利用価値があるような工夫を加える必要があるんだ。
誰でも参加できたり、恩恵を受けられる企画のほうが、賛成票が集まりやすくなるということもあるよね。
わかりやすく印象に残ること
生徒会の選挙では、全校放送や体育館での立候補演説がメインになることが多い。
その短い時間で、公約の内容を印象づける必要があるんだよね。
「○○プロジェクト」や「学校生活を変える3つの挑戦」みたいにキャッチーな名前をつけると覚えてもらいやすい。
また、説明が長すぎると頭に残らないので、一言でまとめられるようにしておくと強い。
短くてわかりやすく、それでいてワクワクする言葉選びがポイントになるよ。
面白さと真面目さのバランスが取れていること
笑えるだけの公約だと「お遊び」と思われ、真面目すぎると「つまらない」と感じられることもある。
だから、両方のバランスを取ることが重要だ。
例えば「手洗い推進キャンペーン」をやる場合、「風邪予防だけじゃなく、手洗いで運気アップ!」みたいにちょっとした遊び心を加えると覚えてもらえる。
面白さは人を引きつけ、真面目さは信頼を生む。
この2つを合わせると、票も支持も取りやすくなるというわけだ。
※くわしくは「生徒会 面白い公約 まじめな公約一覧」
「公約が浮かばない…焦りがちなあなたへ」
まず最初に、「なぜ公約が思いつかないのか」という原因を整理することが大事だよね。
焦ってもいいアイデアは出づらい。
逆に、今の状態をチャンスととらえて工夫できる発想法を知っておくと、公約ネタのストックがぐっと増えるんだ。
そこで、原因の探り方、見方の変え方、具体的発想法をこのセクションで伝えるよ。
公約作りの土台固めになる部分だから、一緒にじっくり進もう。
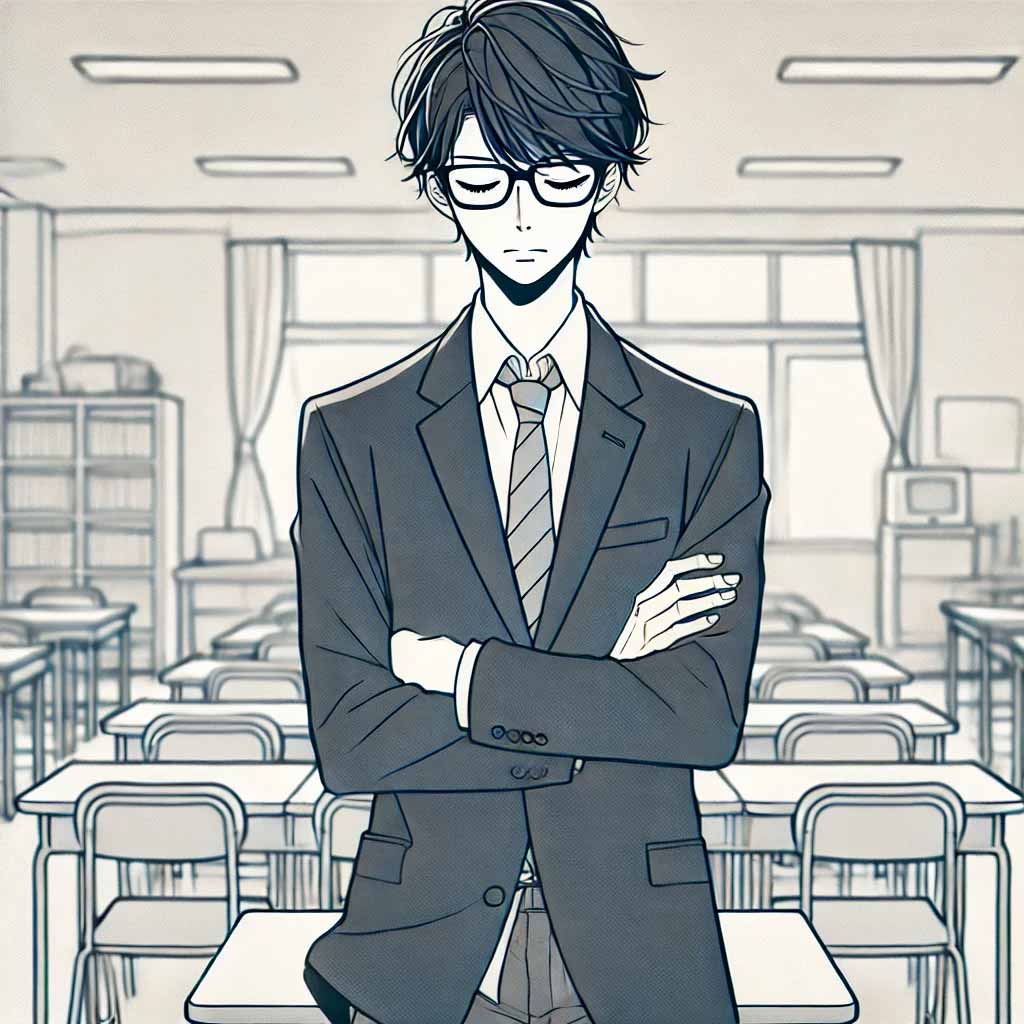
原因を探る:なぜ“思いつかない”のか
公約が浮かばない原因は、人それぞれ違う。
たとえば「学校のことをあまり観察していない」「無理にすごいことを掲げようとしている」「自分の立場を意識しすぎて自由に考えられない」など。
まずは、普段の“悩み”や“困っていること”をメモしてみて。
学校生活で「ここが変わったらいいな」と感じたことを拾っていくと、公約の種が見えてくるよ。
思いつかない状態はむしろチャンス
アイデアが全く出ないということは、逆に“白紙”という自由地帯でもあるんだ。
既存の枠にとらわれない発想を許すタイミング。
「ありきたりなアイデアでは勝てない」と思ってしまうと、手が止まる。
逆に、“少し変なアイデア”も許してあげていい。
その中から、実現できそうなものを選んで磨いていけばいいんだ。
ブレスト(発想法)でアイデアを刈り取る
ブレスト=ブレインストーミングを活用すると、公約アイデアがたくさん出る。
たとえば、クラスメイトとペアで「困っていることリスト」を出し合って、それを公約ネタに変換する。
「もし休み時間が時間無制限だったら?」という仮定で発想することも有効。
形にとらわれずアイデアを出したら、それを後から絞って“実現可能なもの”に調整すればいいんだよ。
インプット型発想 – 他校・ネット・漫画から盗む技術
他の学校の生徒会公約を見たり、ネットの記事を読んだり、漫画の中の学校描写を観察したりするのもアイデア源になる。
「この学校はこんな公約を出してたな」「こういう学校活動いいな」と思ったことを、自分なりに咀嚼して取り込む。
ただし、丸パクリはダメ。
自分の学校に合うようにアレンジすること。
こうしたインプットを重ねて、脳の引き出しを増やしておくと、公約案が自然と出やすくなるよ。
※くわしくは「生徒会に立候補したいけど 公約が思いつかない」
スピーチが苦手じゃ生徒会は無理?
生徒会って、みんなの前でスピーチするだけじゃない。
会議をまとめたり、イベントを企画したり、裏で支えたり。
話すのが苦手でも活躍できる場所、けっこうあるんだよ。
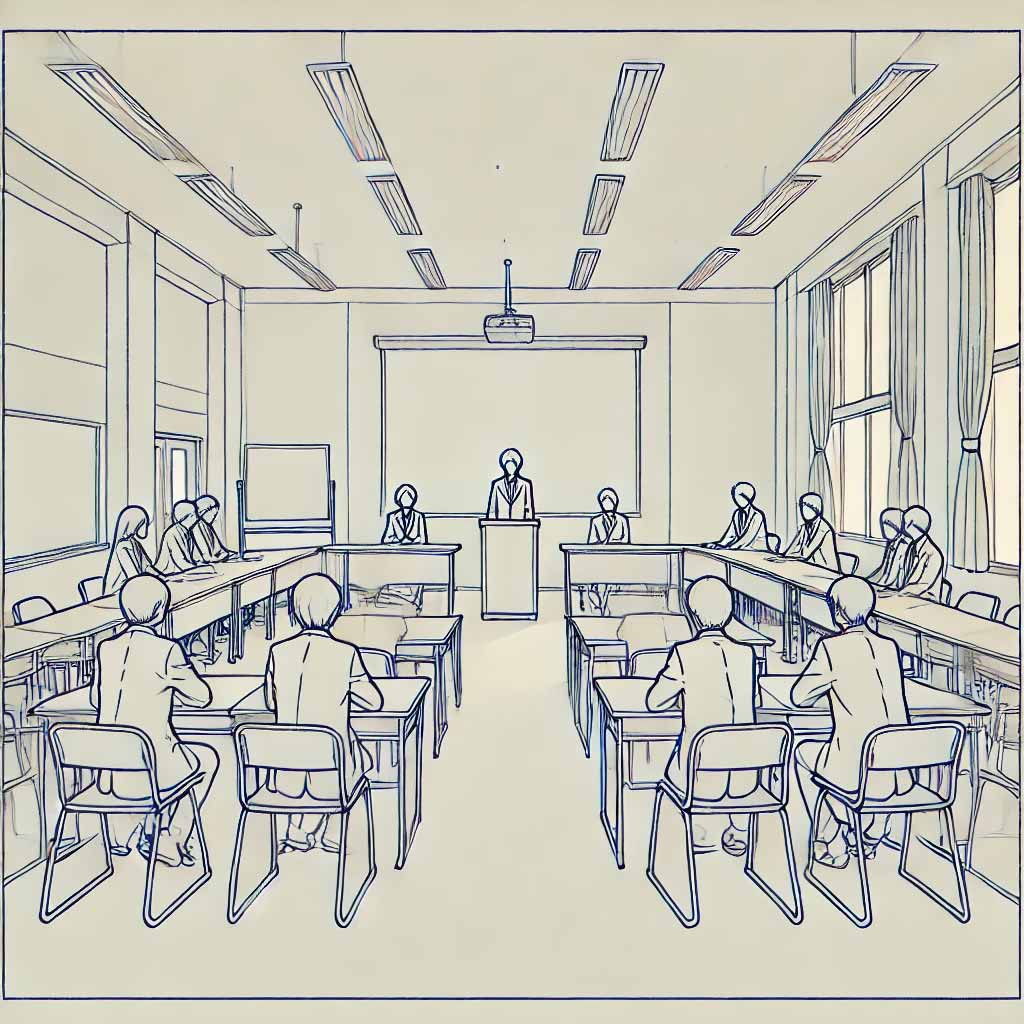
生徒会のしごとにはいろいろなものがある
生徒会は文化祭や体育祭の企画、学校のルールの話し合い、委員会の調整なんかもやる。
発表するより「まとめる」「考える」場面が多いんだ。
地味に見えるけど、そこがチームの要になることもある。
スピーチは“全部”じゃなくて“一部”なんだ
生徒会選挙のスピーチって目立つけど、それが全部じゃない。
準備や裏方が得意な人も、ちゃんと役に立つ。
スピーチが苦手なら、原稿を短くして“中身で勝負”すればいい。
会議では話すよりもまとめるチカラ
会議って、長く話す人よりも“流れを整える人”が大事なんだよね。
「じゃあ次の意見お願いします」とか「まとめるとこうですね」みたいに。
聞くチカラやまとめる力が光る場所でもある。
裏方で光るタイプもいる
人前はちょっと…って人でも、企画書作りとかポスター担当、資料係とかで大活躍できる。
目立たないけど、誰よりも頼られる存在になれることもあるんだよ。
※くわしくは「人前で話すことが苦手じゃ生徒会は無理?」

生徒会選挙演説の全体像—“当てにいく型”で勝ちにいく
演説は自己紹介、立候補理由、公約、締めの順で一本線にするのが王道だ。
骨組みがぶれると全体がふわふわして伝わらないから、最初に型を決めると安心だよね。
自己紹介では同じ生徒としての目線を見せ、立候補理由では経験に裏づけられた気づきを短く語ると信頼が生まれる。
公約は願望で終わらせず、実現までの段取りと数字を添えると候補としての格が上がるよ。
締めはお願いではなく共犯宣言で、みんなで作る学校だよね、と巻き込み型で終えるのがコツだ。
まずは当てにいく型で、当たり前に当ててから差を広げよう。
まずは骨組み:自己紹介→立候補理由→公約→締めの順で一本線
演説は起承転結より結論ファーストの流れが刺さる。
自分は誰か、なぜ立候補するのか、何を実現するのか、最後にどう一緒に進めるのかを一筆書きで示す。
聞き手は道筋が見えると安心して内容に集中できるんだよね。
骨組みは信頼の土台、まずここを固めよう。
「誰トク?」を明確に:ベネフィットを30秒で言い切る
聴衆は私たちに何の得があるのかを知りたい。
昼休みの活動を広げて参加しやすくする、意見箱をデジタル化して全体の声を拾うなど、学校や生徒に効く効果を短く言い切る。
三十秒で分かるベネフィットは最強のフックだよね。
数字と期限で盛る:公約は“何を・いつまでに・どう測る”
文化祭の新企画を三本、来年度の一学期までに試験導入、参加率40パーセントを目標など、数と期日と指標を置く。
測れる公約は実現の道筋が見えるから、候補の信用が上がるんだ。
評価方法を先に示すことも企画の一部だよね。
ラスト一行の魔法:お願いではなく“共犯宣言”で締める
ご清聴ありがとうございましただけで終わると他人ごとで閉じてしまうよね。
ここから一緒に動こう、私たちで楽しい学校を作ろう、と未来の主語を私から私たちに切り替えよう。
共犯宣言は聞き手を役員や活動の仲間に変える合図になるんだ。
※くわしくは「生徒会選挙演説はどうやるの?」
「投票してもらえる生徒会ポスター」って何?
生徒会のポスターって描き始める前から少し気が重くなるよね。
学校の廊下に貼られて知らない人にも見られてクラスの人にも見られる。
それだけで緊張するのは普通だと思う。
でも投票してもらえるポスターって特別な才能が必要なものじゃないんだよ。
見た人が一瞬だけでも「この人なら大丈夫そうかも」と思えるかどうか。
そこがいちばん大事なんだと思う。
うまく説明しなくてもいいし立派な言葉を使わなくてもいい。
安心できる空気が伝わればそれでいいんだよ。
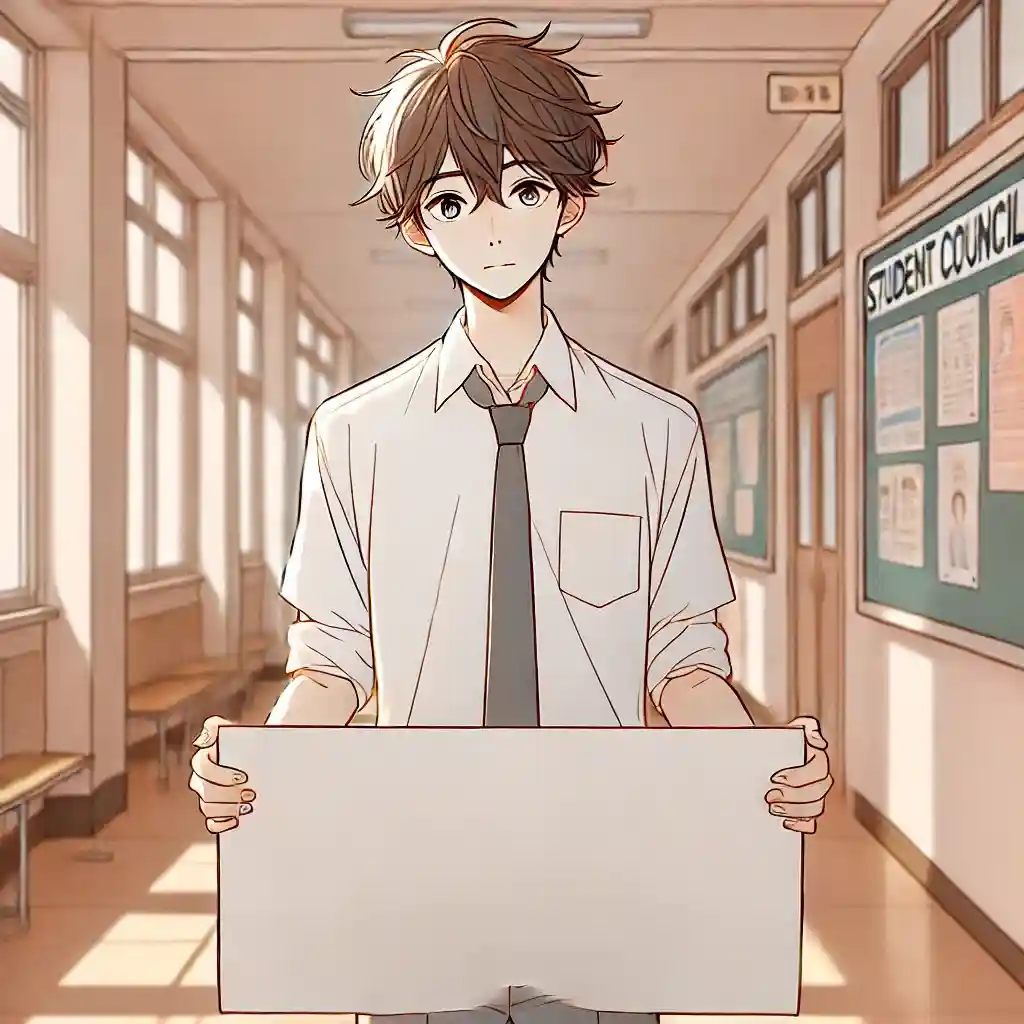
投票されるポスターを分解して考えてみよう
投票されるポスターって聞くと何かすごいことを書かなきゃいけない気がするかもね。
でも実際はもっとシンプルなんだよ。
名前がちゃんと読めること。
役職がすぐ分かること。
どんなことを考えて立候補した人なのかがなんとなく想像できること。
それだけで十分だったりする。
廊下を歩きながらチラッと見たときに頭の片すみに残るかどうか。
投票って意外とそういう感覚で決まることが多いんだよね。
目立つだけじゃ票が入らないワケ
目立つ色を使えば見てもらえる気がするよね。
文字を大きくすれば読んでもらえる気もする。
でも目立ちすぎると逆に「なんかうるさいな」と感じる人もいるんだよな。
学校って静かな場所が多いから派手さより落ち着きの方が安心されやすい。
投票って一瞬のインパクトより何度も見て「まあこの人でいいかも」と思えるかどうかが大きい。
だから目立つだけのポスターは記憶に残らないことも多いんだと思う。
生徒はどんな流れで投票を決めてる?
正直に言うと投票を家で真剣に考える人はあまり多くないかもね。
授業の合間や休み時間に友だちと話しながら決めることが多い。
そのときに「ああこの名前見たことあるな」って思い出せるかどうか。
ポスターはそのきっかけを作る役目なんだと思う。
一回で覚えてもらえなくてもいい。
何回か見て少しずつ慣れてもらえたらそれで十分だよ。
ポスターにできること・できないこと
ポスター一枚ですべての人を納得させるのは正直むずかしい。
それは当たり前のことだと思う。
でも「怪しくなさそう」「ちゃんとしてそう」「変なことはしなさそう」って思ってもらうことはできる。
それだけで投票用紙に名前を書いてもらえる可能性は少し上がる。
完ぺきじゃなくていい。
安心材料になればそれでいいんだよ。

実は気になる③ 生徒会で得られるスキル—将来にも役立つ!
生徒会で活動していると、これ大人になっても使えるんじゃないと感じるスキルがけっこう身につくんだよね。
ここでは、社会に出ても役立つ四つのスキルを紹介するよ。
企画力—行事やイベントをゼロから組み立てるチカラ
文化祭や体育祭などの学校行事は、企画段階から関わることが多い。
テーマを決めて、内容を考えて、必要な人や予算を割り振る。
この経験があると、将来の仕事でもプロジェクトを動かす力になるんだよね。
まとめ役スキル—意見がバラバラでもまとめる技
会議では、意見が衝突することも珍しくない。
そんなときに、じゃあこうしようと落とし所を見つける力は、生徒会役員ならではの武器になる。
クラスや委員会をまとめる経験は、リーダーシップそのものだよね。
お金の管理力—予算を組んでちゃんと使う力
会計や監査を経験すると、限られたお金をどう配分するかが自然と身につく。
これは社会人になってからも、家計管理や仕事の経費管理に直結するスキルだ。
数字に強くなると、信用も得やすくなるんだよね。
面接でのアピール—「やったこと」より「どうやったか」
推薦入試や就職面接で生徒会経験を話すときは、単にやりましたじゃもったいない。
どうやってやったか、どんな問題を解決したかを具体的に話すと、評価がグッと上がる。
やり方や工夫を説明できる人は、面接官にも好印象を与えるんだよね。

まとめ
生徒会は、学校生活の中で「みんなの声を集めて実現する」ための中心的な組織だよね。
会長や副会長、書記・広報、会計・監査といった役員が、それぞれの役割をしっかり果たしているから、行事や活動が成り立っている。
総会や評議会での話し合い、委員会や顧問の先生との協力、地域とのつながりまで、生徒会の活動範囲は想像以上に広い。
忙しいけれど、そのぶん得られる経験やスキルは、将来にもつながる大きな財産になるんだよね。
もし「ちょっとやってみようかな」と思ったら、選挙に挑戦してみるのもアリだ。
失敗しても、それが次の挑戦のきっかけになることもあるし、なにより学校生活がもっと面白くなるはずだよ。

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません