生徒会 面白い公約 まじめな公約一覧 一気に100!
🔷 結論:
生徒会の公約は「ウケそうかどうか」だけで選ぶのではなく、ジャンルと実現度をセットで考えて設計することが大事だよ。
🔷 結論:
この記事を使えば、公約アイデア選びから当選後の動かし方・引き継ぎまで、「ちゃんと当選して、ちゃんと実行できる公約プラン」まで一気に組み立てられるよ。
🌟 重要ポイント(まずここを押さえる!)
- ● 理由:
「面白い/まじめ/未来系/地域・SDGs」などのジャンル別に、公約アイデアを実現度つきで100個チェックできるから、自分たちの学校に合った公約を選びやすくなるよ。 - ● 具体例:
実際に「実現できた公約」「実現できなかった公約」の理由や、やりがちな失敗パターンを先に知ることで、「公約はウケたけど、あとから全然できない」というパターンを回避できるよ。 - ● 今日からできる対策:
記事を読みながら、公約候補をジャンルごとにピックアップしてみよう。実現度や必要な準備も一緒にメモしておくと、そのまま演説台本と年間ざっくり計画のたたき台として使えるよ。
📘 この先を読むメリット
この記事を読みながら公約候補をピックアップすれば、そのまま生徒会選挙の演説台本と、当選後の年間ざっくり計画のたたき台まで一気に仕上がるよ。「とりあえずウケそう」止まりのネタから卒業して、「ちゃんと当選して、ちゃんと実行する公約」にステップアップできるはず。
- 1. 生徒会の公約100例|面白い&まじめ&未来型を一気見
- 2. そもそも公約って何?
- 3. 良い公約の条件とは?
- 4. 実現できた公約のリアル事例集
- 5. 実現できなかった公約とその理由
- 6. ウケ狙いと実現性の黄金バランス公約
- 7. 誰もが安心して賛成できる定番公約
- 8. 学校生活をもっと楽しくするイベント公約
- 9. 最新トレンドを盛り込んだ未来型公約
- 10. 公約実行後も評価されるフォローアップ策
- 11. 面白いだけじゃない!当選を引き寄せる話し方テク
- 12. 公約を作るときに先生・生徒会へ聞いておくべきこと
- 13. 見せ方で差がつく!「推され公約」の作り方
- 14. 当選後に信頼を守るための実行マネジメント
- 15. やりっぱなし禁止!当選後の“つなげ方”講座
- 16. まとめ
生徒会の公約100例|面白い&まじめ&未来型を一気見
まずは、演説づくりにすぐ使える公約アイデアを100個まとめたよ。
「分類」「公約」「実現度(◎=任期内で現実的/◯=条件があれば可/△=工数や許可が重い)」「ポイント」の順で一望できる。
下に行くほど準備が増える傾向だから、時間や人手と相談しながら選んでね。
| 分類 | 公約 | 実現度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 面白い | 昼休みラジオ「校内放送ジャックDAY」 | ◎ | 放送委と連携で即実施。曲リクエスト箱を設置。 |
| 面白い | クラス対抗早口言葉大会(月1) | ◎ | 昼休み5分で完結。実況は生徒会が担当。 |
| 面白い | 先生モノマネOKの「声真似MCデー」 | ◯ | 侮辱NGのガイドライン明記で健全に。 |
| 面白い | 写真スポット(学年カラー背景+小道具) | ◎ | 廊下1コーナーに期間限定で設置。 |
| 面白い | 黒板アート週間(放課後15分開放) | ◎ | チョーク提供と清掃当番の分担を明確化。 |
| 面白い | 「先生クイズ王」昼放送コーナー | ◎ | 先生の趣味・特技を当てる。事前承諾必須。 |
| 面白い | 校内BGMリクエスト週間 | ◯ | 選曲基準(歌詞等)を明文化し審査。 |
| 面白い | 廊下片側「逆走禁止」おもしろ標識POP | ◎ | 安全啓発をユーモラスに。掲示委と共同。 |
| 面白い | 「忘れ物ゼロ」ゆるポスター公募 | ◎ | 最優秀作は全教室掲示。景品は図書券。 |
| 面白い | なぞなぞ下駄箱(週替わり問題) | ◎ | 正解発表は金曜日の放送で。 |
| 面白い | リアクション王決定戦(拍手測定) | ◯ | 体育館マイクで拍手音量を測る。安全配慮。 |
| 面白い | 「先生の若い頃」写真当てクイズ | ◯ | 提供任意。個人情報と肖像権の同意取得。 |
| 面白い | 教室の「一言ボード」(ポジティブ限定) | ◎ | 悪口NGルールを明記し、当番で管理。 |
| 面白い | 5分だけ「方言DAY」 | ◎ | 差別表現禁止の注意書き。笑顔で交流。 |
| 面白い | 「給食キャッチコピー」公募 | ◎ | 栄養士さんにOKをもらい掲示。 |
| 面白い | 「名札アレンジOKの日」(規定内) | ◯ | 安全と識別性が保てる範囲で。 |
| 面白い | 廊下ミニギャラリー(写真・俳句) | ◎ | テーマは季節。掲示枠を明確に。 |
| 面白い | 「本の帯」手書きコンテスト | ◎ | 図書委と合同。貸出数アップ狙い。 |
| 面白い | 3分スピーチ「好きの話だけ」 | ◎ | 発表は任意。教室単位で回す。 |
| 面白い | 早朝あいさつカウンター(数で競う) | ◎ | 学年対抗。過度な大声はNG。 |
| 面白い | 一発芸じゃない「1ボケ1ツッコミ講座」 | ◯ | お笑い“いじり”禁止。言葉の配慮を学ぶ。 |
| 面白い | 「先生にありがとう」メッセージ週間 | ◎ | 短冊に一言。掲示後、本人に返却。 |
| 面白い | 教室掃除選手権(タイム+美しさ) | ◎ | 安全第一。水回りは点数高め。 |
| 面白い | 給食トレイ“静音チャレンジ” | ◎ | マナー啓発をゲーム化。 |
| 面白い | 「落とし物ビンゴ」掲示 | ◎ | 返却促進。個人名の扱いに注意。 |
| まじめ | 目安箱+月イチ回答の見える化 | ◎ | 掲示とサイトで公開(個人特定情報除外)。 |
| まじめ | トイレ備品の定期点検(要望集計) | ◎ | 事務・業者連携。消耗品の在庫表を作成。 |
| まじめ | ロッカー鍵の不具合リスト化と改善要望 | ◯ | 故障箇所の写真付きで提出。 |
| まじめ | 放課後自習室の曜日固定オープン | ◎ | 監督教員配置。静粛ルールを明記。 |
| まじめ | 定期テスト前の図書室延長開放 | ◯ | 試験2週間前のみ。安全管理表を作成。 |
| まじめ | 学年混合清掃チームで交流促進 | ◎ | 固定化しすぎずローテーション。 |
| まじめ | 靴箱ゾーニングとラベル更新 | ◎ | 混雑緩和。色分けで視認性UP。 |
| まじめ | 忘れ物返却フローの標準化 | ◎ | 学年掲示+週1返却会。 |
| まじめ | 給食当番の衛生チェックリスト運用 | ◎ | 手洗い・マスク・消毒の可視化。 |
| まじめ | 昇降口の混雑緩和レーン導入 | ◎ | 矢印シールと誘導係で安全確保。 |
| まじめ | 掲示物の期限ルール化(剥がす日) | ◎ | 古い掲示を撤去、情報鮮度を維持。 |
| まじめ | 教室の二酸化炭素(換気)啓発POP | ◎ | 5限開始時に窓開けの声かけ。 |
| まじめ | 忘れ物ゼロ週間(学年対抗) | ◎ | チェック表を配布、表彰で動機づけ。 |
| まじめ | 部活動の活動日・場所一覧の月次更新 | ◎ | 被り解消。先生と共有カレンダー。 |
| まじめ | 「相談ルート」掲示(悩み別の窓口) | ◎ | 養護・担任・スクールカウンセラー。 |
| まじめ | いじめ・悪口NGの言葉ガイドライン掲示 | ◎ | “言い方”の工夫もセットで提示。 |
| まじめ | 安全見回り当番(下校時10分) | ◯ | 教員帯同のもとで実施。 |
| まじめ | 落ち着く教室レイアウト提案(通路幅) | ◯ | 防災動線を優先、写真で提案。 |
| まじめ | テスト前SNS&ゲーム時間セルフ宣言 | ◎ | 強制しない。自己管理の可視化。 |
| まじめ | 朝読書の静粛リマインド(BGMなし) | ◎ | 開始・終了の合図を統一。 |
| まじめ | 学級委の議事録テンプレ配布 | ◎ | クラウド共有で引き継ぎ楽に。 |
| まじめ | 授業間の廊下右側通行徹底 | ◎ | 安全教材を掲示。実習で周知。 |
| まじめ | 検温・体調申告の簡素化提案 | ◯ | 保健と相談、紙→デジタル化も検討。 |
| まじめ | 清掃用具の置き場統一&名札化 | ◎ | 紛失減・準備時短。 |
| まじめ | 図書委と連携「おすすめ本POP」拡充 | ◎ | 借りられた冊数を月次で発表。 |
| 未来系 | 電子掲示板(モニター1台)で行事案内 | ◯ | 小規模導入から。スライドは生徒会で作成。 |
| 未来系 | オンライン目安箱(フォーム) | ◎ | 匿名可。個人特定情報は自動で除外。 |
| 未来系 | 部活・行事の共有カレンダー運用 | ◎ | 閲覧専用リンクを掲示。 |
| 未来系 | 昼休みミニ配信(校内限定動画) | ◯ | 肖像権同意の範囲で短尺。 |
| 未来系 | 「紙→デジタル」提出物の試行(1件) | ◯ | 同意が必要。保護者案内もセット。 |
| 未来系 | タブレット学習の持ち帰りルール啓発 | ◎ | 充電・破損対策・紛失時の流れ明記。 |
| 未来系 | 図書の新刊希望フォーム | ◎ | 採否は図書予算と相談。 |
| 未来系 | リモート委員会(欠席者向け補助) | ◯ | 校内ネットワーク規程に準拠。 |
| 未来系 | 「勉強タイマー」共有(集中25分運動) | ◎ | 全校一斉は難しいので希望制。 |
| 未来系 | 学級ページで「今週の連絡」統一 | ◎ | 紙と併用で移行期を滑らかに。 |
| 未来系 | 行事の写真共有ルール(公開範囲) | ◎ | NG希望の尊重を最優先。 |
| 未来系 | 校内Wi-Fiマナー啓発(動画1分) | ◎ | 短尺で繰り返し流すと浸透。 |
| 未来系 | 「静かな自習BGM」著作権クリアの配信 | ◯ | 楽曲の権利確認。音量管理徹底。 |
| 未来系 | ICT係の設置(配線・投影サポート) | ◯ | 教員と役割分担を明確に。 |
| 未来系 | アンケート自動集計のテンプレ配布 | ◎ | Googleフォーム等で効率化。 |
| 未来系 | 緊急時連絡の多重化(掲示+放送) | ◎ | 情報の重複提示で見落とし防止。 |
| 未来系 | 電子黒板の活用事例共有会 | ◯ | 先生と合同で10分ショーケース。 |
| 未来系 | 「失くし物QR」返却受付(実験導入) | △ | 個人情報配慮が重い。小規模試行から。 |
| 未来系 | 通知の多言語サポート(日本語+英語) | ◯ | 重要連絡のみ翻訳対応。 |
| 未来系 | 授業外学習のリマインドBot(掲示代替) | △ | 環境整備が必要。まずは掲示強化で代替。 |
| 未来系 | 行事のライブ投票(安全な範囲で) | ◯ | 紙投票の補助として小規模から。 |
| 未来系 | 先生紹介ショート動画(30秒) | ◯ | 同意必須。撮影・編集は生徒会。 |
| 未来系 | 端末の持ち込み充電マナー周知 | ◎ | 安全第一。充電場所の明確化。 |
| 未来系 | クラブ成果のデジタル年鑑(1学年1本) | ◯ | 写真・動画の権利確認を徹底。 |
| 未来系 | 「公約達成率発表会」をスライド化 | ◎ | 数値と写真で透明性を確保。 |
| 地域・SDGs | ペットボトルキャップ回収 | ◎ | 回収先と搬出日を明確に。 |
| 地域・SDGs | 古紙・ノートのリサイクルBOX | ◎ | 機密文書は不可の注意書き。 |
| 地域・SDGs | 地域清掃(学期に1回) | ◯ | 安全管理と保険の確認が必須。 |
| 地域・SDGs | 商店街PRポスターを生徒が制作 | ◯ | 掲示場所と期間を事前調整。 |
| 地域・SDGs | フードドライブ(家庭の余剰食品) | △ | 受け入れ団体・衛生ルールの確認が必要。 |
| 地域・SDGs | 省エネ週間(教室の電灯ゾーン運用) | ◎ | 自然光活用。安全・視力に配慮。 |
| 地域・SDGs | マイボトル推進(給水ポイント案内) | ◎ | 衛生管理の基準を掲示。 |
| 地域・SDGs | 衣類リユース会(制服小物など) | ◯ | 保護者会と共同で安全に。 |
| 地域・SDGs | 見守り挨拶運動(登下校) | ◯ | 地域ボランティアと連携。 |
| 地域・SDGs | プランター菜園(理科×家庭科) | ◎ | 収穫は掲示で共有。土壌管理に注意。 |
| 地域・SDGs | ごみ分別の色分けシール刷新 | ◎ | イラストで直感的に。 |
| 地域・SDGs | 使い捨てカイロ回収(資源化) | ◯ | 回収先の有無を事前確認。 |
| 地域・SDGs | 地域の図書館・施設ツアー | ◯ | 学年代表のみでも効果あり。 |
| 地域・SDGs | 自転車マナー強化週間 | ◎ | ヘルメット・二人乗りNGを徹底。 |
| 地域・SDGs | エコ標語コンクール(入賞掲示) | ◎ | 短く力のある言葉を募集。 |
| 地域・SDGs | 落ち葉アートDAY(秋の中庭) | ◎ | 終了後の清掃までセット。 |
| 地域・SDGs | 節水ポスターの全校掲示 | ◎ | 水道周りの注意書きを更新。 |
| 地域・SDGs | 地域の高齢者施設へ季節カード送付 | ◯ | 個人情報管理と宛先承諾。 |
| 地域・SDGs | 避難経路の再掲示&点検 | ◎ | 防災訓練前に更新。 |
| 地域・SDGs | 雨天時の滑り止めマット整備要望 | ◯ | 安全委と写真付き申請。 |
| 地域・SDGs | 使用済み電池の回収ボックス | ◯ | 自治体ルールに沿って処理。 |
| 地域・SDGs | 「ありがとうカード」地域版(商店街へ) | ◯ | 代表生徒が届けて交流。 |
| 地域・SDGs | 通学路の危険箇所マップ作成 | ◯ | PTA・自治体に提出して改善要望。 |
| 地域・SDGs | 文化祭で地域PRコーナー | ◯ | 地域の許可・協力先を確保。 |
| 地域・SDGs | 使用しない教室の消灯チェック | ◎ | 当番制でムダ電力を削減。 |
そもそも公約って何?
生徒会の選挙で耳にする「公約」という言葉。
これは立候補した候補者が「当選したらこれを実現します」という約束のことだ。
言葉だけなら簡単に聞こえるけれど、その中身は学校生活や活動内容に直結する大事な部分なんだよね。
中学校でも高校でも、生徒会長や副会長、役員が掲げる公約は、学年や委員会、先生たちとの調整が必要になる。
選挙のときに掲げる企画や活動は、単なる願望ではなく、実現可能な目標であることが求められる。
だからこそ、準備や必要な時間、参加する生徒や役員の協力など、細かい部分まで考えたうえで言葉にしないと、活動が始まってから困ることになるよね。
ここではまず、公約がどんな意味を持ち、なぜ重要なのかを見ていこう。

公約の基本的な意味と役割
公約とは、候補者が選挙のときに「当選したらやること」を生徒や先生に対して約束することだ。
ただの思いつきや願望じゃなく、実際の活動や設置、開催にまで落とし込む必要があるんだよね。
学校生活における公約は、イベントの開催、施設の改善、活動の新設など、具体的な動きに直結する。
だから、生徒たちにとっては「この人が当選したら、学校がどう変わるのか」を判断する材料になる。
役員や委員会にとっては、年間の活動計画や予算の配分に影響する大事な指針にもなるんだ。
選挙で公約が重要な理由
選挙では、候補者の人柄や学年での人気も大事だけど、公約の内容が票を動かすことも多い。
面白くて実現可能な企画を出せば、同じ学年はもちろん、他学年の生徒からも「参加してみたい!」という反応がもらえるんだよね。
逆に、あいまいで抽象的な言葉だけの約束だと、「結局何をするのか分からない」という回答が多くなる。
だからこそ、立候補する生徒会長や副会長は、自分の活動内容を具体的に示し、必要な準備や先生との相談も事前に済ませておく必要があるんだ。
この差が、当日の演説や放送での説得力にも直結するよ。
生徒会公約と政治家の公約の違い
政治家の公約は国や自治体レベルで法律や予算を動かす大きな約束だよね。
それに比べて、生徒会の公約はスケールは小さいけど、実現までのスピード感があるのが特徴だ。
中学校や高校の公約は、企画から実施までが年間スケジュールで動くことが多く、立候補して当選すればすぐ活動を始められる場合もある。
ただし、学校の場合でも、委員会や先生の許可、予算の確保など、必要な手続きは避けて通れない。
そのため、生徒会公約は「学校生活をより良くするための現実的な約束」という点で、政治家の公約よりも具体的で身近なものになることが多いんだ。
実現できない公約のリスク
公約を掲げた以上、それを実現できなければ信用を失う可能性がある。
たとえば、「体育館に最新の冷房を設置します」と宣言しても、予算や工事の制限で叶わないこともあるよね。
そうなると、生徒からは「約束を守らなかった」という評価がつく。
また、先生や役員からも次の企画や活動での信頼が薄くなるかもしれない。
だからこそ、立候補の段階で、実現できるかどうかをしっかり検討することが必要なんだ。
実現性を無視した言葉は、選挙では響いても、その後の活動で重荷になるということもあるよね。

良い公約の条件とは?
良い公約って、一言でいえば「やってほしいし、できそうだし、面白そう」なものだよね。
立候補した生徒会長や副会長が掲げる約束がこの3つを満たすと、生徒も先生も「それなら応援する!」となる確率が高いんだ。
逆に、この条件が欠けると、どんなに話し方や見た目が良くても票が伸びないこともある。
ここでは、良い公約に必要な4つの条件を具体的に解説していくよ。
予算や時間の範囲内にあり、実現可能であること
どんなに面白い公約でも、予算や時間の壁を越えられなければ実現しない。
例えば「学校にプールをもう1つ作る」とか「毎週金曜日は全校でカラオケ大会」なんていう企画は、聞いてる分には楽しいけど、現実的じゃないよね。
生徒会の活動内容は、学校の年間予定や行事スケジュールの中で動く。
だから、先生や委員会に事前に相談して、必要な予算や許可が取れるかを確認しておくことが大事だ。
「できること」と「やりたいこと」のバランスを見極める力が、候補者には求められるんだよ。
誰にとってもメリットがあること
公約は立候補した自分のためだけじゃなく、学校全体のためにあるべきだよね。
特定の学年や部活だけが得をする公約だと、ほかの生徒からの支持を得にくい。
例えば「放課後にゲーム部屋を作る」なら、ゲームをしない生徒にも利用価値があるような工夫を加える必要があるんだ。
誰でも参加できたり、恩恵を受けられる企画のほうが、賛成票が集まりやすくなるということもあるよね。
わかりやすく印象に残ること
生徒会の選挙では、全校放送や体育館での立候補演説がメインになることが多い。
その短い時間で、公約の内容を印象づける必要があるんだよね。
「○○プロジェクト」や「学校生活を変える3つの挑戦」みたいにキャッチーな名前をつけると覚えてもらいやすい。
また、説明が長すぎると頭に残らないので、一言でまとめられるようにしておくと強い。
短くてわかりやすく、それでいてワクワクする言葉選びがポイントになるよ。
面白さと真面目さのバランスが取れていること
笑えるだけの公約だと「お遊び」と思われ、真面目すぎると「つまらない」と感じられることもある。
だから、両方のバランスを取ることが重要だ。
例えば「手洗い推進キャンペーン」をやる場合、「風邪予防だけじゃなく、手洗いで運気アップ!」みたいにちょっとした遊び心を加えると覚えてもらえる。
面白さは人を引きつけ、真面目さは信頼を生む。
この2つを合わせると、票も支持も取りやすくなるというわけだ。
実現できた公約のリアル事例集
「本当に実現したの?」と疑う前に、まずは実例を知っておこう。
実現できた公約には、必ず「現実的な計画」と「周囲の協力」があるんだ。
中学校や高校の生徒会では、思った以上にいろんな公約が成功している。
ここでは、実際に中学校や高校で実現された公約を4つ紹介するよ。

電子マネー導入で食堂の行列短縮
ある高校では、生徒会の公約で食堂に電子マネー決済を導入した。
これにより、昼休みの行列が短くなり、時間を有効に使えるようになったんだ。
「SuicaやPayPayが使える学校食堂」なんて、聞くだけでちょっと未来感があるよね。
実際、参加した生徒や先生からは「並ぶ時間が減った」と好評だった。
これは、必要な機材設置や業者との連絡、先生の許可といった準備をしっかり整えたからこそ実現できた例だ。
クラス対抗スポーツ大会の定例化
毎年1回だけだったスポーツ大会を、学期ごとに開催することを公約に掲げた例だ。
開催回数を増やすためには、体育館や校庭の使用スケジュールを調整する必要があったけど、生徒会と体育委員会が協力してクリアした。
この結果、学年や部活動の枠を超えて参加できる機会が増え、学校全体の交流が活発になったんだよね。
放課後自習室のオープン
勉強したい生徒のために、放課後に自習室を開放する公約。
静かな環境で集中できる場所が欲しいという声は多く、特に受験を控えた生徒にとってはありがたい企画だった。
この公約は、教室の空き状況や先生の見回り体制を整える必要があったけど、委員会や学年主任の協力で実現したんだ。
文化祭に新しいステージイベント追加
文化祭のステージイベントに新しいジャンルを追加する公約もある。
例えば「先生カラオケ大会」や「即興コント対決」など、生徒も先生も参加できるものだ。
こういう企画は観客の参加型にすると、より盛り上がるんだよね。
実現には先生方の理解と事前準備が必要だったけど、その分文化祭の満足度は大きく上がった。
実現できなかった公約とその理由
公約は必ずしも全部が叶うわけじゃない。
中には、立候補のときは盛り上がったのに、実際の活動に入ったら実現できなかった例もあるんだよね。
その多くは、予算や時間、学校の規則など、現実的な壁にぶつかってしまうケースだ。
ここでは、実際に学校であった「実現できなかった公約」と、その背景を紹介するよ。

制服完全自由化が頓挫したケース
「制服を完全に自由化します!」という公約は、一見すると生徒から大きな支持を得そうだよね。
でも、これには学校の規則や保護者、先生たちの意見が絡む。
安全面や学校のイメージを守る必要があるため、完全自由化は認められなかったんだ。
結局、一部の規定を緩和する形に落ち着いた。
制服の自由化は理想的だけど、実現にはかなりの時間と話し合いが必要になるという例だ。
校内カフェ設置が叶わなかった背景
「校内にカフェを作る」という公約も人気が高い。
特に高校生からは「放課後に友達と過ごせる場所が欲しい」という声が多いんだよね。
しかし、飲食を提供するためには衛生管理、設備投資、人員の確保など多くの課題がある。
さらに、授業時間や部活動の時間との兼ね合いも難しく、実現には至らなかった。
この例は、アイデアは良くても準備や運営体制が整わなかったパターンだ。
部活動予算倍増が却下されたワケ
「部活動の予算を倍にする」という公約は、部員からは絶大な支持を集める。
しかし、学校全体の予算には限りがあり、ある部の予算を増やせば、他の部の予算を減らす必要がある。
公平性を保つため、結局この公約は通らなかったんだ。
部活動の支援をしたいなら、予算の増額以外の方法を考える必要があるという教訓になるね。
体育館冷房設置が先送りになった事情
真夏の体育館は暑すぎる。
そこで「体育館に冷房を設置します」という公約を掲げた候補者もいた。
しかし、冷房設備の設置には高額な費用と工事期間が必要だ。
さらに、耐震や電気設備の問題も絡み、予算の優先順位としては後回しになった。
最終的に、冷房設置は数年後の計画に組み込まれることになったけど、任期中には実現できなかったんだ。
ウケ狙いと実現性の黄金バランス公約
笑いを取るだけでなく、ちゃんと実現できる公約は強い。
こういう公約は、生徒からも先生からも「面白いし、やってみよう」と思ってもらえるんだよね。
ここでは、実際に学校生活を盛り上げつつ、実行可能なアイデアを紹介するよ。

「手洗い推進」や「ストッキング綱引き」で笑いを取る
手洗い推進は真面目な健康対策だけど、これを面白く見せる方法がある。
例えば「手を洗うとポイントがもらえるイベント」を企画したり、「先生VS生徒のストッキング綱引き大会」を組み合わせたりするんだ。
これなら予算も少なく、参加する生徒も多くなるだろう。
感染症対策にもなって一石二鳥だよね。
元気なあいさつ運動で学校を明るく
あいさつ運動はどこの学校でもあるけれど、やり方次第で面白くできる。
例えば「一番元気なあいさつをした人を表彰する」とか、「学年ごとのあいさつ対決」を開催するんだ。
こうすることで、ただの形式的な活動が、参加したくなるイベントに変わる。
元気な声が響く学校って、やっぱり雰囲気がいいよね。
デジタル掲示板で便利化
掲示板をデジタル化して、行事予定や活動内容をリアルタイムで表示する。
こうすれば、急な変更や連絡もすぐに全校に伝えられる。
部活動の大会日程や、委員会の募集なども簡単に更新できるのが強みだ。
これは予算と設置場所の確保が必要だけど、十分実現可能な公約だよね。
SDGsやエコ活動で未来感をプラス
最近は、学校でもSDGsの取り組みを進めているところが多い。
例えば「ペットボトルキャップ回収」や「リサイクル文具の交換会」などはすぐに始められる。
こういう活動は、社会貢献にもつながるし、生徒や先生の協力も得やすいんだ。
未来志向の公約は、聞いた人に「いいね」と思わせやすいという強みもある。
誰もが安心して賛成できる定番公約
奇抜なアイデアも面白いけど、やっぱり安定して票を集めるのは「みんなにメリットがある定番公約」だよね。
こういう公約は実現性が高く、先生や委員会からの理解も得やすい。
活動内容も具体的だから、立候補演説で説明するときも説得力があるんだ。

目安箱設置と意見の見える化
「学校生活をもっと良くするには、まず声を集めることから」。
目安箱を設置して、生徒の意見や要望を集める公約は定番だ。
ただ置くだけじゃなく、寄せられた意見を定期的に発表したり、実現可能なものから順に企画に反映させたりすると効果的。
こうすれば「意見が無視されない学校」になるよね。
トイレやロッカーの環境改善
トイレの清掃強化やロッカーの鍵交換など、日常の不満を解消する公約は支持されやすい。
特に中学校や高校では「洋式トイレを増やしてほしい」という声が多い。
こういう改善は、先生や事務室との連絡で進めやすく、必要な予算も比較的少ないことが多い。
実際、これを公約にして当選した生徒会長もいるんだよ。
放課後勉強スペースの提供
部活動に参加しない生徒や、静かに勉強したい生徒のために、放課後に教室や図書室を開放する公約だ。
「自習室があると助かる」という回答はどの学校でも多い。
これも先生の監督が必要だけど、空き教室を活用できれば低コストで実現できる。
特に受験前の学年からの支持が厚い公約になるよ。
クラス対抗スポーツ大会や昼休みイベント
全校が楽しめる行事は、やっぱり盛り上がる。
クラス対抗スポーツ大会や昼休みのミニイベントは、参加率が高く、準備も生徒会と委員会で分担しやすい。
こういう活動は学校生活の思い出にも残るから、毎年恒例にしてもいいかもね。
学校生活をもっと楽しくするイベント公約
イベント系の公約は、「やってみたい!」という気持ちを刺激する。
実行までのハードルもそこまで高くないことが多いから、初心者の候補者にもおすすめだ。
ここでは、学校全体を巻き込めるイベント系のアイデアを紹介するよ。

文化祭や体育祭に新しい出し物を追加
文化祭に「コスプレコンテスト」や「写真スポットコーナー」を加えると、参加する楽しみが増える。
体育祭なら「学年混合リレー」や「障害物リレー」も人気だ。
こういう新しい出し物は準備が必要だけど、その分注目度も高い。
参加する生徒の幅が広がるのがポイントだね。
昼休み放送やYouTube広報で盛り上げる
昼休み放送を活用して、クイズ大会やリクエスト音楽タイムを企画する。
さらに、行事や活動内容をYouTubeで配信すれば、保護者や卒業生にも見てもらえる。
情報発信の幅を広げることで、学校の雰囲気も明るくなるよね。
「誉め愛会」などポジティブ交流イベント
生徒同士でお互いを褒め合うイベントは、学校生活を温かくする。
「今日のいいところ」を発表し合うだけでも雰囲気が変わるんだ。
こういう活動は特別な予算が必要ないので、すぐ始められるのも魅力だ。
地域清掃や地域PR活動で外とのつながり強化
地域との交流を深めるイベントは、学校の評価アップにもつながる。
例えば商店街の清掃や、地元の特産品紹介イベントなどがある。
これなら先生や地域の人も協力してくれる可能性が高いよね。
最新トレンドを盛り込んだ未来型公約
最近の生徒会では、時代に合った公約を掲げる動きも増えている。
テクノロジーや多様性、環境への配慮など、少し先を見据えたアイデアだ。
ここではそんな未来型公約を紹介するよ。

制服の自由化や多様性尊重の取り組み
完全自由化は難しくても、スラックスやスカートを自由に選べる制度は導入できる場合がある。
性別にとらわれない服装を認める取り組みは、最近特に注目されている。
これなら多様な価値観を尊重できるよね。
デジタル化で掲示や情報共有を効率化
掲示物や連絡事項をタブレットや電子掲示板で配信する。
これにより紙の使用を減らし、情報の更新も速くなる。
SDGsの観点からも評価されやすい公約だ。
環境に配慮した学校運営(ゴミ分別や節電)
校内にリサイクルステーションを設置したり、節電週間を作るなど、環境への意識を高める活動。
こういう企画は長期的な効果があるし、地域からも評価されやすい。
健康・安全推進(熱中症対策や防犯強化)
夏場の熱中症対策として、休憩用のミストシャワー設置や日陰スペースの確保を行う。
また、防犯カメラの増設など、安全面の強化も含めると実現性が高い。
公約実行後も評価されるフォローアップ策
公約は当選して実行して終わり…じゃないんだよね。
その後どうフォローするかで、候補者としての評価も大きく変わる。
任期中の活動を最後までやり切るためには、進捗や成果をしっかり見せる工夫が必要になる。

進捗を公開する「公約達成率発表会」
学期ごとに「どこまでできたか」を発表する場を作る。
これは全校放送や掲示板、朝会などでやると効果的だ。
生徒からも「ちゃんとやってくれてるんだ」と信頼を得られるし、活動内容の透明化にもつながる。
数字や写真を使うとより分かりやすくなるよね。
実施後の改善アンケートで次に活かす
イベントや活動を終えたら、アンケートを取って評価を集める。
「何が良かったか」「改善してほしい点は何か」を聞くことで、次の企画の質が上がるんだ。
こういうフィードバックは委員会や次の役員にも共有できるから、学校全体の財産になる。
公約を引き継ぐ後輩へのバトンタッチ
任期内に終わらなかった企画は、後輩にしっかり引き継ぐ。
書類や手順を残しておけば、次の生徒会役員も迷わず活動を続けられる。
これは学校の年間活動を継続的に成長させるためにも重要だよね。
成果を動画や冊子で記録に残す
写真や動画で活動を記録し、卒業後も見返せる形にする。
こうした記録は、新しい候補者の参考資料にもなる。
先生や保護者にも成果を共有できるのがポイントだ。
面白いだけじゃない!当選を引き寄せる話し方テク
公約の内容が良くても、伝え方が下手だと票は伸びない。
逆に、話し方が上手いと普通の公約でも「面白そう!」と思わせられるんだよね。

笑いを自然に入れる間の取り方
演説や放送で、ちょっとした間をあけて笑いを取る。
笑わせようとしすぎると寒くなるので、自然なタイミングを狙うのがコツだ。
たとえば失敗談や身近なエピソードを軽く挟むと効果的だよ。
公約の核心を短くわかりやすく言うコツ
演説は短時間勝負。
「○○をやります!」と一言で伝え、その後に理由や効果を補足する。
最初に長々説明すると、肝心な部分が埋もれちゃうから注意だね。
表情・身振りの見せ方
口だけじゃなく、顔や手の動きで熱意を表す。
視線を動かしすぎると落ち着きがなく見えるので、1〜2秒は相手の目を見ると効果的だ。
舞台に立つなら背筋を伸ばし、声を前に飛ばすイメージで話すといいよ。
質問タイムを逆に利用する返し方
質疑応答で予想外の質問が来たときこそチャンスだ。
「いい質問ですね」と受けてから、自分の公約や活動に結びつける。
これができると、頭の回転が早い人だと思ってもらえる。
公約を作るときに先生・生徒会へ聞いておくべきこと
公約は1人で作るものじゃない。
先生や先輩役員の意見を聞くことで、実現性がグッと上がるんだ。

実現に必要な予算と手続き
「やりたいこと」にいくらかかるのか、どんな手順が必要なのかを確認する。
予算や申請方法を知らずに動くと、時間をムダにすることになる。
事前のリサーチがカギだよね。
行事や授業との兼ね合い
学校の年間予定表を見て、行事やテスト期間にかぶらないように企画を組む。
タイミングを間違えると、参加率がガクッと下がることもある。
協力してくれる先生や部活の有無
活動には必ず協力者が必要だ。
「この先生なら力になってくれる」という相手を早めに見つけること。
部活動との連携も視野に入れると、動員力が増すよ。
規則や安全面の制限事項
学校ごとの規則や安全ルールは必ず確認する。
特に飲食や設備使用に関しては制限がある場合が多いんだ。
ここを見落とすと実現が遠のく。
見せ方で差がつく!「推され公約」の作り方
内容が良くても、伝わらなければ票は動かない。
押す理由を3秒で理解できる“見せ方”から先に作るのが近道だ。
ポスターの一言、放送のワンフレーズ、動画の最初の5秒。
その小さな入口で「参加したい」を引き出せれば勝ち筋が見える。
媒体ごとの強みを使い分け、ストーリーで共感を積み上げよう。

ポスターは“3秒で伝わる”デザインに
公約の内容がよくても、「伝わらなきゃ意味ない」ってやつ。
だから、まずは“見せ方”で勝負しよう。
ポスターなら、ごちゃごちゃ書くよりも「一言の強さ」で決まる。
色は3色以内、文字は太め、キャッチコピーは“3秒で読める長さ”が鉄則だ。
「明日がちょっと楽しみになる学校へ」くらいがちょうどいい。
放送や演説は“声のテンション”が命
演説や放送では、声のテンションが命。
大声で叫ぶより、抑揚と間をうまく使うほうがずっと響く。
「え?」って思わせて、次の一言でグッと掴む。
話す内容より、聞き手の表情を観察できる人が強い。
広報は“媒体ごとにキャラ変”が正解
広報の仕方も全部同じじゃつまらない。
放送ならテンポ重視、掲示なら見やすさ、動画ならリズム感。
それぞれに“性格”があるから、使い分けると印象がまるで変わる。
ストーリーで「この人応援したい!」を作る
そして何より大事なのは、「この人、応援したい」と思わせるストーリー。
自分がなぜそれをやりたいのか。
どんな場面で「これ、変えたいな」と思ったのか。
それをまっすぐ話すだけで、説得力がぐんと上がる。
内容だけじゃなく、“伝え方も含めて公約”なんだ。
当選後に信頼を守るための実行マネジメント
当選してからが本番だ。
ここで失敗すると、公約が形だけになってしまう。
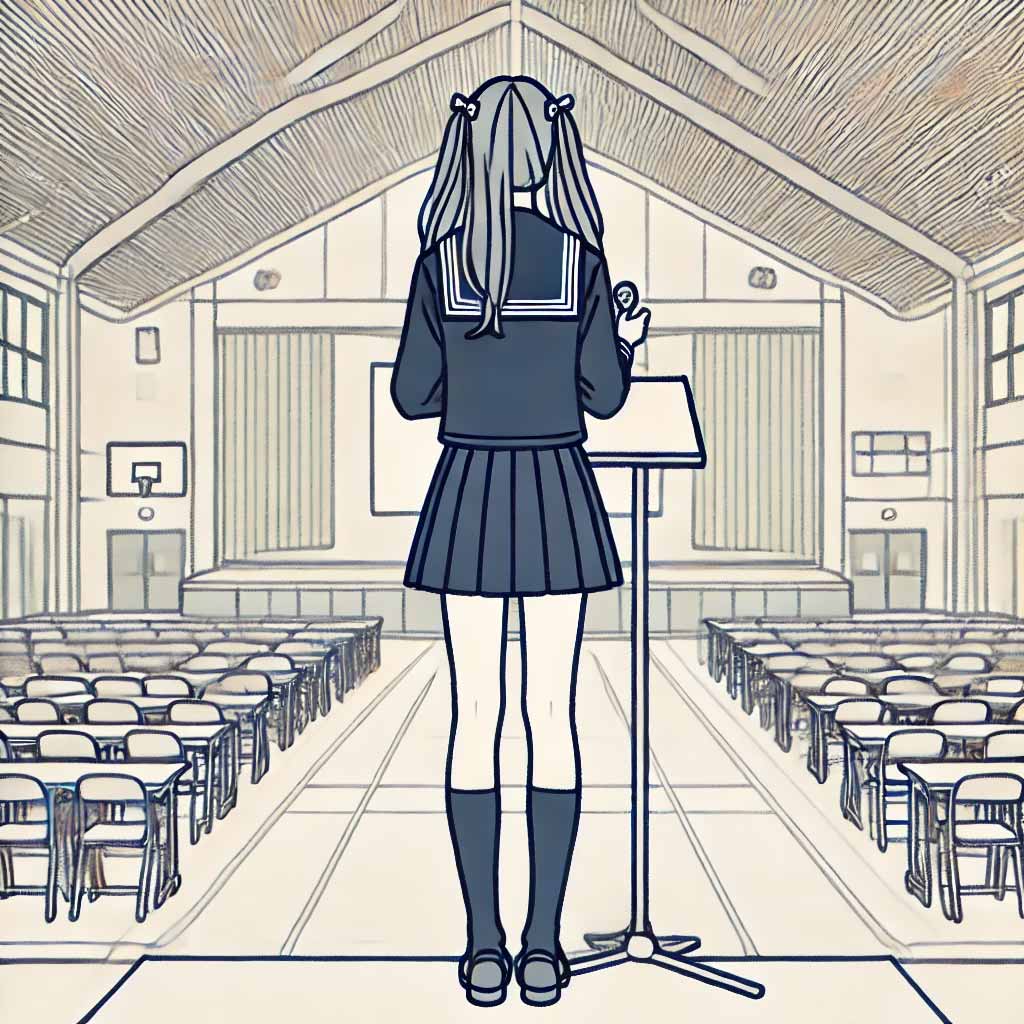
公約の優先順位を明確にする
全部を一度にやろうとせず、重要度や実現性で優先順位をつける。
「まずはこれから」という順番を決めることで、活動がスムーズになる。
仲間を巻き込んだタスク分担
生徒会役員だけでなく、学年や委員会のメンバーも巻き込む。
役割を分担すれば負担が減り、スピードも上がるよね。
定期報告で不安を解消
進捗や課題を定期的に共有することで、「ちゃんと進んでるんだ」と安心してもらえる。
報告は短くてもいいから継続することが大事だ。
成果をお披露目するイベント
達成した公約は発表会や動画で共有する。
これは次の候補者の参考にもなり、学校全体のモチベーションが上がる効果もある。
やりっぱなし禁止!当選後の“つなげ方”講座
当選はスタートで、ゴールじゃない。
任期が終わっても動き続ける仕組みを作れば、学校はどんどん良くなる。
ノートで知見を残し、委員会とコラボして恒例化し、後輩へバトンを渡す。
さらに成果を見える形で共有すれば、信頼が積み上がる。
“やって終わり”を卒業して、“つなげて育てる”に切り替えよう。
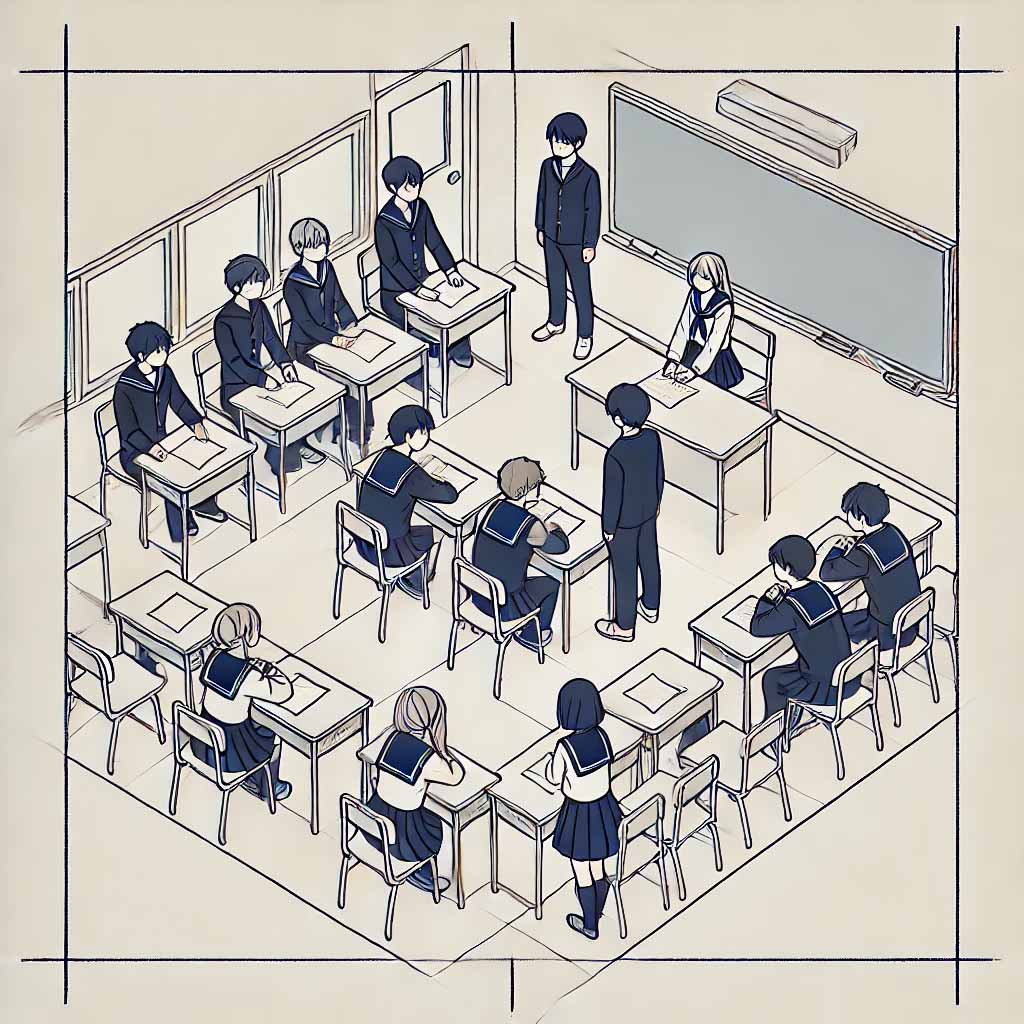
後輩に残す“公約ノート”を作っとこう
当選したらゴール、じゃない。
むしろそこからが本番だ。
任期が終わっても次につながる仕掛けを作れば、学校はもっと面白くなる。
まずは「公約ノート」。
実施日・協力者・使った資料をざっくり残しておくだけで、後輩は助かる。
これがあるかないかで来年の動きが変わる。
“コラボ生徒会”で一人企画をチーム戦に
次に、“コラボ生徒会”を意識しよう。
他の委員会や部活と組めば、企画の幅が一気に広がる。
お互いの得意を持ち寄れば、継続率もテンションも上がる。
次の候補にバトンタッチ作戦
そして、次の候補者へのバトンタッチ。
成功も失敗もぜんぶ共有すれば、“生徒会のDNA”が受け継がれる。
“やって終わり”じゃもったいない!成果見せタイム
最後は成果を見せる。
動画、ポスター、スライドなんでもいい。
「ちゃんとやった」が形になると、信頼が残る。
やりっぱなしで終わるより、“つなげて残す”がほんとのリーダーだ。

まとめ
生徒会の公約は、面白さと実現性のバランスが命だ。
大げさすぎても現実的すぎても響かない。
学校生活を楽しく、便利に、安全にするアイデアを、笑顔と熱意で伝えることが勝利の近道になる。
そして、当選後は必ず実行とフォローを忘れないこと。
そうすれば、あなたの名前は学校中で「必ず実現させる人」として残るはずだよ。
※合わせて読みたい「生徒会の役割 各役員は何をするの?」

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

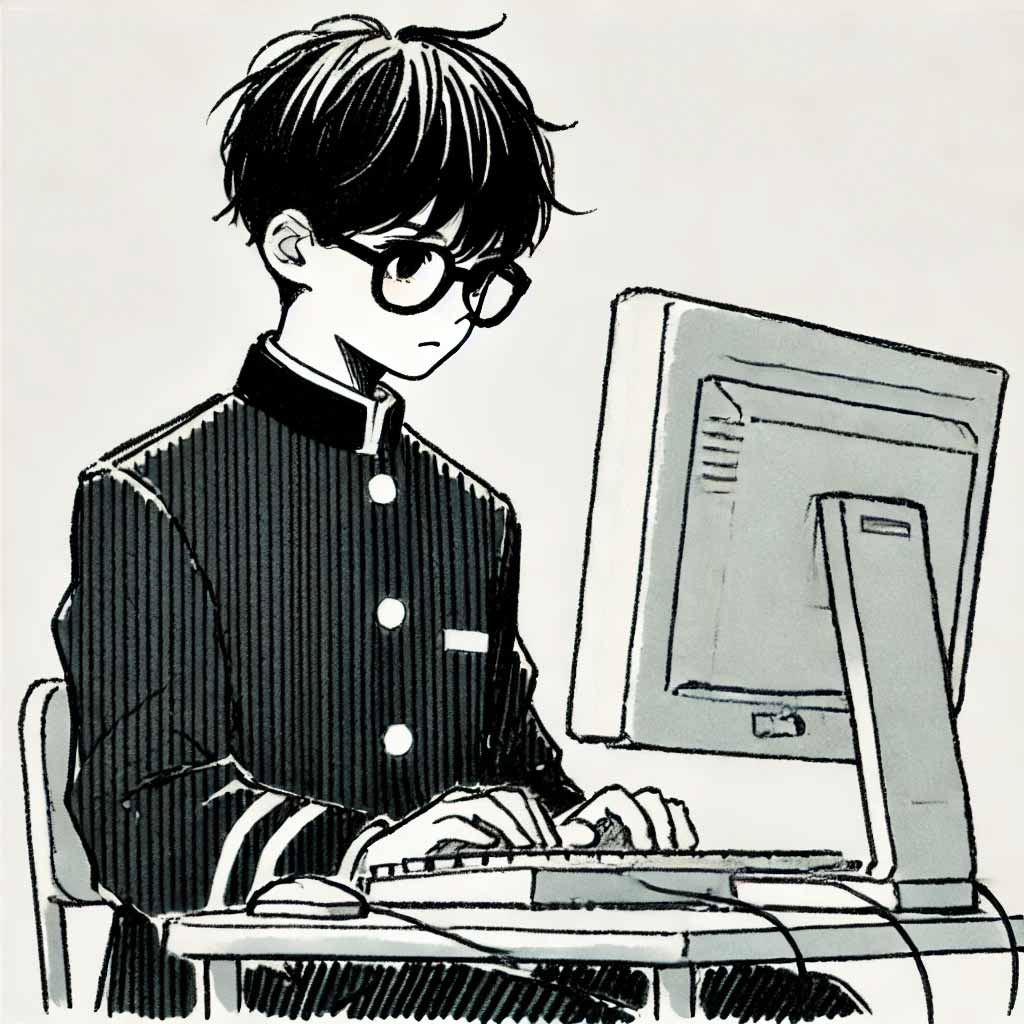





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません