生徒会公約が思いつかない すぐにコピれるイケてる公約50!
🔷 結論:
生徒会の公約は「すごいこと」をひねり出す必要はなく、学校の小さな困りごとを自分が動いて変える約束を、できる範囲で具体的に決めればOK。
🔷 結論:
この原稿のアイデアや型を使えば、「公約が思いつかない…」状態からでも、先生にも友だちにも伝わる公約が必ず作れるよ。
🌟 重要ポイント(まずここを押さえる!)
- ● 理由:
公約が浮かばないのは「才能」ではなく、学校の現状と自分の力をまだ整理できていないだけだから - ● 具体例:
トイレ清掃・換気・意見箱など低コストで実行しやすい改善策だけでも十分に戦える - ● 今日からできる対策:
公約50例や発想法を使って「困りごと→改善策→自分の動き方」をメモ化して公約に落とし込む
📘 この先を読むメリット
公約が思いつかない原因の整理から、公約50例、発想法、先生に通る構成、演説・ポスターでの見せ方、当選後の公約の守り方まで一気に理解でき、「この人に任せたい」と思われる公約が自力で作れるようになるよ。
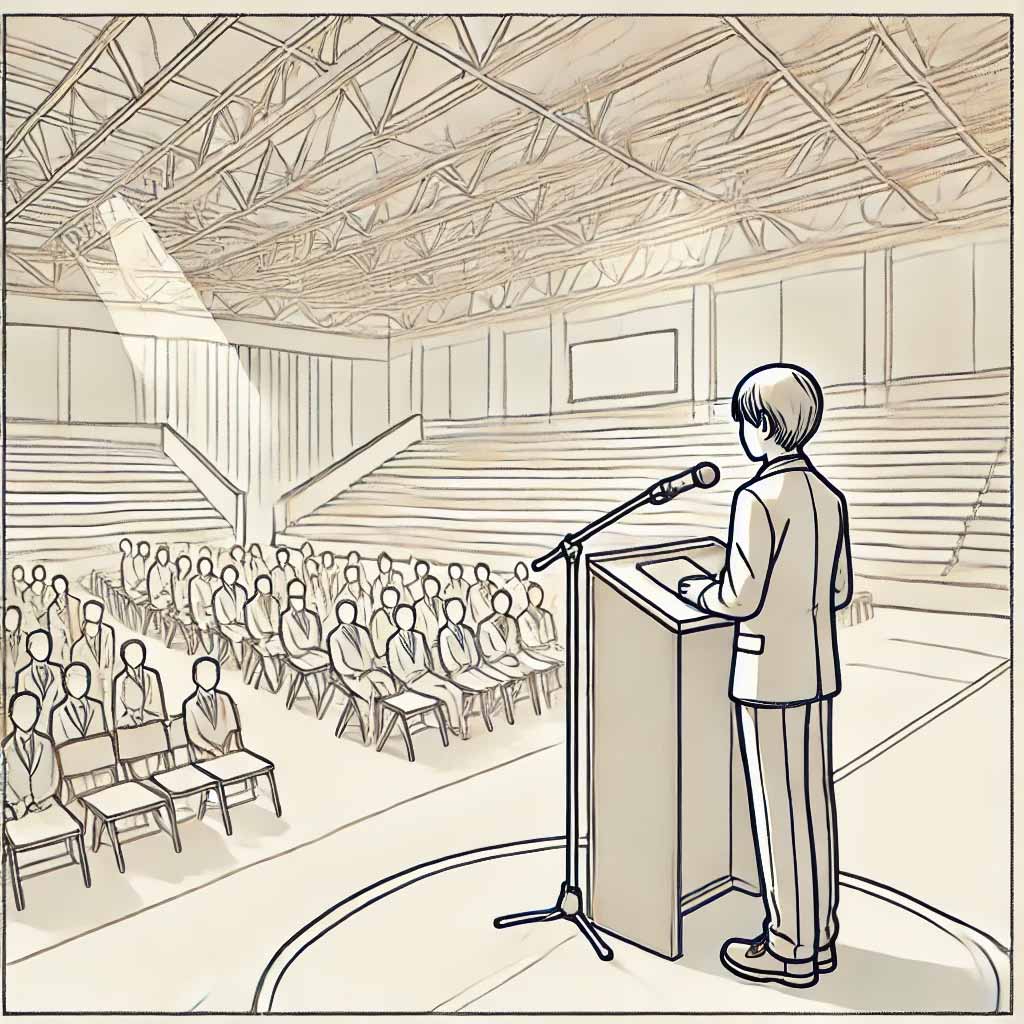
- 1. すぐにコピれるイケてる公約50
- 2. 「公約が浮かばない…焦りがちなあなたへ」
- 3. 同じテーマでも、役職で公約の「言い方」が変わる
- 4. テーマ① みんなの意見を集める仕組みづくり
- 5. テーマ② 学校生活の不便を減らす
- 6. テーマ③ 生徒会活動の見える化
- 7. テーマ④ 行事やイベントを盛り上げる
- 8. テーマ⑤ 生徒会の信頼性アップ
- 9. まずは周りの意見を聞くのがおすすめ
- 10. 公約をブラッシュアップする方法
- 11. 思いつきを「形」にする仕組み
- 12. 「定番すぎずウケる!公約ネタのジャンル4選」
- 13. 「実行可能性を担保する“ギリギリ予算でできる公約”」
- 14. 「インパクトを仕込む公約構成の“演出”テクニック」
- 15. 「実例から学ぶ:成功&失敗した公約ケーススタディ」
- 16. 「公約案を出しても先生や生徒にダメ出しされた時のリカバリー法」
- 17. よくある不安、ここで一気に解消しよう【Q&A】
- 18. 「公約を“見せ方”で差をつけるプレゼン戦略」
- 19. 「当選後に“公約破り”を回避するための設計法」
- 20. まとめ
すぐにコピれるイケてる公約50
まずはいろいろいう前にすぐにコピって提出できる「公約」を50個用意したよ。
すべて「先生にOKをもらいやすい」「コストがかからない」「すぐ実行できる」ことを前提にしている。
どれもシンプルだけど、やると確実に雰囲気が変わる。
そしてどの案も「自分が中心になって動く」という姿勢を見せられるのがポイント。
生徒会選挙では“アイデアの派手さ”よりも、“実現力”と“誠実さ”が信頼につながる。
気になるものを選んで、君なりの言葉に言い換えてみると信ぴょう性が高まるよ。
演説の原稿もポスターも、それだけでぐっと説得力が増すはずだ。
学校環境改善系(1〜10)
| No | アイデア | 良いところ |
|---|---|---|
| 1 |
トイレの消耗品チェック表を設置して、切れたらすぐ交換できる仕組みをつくる。 |
清潔を保てて、先生の手間も減る実用的な提案。 |
| 2 |
教室の換気タイムを毎授業後1分設定し、空気をリセット。 |
空気が変わると集中力もアップ、健康面でも効果大。 |
| 3 |
黒板のチョーク粉を減らすために、黒板消し掃除当番を作る。 |
小さな配慮で教室がきれいに、先生も助かる。 |
| 4 |
ゴミ箱の分別ラベルを貼り替えて、リサイクル率を上げる。 |
エコ活動としてアピールしやすく、成果が目に見える。 |
| 5 |
教室の照明をつけっぱなしにしない“最後の一人ルール”を掲示。 |
節電と責任感の両方を育てられる。 |
| 6 |
雨の日用の傘立て整理カードを作って混乱防止。 |
ちょっとした工夫で廊下が安全に保てる。 |
| 7 |
教室の後ろに“忘れ物回収ボックス”を常設。 |
紛失トラブルが減り、助け合いの雰囲気が生まれる。 |
| 8 |
水筒の置き場を決めて、こぼれ事故を減らす。 |
安全面に配慮があり、実行しやすい。 |
| 9 |
“静かな掃除の日”を週1回設定して集中できる空間にする。 |
掃除の質が上がり、落ち着いた雰囲気が作れる。 |
| 10 |
落とし物ボックスに写真付き掲示を週1回更新。 |
担任の負担を減らし、生徒同士の協力を促せる。 |
行事・イベント活性系(11〜20)
| No | アイデア | 良いところ |
|---|---|---|
| 11 |
文化祭で“1人1作品展示”ブースを作る(絵・詩・写真OK)。 |
誰でも主役になれるチャンスができる。 |
| 12 |
体育祭前に「応援練習フェアプレー宣言」を全クラス掲示。 |
勝敗よりもチームワークを大切にできる。 |
| 13 |
委員会横断の“ありがとうメッセージカード”コーナーを設置。 |
感謝を可視化して、学校全体が温かくなる。 |
| 14 |
行事準備を短縮する“30分片付けチャレンジデー”を導入。 |
時間効率が上がり、次の授業への切り替えがスムーズ。 |
| 15 |
学年別の“得意自慢ショー”を昼休みに開催。 |
個性を出せてクラスを超えた交流が生まれる。 |
| 16 |
三送会で「1年生メッセージリレー」を導入。 |
学年間のつながりを作る感動的な企画。 |
| 17 |
図書委員+美術部で“読書ポスター展”を開催。 |
委員会コラボで企画力をアピールできる。 |
| 18 |
体育祭で“競技外表彰”(応援・団結賞)を設ける。 |
頑張る姿勢を評価できてモチベーションアップ。 |
| 19 |
放送委員とコラボして“昼休みDJリクエストタイム”を復活。 |
校内の雰囲気を明るくして、楽しさを演出できる。 |
| 20 |
校内掲示をポスターコンテスト形式にして、投票で表彰。 |
生徒全員が参加できる民主的なイベントになる。 |
コミュニケーション系(21〜30)
| No | アイデア | 良いところ |
|---|---|---|
| 21 |
“あいさつリレーウィーク”を年3回実施。 |
クラスの雰囲気が明るくなり、声かけの習慣がつく。 |
| 22 |
異学年交流日を月1回設定して、縦割り班で昼食交流。 |
年齢差をこえて協力できる空気が生まれる。 |
| 23 |
“友だち紹介カード”掲示で、新しい友達を増やす。 |
孤立防止にもつながる優しい仕組み。 |
| 24 |
HRの最初に「1分ありがとう発表」を週1回実施。 |
感謝の連鎖をつくって、空気が柔らかくなる。 |
| 25 |
“無言掃除デー”を設けて、協力を体感。 |
言葉がなくても連携できることを学べる。 |
| 26 |
新入生に向けた“やってよかった部活体験談”掲示。 |
勧誘ではなく共感でつながる導入ができる。 |
| 27 |
休み時間に“ちょこっとゲームコーナー”を設ける。 |
コミュニケーションのきっかけが自然にできる。 |
| 28 |
月に1度、他クラスと席交換企画をやって新しい関係を作る。 |
固定化を防ぎ、クラス間の壁が低くなる。 |
| 29 |
“SNSマナー宣言”をクラス代表で読み上げる。 |
ネットトラブルを防ぐ意識を持てる。 |
| 30 |
“笑顔であいさつキャンペーン”の達成率を黒板に掲示。 |
成果が見えると、あいさつが習慣になる。 |
学習・意識向上系(31〜40)
| No | アイデア | 良いところ |
|---|---|---|
| 31 |
“小テストリベンジ週間”を学期末に導入。 |
挑戦を応援する空気を作り、努力が報われる場になる。 |
| 32 |
“朝5分読書チャレンジ”を全校で実施。 |
1日のスタートが落ち着いて、集中力が上がる。 |
| 33 |
“ノートのとり方展示会”を図書室前に設置。 |
勉強法を共有して、みんながレベルアップできる。 |
| 34 |
授業後の質問タイムを“2分だけ”公式ルールに。 |
聞きやすくなり、理解度が上がる。 |
| 35 |
先生に「ここ苦手アンケート」を取って、授業改善提案。 |
先生との協働姿勢を見せられる建設的な案。 |
| 36 |
“学年別おすすめ参考書コーナー”を掲示板で紹介。 |
自主学習のきっかけになる。 |
| 37 |
“お手紙先生感謝デー”で授業の感想を1行で伝える。 |
感謝の文化を作り、関係が良くなる。 |
| 38 |
“給食残さないキャンペーン”を1週間実施。 |
食の大切さと協力意識が育つ。 |
| 39 |
“目標カード”を月初に書いて黒板横に貼る。 |
自分で立てた目標が意識に残りやすい。 |
| 40 |
“勉強×趣味両立エピソード”を募集して共有。 |
無理せず頑張るヒントを全校で共有できる。 |
時間・効率化系(41〜45)/ボランティア・地域連携系(46〜50)
| No | アイデア | 良いところ |
|---|---|---|
| 41 |
掃除の始まりと終わりを知らせる“30秒ベル”を導入。 |
だらだらせずに集中できる。 |
| 42 |
掃除道具の置き場所を統一して、時間ロスをゼロに。 |
動線が整ってスムーズに終わる。 |
| 43 |
朝のホームルームを短縮して“1分振り返り”を追加。 |
時間の使い方を見直すきっかけになる。 |
| 44 |
配布物の電子掲示(QRコード)を導入。 |
印刷の手間が減り、環境にも優しい。 |
| 45 |
昼休み終了5分前に“音楽でお知らせ”を試験導入。 |
雰囲気よく切り替えができる。 |
| 46 |
地域の清掃ボランティアに“月1班制”で参加。 |
地域との関係が深まり、社会性を育てられる。 |
| 47 |
学校花壇の世話を有志で分担して掲示。 |
見た目が変わると気分も変わる、成果が分かりやすい。 |
| 48 |
図書の修復ボランティアデーを設ける。 |
小さな奉仕で大きな信頼が生まれる。 |
| 49 |
地域掲示板に“生徒の作品紹介コーナー”を作る提案。 |
学校の取り組みを外にも広げられる。 |
| 50 |
小学校との“お手伝い交流デー”を年1回開催。 |
後輩に頼られる経験が自信になる。 |
「公約が浮かばない…焦りがちなあなたへ」
では次に、「なぜ公約が思いつかないのか」という原因を整理することが大事だよね。
焦ってもいいアイデアは出づらい。
逆に、今の状態をチャンスととらえて工夫できる発想法を知っておくと、公約ネタのストックがぐっと増えるんだ。
そこで、原因の探り方、見方の変え方、具体的発想法をこのセクションで伝えるよ。
公約作りの土台固めになる部分だから、一緒にじっくり進もう。
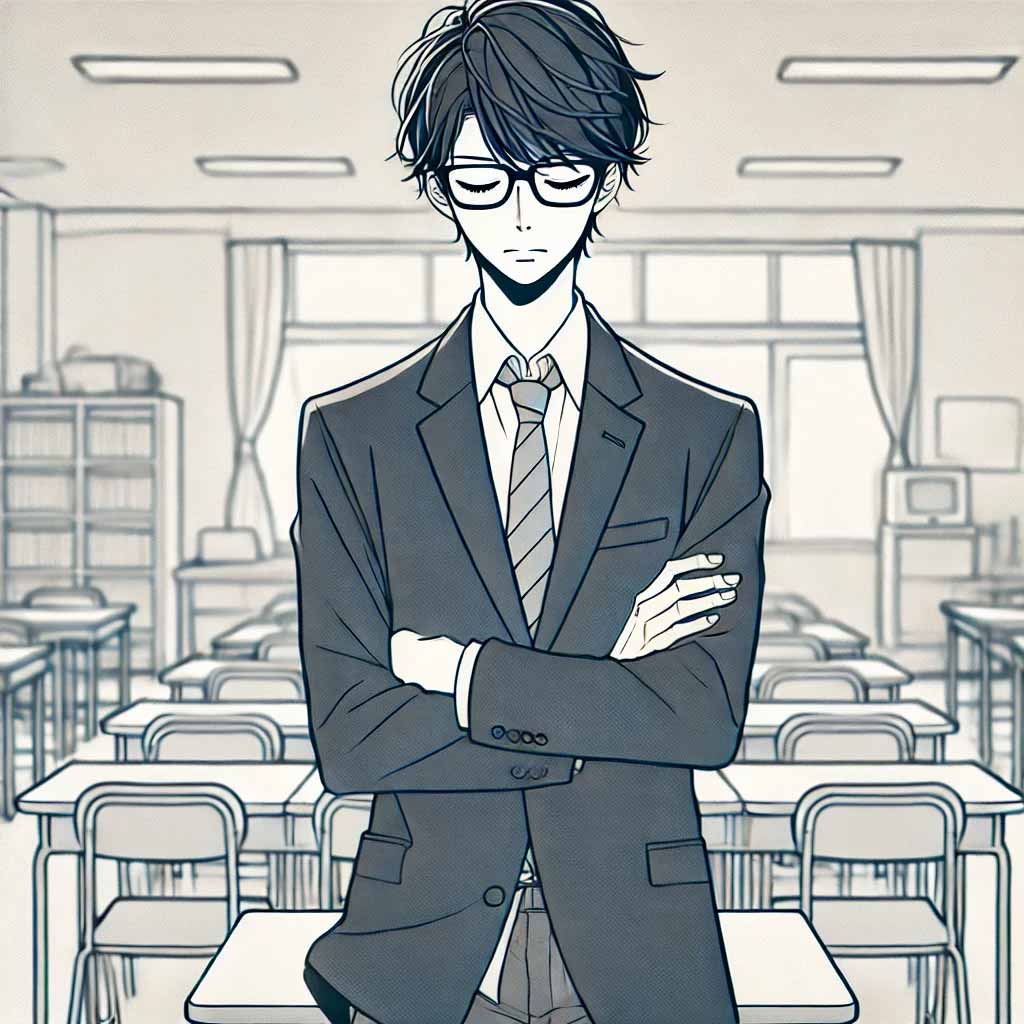
原因を探る:なぜ“思いつかない”のか
公約が浮かばない原因は、人それぞれ違う。
たとえば「学校のことをあまり観察していない」「無理にすごいことを掲げようとしている」「自分の立場を意識しすぎて自由に考えられない」など。
まずは、普段の“悩み”や“困っていること”をメモしてみて。
学校生活で「ここが変わったらいいな」と感じたことを拾っていくと、公約の種が見えてくるよ。
思いつかない状態はむしろチャンス
アイデアが全く出ないということは、逆に“白紙”という自由地帯でもあるんだ。
既存の枠にとらわれない発想を許すタイミング。
「ありきたりなアイデアでは勝てない」と思ってしまうと、手が止まる。
逆に、“少し変なアイデア”も許してあげていい。
その中から、実現できそうなものを選んで磨いていけばいいんだ。
ブレスト(発想法)でアイデアを刈り取る
ブレスト=ブレインストーミングを活用すると、公約アイデアがたくさん出る。
たとえば、クラスメイトとペアで「困っていることリスト」を出し合って、それを公約ネタに変換する。
「もし休み時間が時間無制限だったら?」という仮定で発想することも有効。
形にとらわれずアイデアを出したら、それを後から絞って“実現可能なもの”に調整すればいいんだよ。
インプット型発想 – 他校・ネット・漫画から盗む技術
他の学校の生徒会公約を見たり、ネットの記事を読んだり、漫画の中の学校描写を観察したりするのもアイデア源になる。
「この学校はこんな公約を出してたな」「こういう学校活動いいな」と思ったことを、自分なりに咀嚼して取り込む。
ただし、丸パクリはダメ。
自分の学校に合うようにアレンジすること。
こうしたインプットを重ねて、脳の引き出しを増やしておくと、公約案が自然と出やすくなるよ。
同じテーマでも、役職で公約の「言い方」が変わる
生徒会の公約って、何をやるかだけじゃなくて「誰が言うか」で説得力が変わるよね。
会長は全体の方向を示す。
副会長は動かすための調整役。
書記は情報を正確にまとめる役。
会計はお金と実現性を押さえる役。
ここでは同じテーマを5つ用意して、役職ごとのニュアンスの違いが一発で分かる表にしたよ。
テーマ① みんなの意見を集める仕組みづくり
「声を聞きます」って言うのは簡単。
でも役職が違うと、約束の中身がちゃんと変わる。
会長は学校全体への宣言。
書記は記録と共有。
会計は予算と現実ライン。
同じテーマでも、担当っぽい言い方に寄せると一気にそれっぽくなるよ。
| 役職 | 公約の例 | ニュアンスの違い |
|---|---|---|
| 会長 | 全校生徒の声を学校運営に反映させるため、定期的な意見募集の場を作ります。 | 全体を動かす立場。学校全体への約束。 |
| 副会長 | 会長を補佐し、各学年の意見が偏らないよう集約をサポートします。 | 会長の方針を現場で支える役割。 |
| 書記 | 集まった意見を正確に記録し、誰でも確認できる形でまとめます。 | 記録・整理がメイン。 |
| 会計 | 意見をもとに必要な予算があるかを検討し、実現可能性を確認します。 | お金の視点から支える。 |
テーマ② 学校生活の不便を減らす
「学校を過ごしやすくする」は人気テーマ。
ここも役職で言い分が変わるよ。
会長は目標をドンと置く。
副会長は優先順位と段取り。
書記は情報の整理。
会計は費用と無理のない提案。
この差が分かると、公約が急にプロっぽくなるんだよね。
| 役職 | 公約の例 | ニュアンスの違い |
|---|---|---|
| 会長 | 学校生活の「ちょっと不便」を改善し、過ごしやすい学校を目指します。 | ビジョンを示す役割。 |
| 副会長 | 各クラスの不便な点を集め、優先順位をつけて改善を進めます。 | 実務寄りで調整役。 |
| 書記 | 不便に関する意見や改善案を整理し、会議で共有します。 | 情報を支える裏方。 |
| 会計 | 改善に必要な費用を把握し、無理のない形で提案します。 | 現実的な判断役。 |
テーマ③ 生徒会活動の見える化
生徒会って、やってることが見えないと「結局なにしてるの」ってなる。
だから見える化はかなり強いテーマ。
会長は信頼づくりの宣言。
書記は会議内容や決定事項の共有。
会計はお金の報告で透明性を足す。
この役職っぽさが出ると、文章が一気に締まるんだ。
| 役職 | 公約の例 | ニュアンスの違い |
|---|---|---|
| 会長 | 生徒会の活動内容を積極的に発信し、信頼される生徒会を作ります。 | 生徒会全体の顔。 |
| 副会長 | 活動内容が分かりやすく伝わるよう発信方法を工夫します。 | 実行・改善担当。 |
| 書記 | 会議内容や決定事項をまとめ、掲示や配信で共有します。 | 記録と伝達の中心。 |
| 会計 | 活動に使った予算を分かりやすく報告します。 | お金の透明性担当。 |
テーマ④ 行事やイベントを盛り上げる
行事系は人気だけど、ふわっとすると落ちやすいよね。
だから役職の色をちゃんと出すと強い。
会長は「参加しやすい行事」に方向を置く。
副会長は連携と運営。
書記は準備と反省点を次に回す。
会計は予算管理で地に足をつける。
同じテーマでも役割に合わせるだけで現実味が出るよ。
| 役職 | 公約の例 | ニュアンスの違い |
|---|---|---|
| 会長 | 生徒全員が参加しやすい行事づくりを目指します。 | 方向性と理想を示す。 |
| 副会長 | 各委員会や学年と連携し、行事の運営を支えます。 | 調整と現場対応。 |
| 書記 | 行事の準備や反省点を記録し、次につなげます。 | 振り返り担当。 |
| 会計 | 行事に必要な予算管理を行い、無駄のない運営をします。 | 金銭管理役。 |
テーマ⑤ 生徒会の信頼性アップ
最後は王道の「ちゃんとやる」系。
ここも役職で言い方を変えると刺さるんだ。
会長は責任を引き受ける宣言。
副会長は進行の管理とフォロー。
書記は進捗を記録して見える化。
会計は予算面で実行を支える。
同じテーマでも、役職っぽさが出ると納得感が上がるよね。
| 役職 | 公約の例 | ニュアンスの違い |
|---|---|---|
| 会長 | 約束した公約を最後まで実行する生徒会を目指します。 | 責任の最終地点。 |
| 副会長 | 進行状況を確認し、遅れが出ないよう支えます。 | 管理・フォロー役。 |
| 書記 | 公約の進捗を記録し、現状を分かりやすく伝えます。 | 見える化担当。 |
| 会計 | 公約実現に必要な予算を管理し、計画的に使います。 | 実行可能性の担保。 |
まずは周りの意見を聞くのがおすすめ
生徒会の公約がどうしても思いつかないとき。
一人で机に向かって考え込むより、いちばん最初にやってほしいのが「周りの声を聞くこと」だよ。
生徒会は自分のアイデアを発表する場ではなく、みんなの学校生活をよくするための役割。
だからこそ、答えはだいたい自分の外に転がっているんだ。
なぜ「自分で考える」より「みんなに聞く」方が強いのか
生徒会は、キミ一人のためのものではないよね。
全校生徒の代表として動く組織だからこそ、多くの人が共通して感じている不便や願いを拾えるかどうかが大事になる。
自分だけの視点では気づけなかった「それ、地味に困ってた」「言われてみれば確かに」という声は、実は公約の宝庫。
共感されやすい公約ほど、「みんなの実感」から生まれやすいものだよ。
何気ない会話の中に、公約のヒントがある
クラスの友だち。
部活の仲間。
廊下ですれ違う先輩や後輩。
そして、日々学校を見ている先生。
こうした人たちとの雑談の中に、公約のヒントは自然に出てくるよ。
「移動教室の荷物が重い」「昼休みに静かに過ごせる場所がほしい」「この部活、もっと知られていいのに」。
こんな一言が、実は多くの生徒の「あるある」だったりするよね。
強い公約は、派手な発想よりも、こうしたリアルな声から育つんだ。
意見を集めるときに大事なのは「聞き方」
意見を集めるときは、聞き方がとても重要。
「生徒会で何してほしい?」と聞くよりも、
「学校生活でちょっと困ってることってある?」
「ここ、こうだったらいいのにって思うことある?」
こんな聞き方のほうが、本音が出やすい。
また、相手の意見を否定しないことも大切なんだ。
「それは無理じゃない?」ではなく、「なるほど、そう感じてるんだね」と受け止める。
安心して話せる雰囲気があると、意見は自然と集まるよ。
この“安心して話せる空気”が、公約づくりの土台になるんだ。
公約をブラッシュアップする方法
思いついたアイデアをそのままにしておくのはもったいないよね。
言葉を少し磨くだけで、伝わり方がぜんぜん違ってくるんだ。
ここでは、具体的で信頼される公約に仕上げるためのコツを紹介するね。
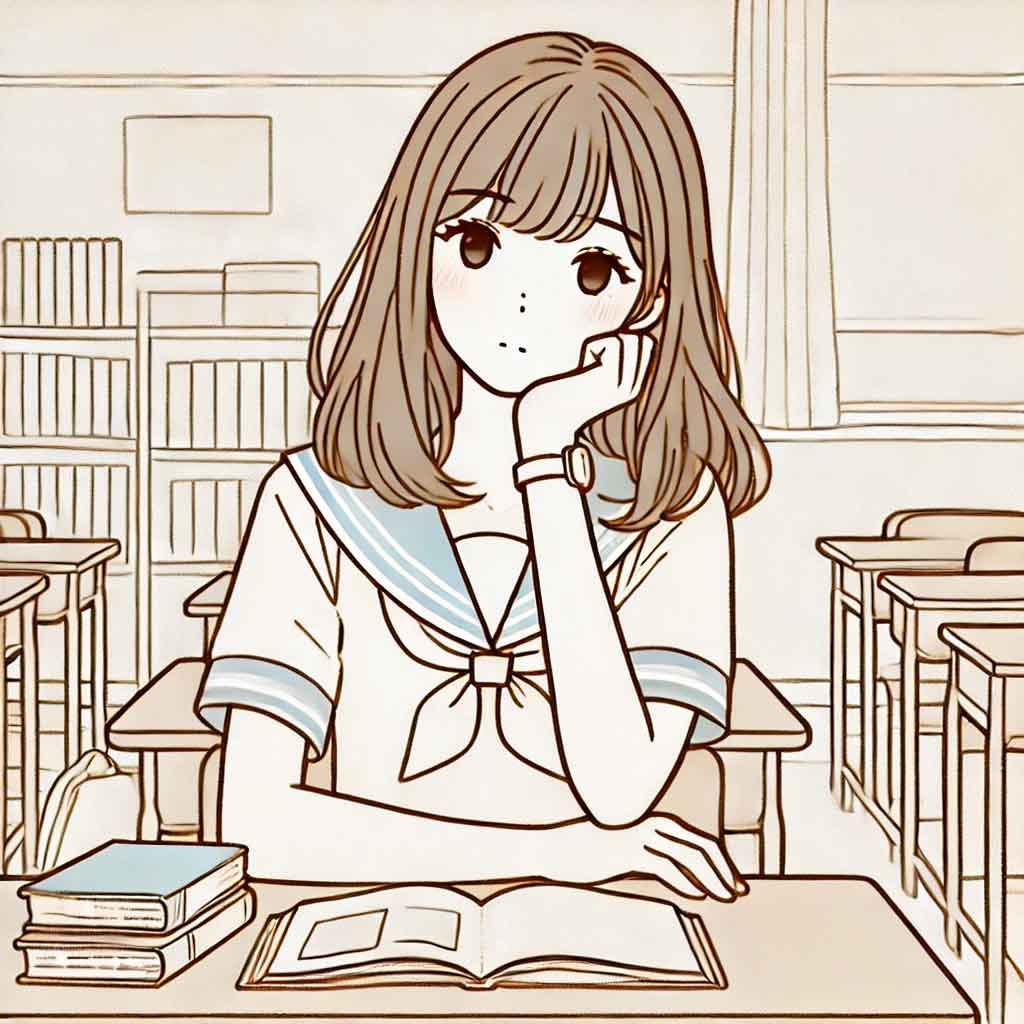
抽象ワードを数字に変える
「もっと明るい学校にしたい」って言葉、よく聞くけど少しふわっとしてるよね。
そんなときは数字で表すのがポイント。
「明るい」を「毎朝のあいさつ率を2倍にする」みたいに変えるだけで、ぐっと伝わるんだ。
数字が入ると、やる気や計画性が見えて説得力が出る。
そして、結果が見えるから達成感もある。
抽象的な言葉を具体的な数字に変えることで、公約は一気に“実行できそう”なものに変わるよ。
「みんな」を定義し直す
「みんなで楽しい学校に」って言葉、よくあるけど“みんな”って誰のこと?
クラス? 学年? 全校?
そこをはっきりさせるだけで、ぐっと印象が変わる。
「1年生が安心して登校できる学校に」って言い換えるだけで、目的が明確になるんだ。
対象がわかると、行動が見えてくる。
あいまいな“みんな”より、具体的な相手を思い浮かべるほうが、心に届くよね。
先生チェックに通るか確認
どんなに素敵な公約でも、学校のルールや安全面に合わなければ実現できないこともある。
だからこそ、思いついたら先生の視点で一度確認してみよう。
校則や予算、安全、スケジュールをリスト化して照らし合わせるんだ。
「放課後の自由時間を作る」なら、教室の管理や先生の負担も考える。
現実を見ながら提案する生徒は、頼もしく見えるよ。
理想だけじゃなく、実行できる形に落とし込むのがプロの発想だね。
演説でどう話すかを想定
公約は書くだけじゃなく、“話して伝わるか”も大切。
実際に声に出して読んでみよう。
長すぎたり、リズムが悪かったりすると伝わりにくいんだ。
短くて覚えやすいフレーズを意識してみて。
「○○を変える3つの約束」みたいな言葉は印象に残る。
スライドやジェスチャーも合わせると、さらに伝わりやすい。
自分がワクワクして話せる内容なら、それが一番の説得力になるよ。
思いつきを「形」にする仕組み
せっかくいいアイデアが出ても、形にできなきゃもったいない。
ここでは、思いつきを“実際の行動”に変えるためのステップを紹介するね。
準備の段階からまとめ方まで、ひとつずつ見ていこう。
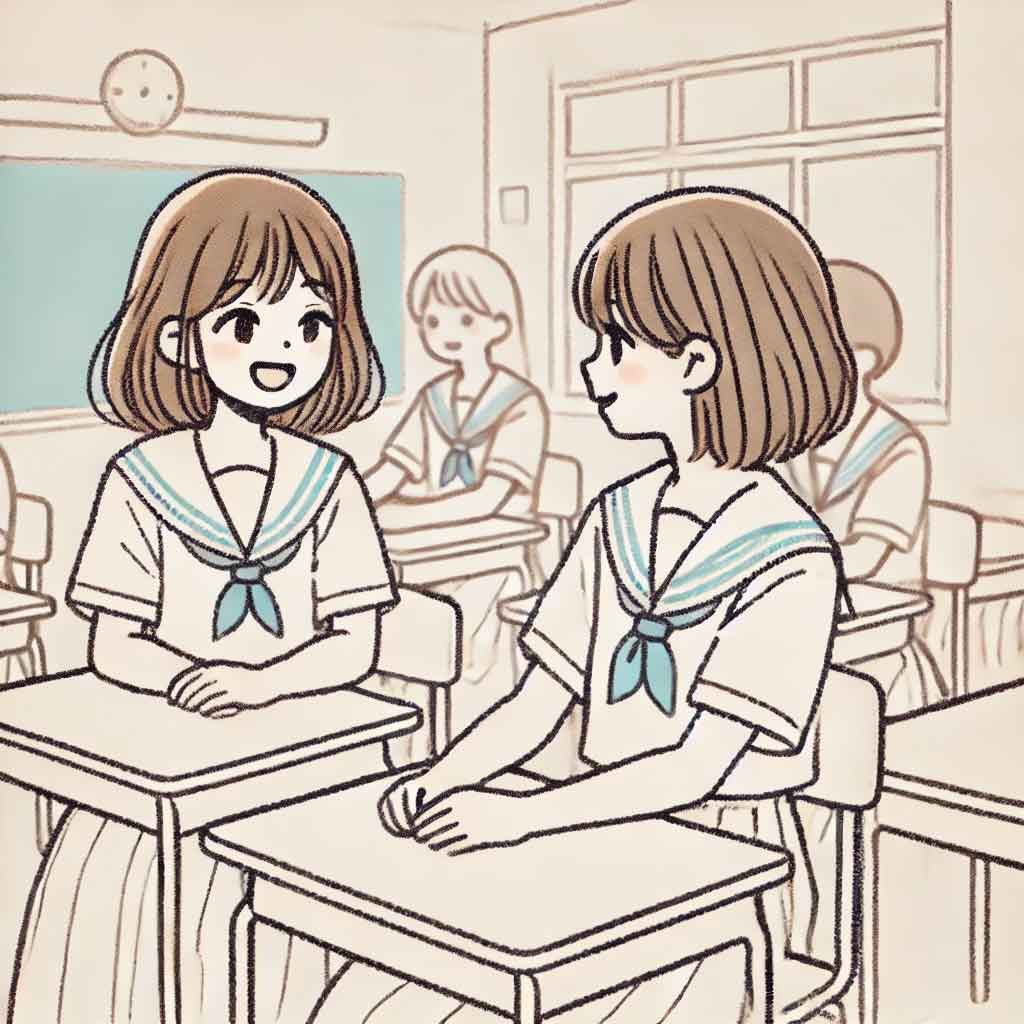
ブレスト表のテンプレート
頭の中だけで考えてると、アイデアがどんどん散らかっちゃうよね。
そんなときは「課題」「アイデア」「実現方法」「メリット」の4マス表を使おう。
紙でもスマホでもOK。
たとえば「掃除がバタバタする」→「放送でタイムアラームを流す」→「準備がスムーズになる」。
こうして整理すると、自分の考えが一気に現実に近づくんだ。
見える化すると、行動しやすくなるよ。
仲間との話し合いで磨く
アイデアって、人に話すと急に形になるもの。
友達に「これどう思う?」と聞くだけでも新しい視点がもらえる。
とくに笑いのツボがわかる友達と話すと、言葉の伝わり方が変わる。
「それ、おもしろいけど実際どうするの?」って言われたら、それが最高の磨きチャンス。
人に話すことで、より現実的な公約になっていくんだ。
仲間とのブレストは最強のツールだよ。
AI(GPT)や先生に相談してみる
どうしても煮詰まったときは、AIに聞いてみるのもあり。
「生徒会の公約を考えたいけどアイデアが出ない」と打ち込めば、ヒントをくれる。
もちろん、それをそのまま使うんじゃなくて、自分の意見を加えることが大事。
先生にも相談して、「そのアイデアいいけど、こうすればもっと現実的」とアドバイスをもらおう。
AIと先生、両方の視点で磨くと、精度の高い公約になるよね。
ポスター・演説との連動
公約が決まったら、見せ方も考えよう。
ポスターやスピーチに同じキャッチコピーを使うと印象が強くなる。
たとえば「掃除を変える3分革命」みたいな短い言葉は覚えやすい。
SNSで投稿するときも統一すると、一貫性が出て信頼感が上がる。
デザインと話し方をそろえると、“本気でやる人”って伝わるよ。
最後は見せ方で差がつく。
そこまで考えられたら完璧だね。
「定番すぎずウケる!公約ネタのジャンル4選」
「ウケる」って言葉、ちょっとカジュアルだけど大事。
生徒の心を掴むには、“ありきたり”ではない公約ジャンルが効くんだ。
でもまったく奇をてらうだけじゃ現実性で失う。
だから、定番ジャンルをベースに「ちょっと意外性」を足したネタ4つを紹介するね。
これらをヒントに、自分らしい公約テーマを練ってみよう。

学校環境改善系(トイレ・掃除・換気など)
学校生活で毎日使う場所、トイレ・廊下・教室の掃除や換気に目を向ける公約は、実感度が高い。
例えば「トイレの衛生強化」「教室の空気入れ替えタイム設置」など。
これは“具体”で“身近”。
生徒会活動として信頼を得やすいジャンルでもあるんだ。
行事・イベント系(文化祭・企画・コラボ系)
文化祭・体育祭・季節イベントに新企画を足す公約も人気。
たとえば「学年混合企画」「クラス対抗ゲーム大会」「校外コラボイベント」など。
企画性があるから“学校生活を楽しくする約束”として響きやすい。
ただし、準備と時間との兼ね合いを考えることが重要だよ。
生徒参加型・民主系(意見箱・アンケート・座談会)
生徒みんなの声を聞きます、という公約も強い。
「意見箱設置」「月1アンケート」「学年別座談会」など。
これは“約束”というより“仕組みを作る”アプローチ。
実現すれば、生徒と役員・先生の交流促進にもなるから相乗効果あり。
コミュニケーション系(あいさつ運動・縦割り交流など)
あいさつ運動強化、異学年交流プロジェクト、部活間交流会など。
人とのつながりを育てる公約だから、学校の雰囲気を変える力を持つ。
“生徒”同士の距離を縮める要素が入る公約は印象に残りやすいんだよ。
「実行可能性を担保する“ギリギリ予算でできる公約”」
思いつく公約があっても、実際にやれなかったら意味がない。
予算や時間、先生の協力などを見越して「本当にできること」を設計しなきゃ。
この章では、予算を抑えながらも実行可能なアイデア、制度活用、協力型、段階構成などを使って、公約を現実に近づける方法を伝えるからね。
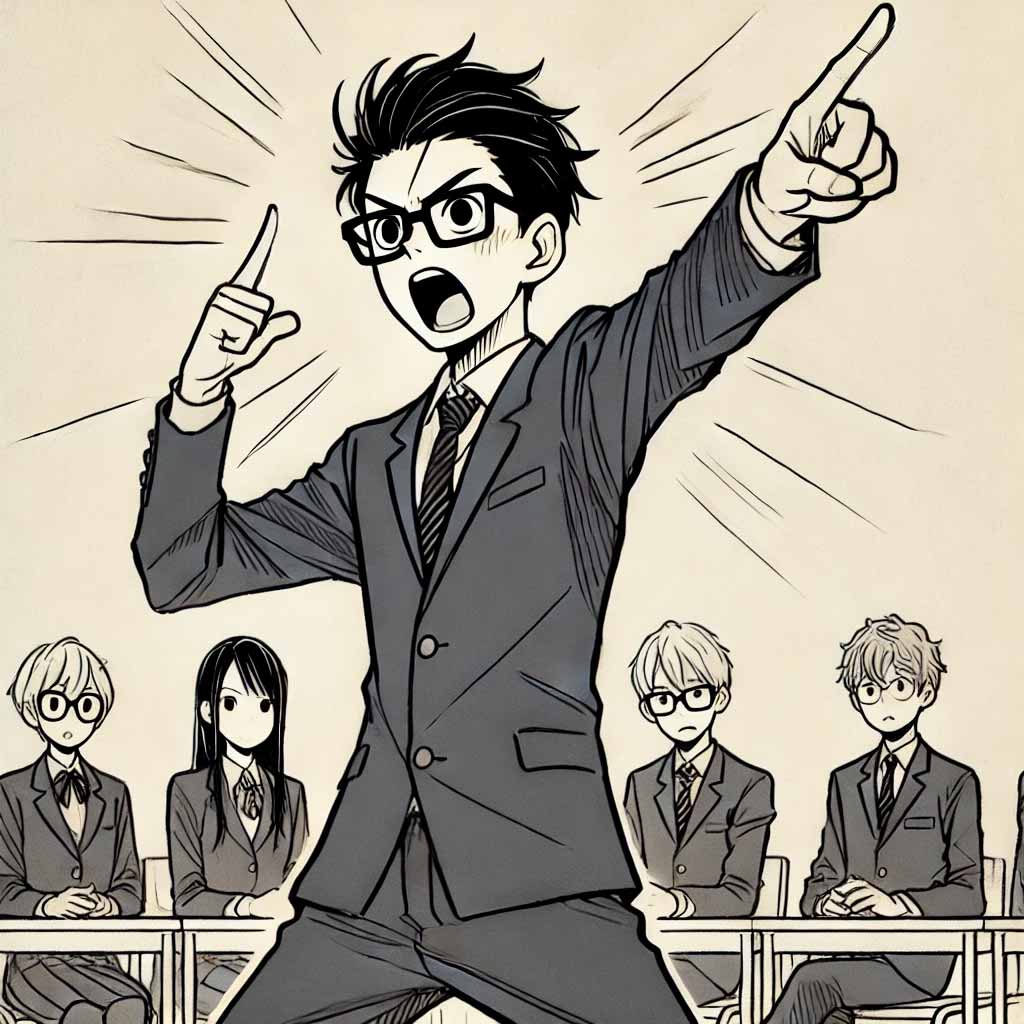
教材・備品を活用するアイデア
学校にすでにある教材・備品を使い回すならコストは最小限。
「余っている図書をリサイクル棚に」「使っていない備品を共同使用」など。
新規購入を伴わない約束なら、先生や役員も承認しやすい。
学校の仕事を“見直し・再活用”という視点で見ると、公約ネタが増えるかもね。
既存制度の調整で実現できること
学校にすでにある制度を少し変えることも強い公約になる。
たとえば「予鈴の変更」「掃除時間の調整」「移動時間に音楽を流す」など。
完全ゼロから作るより、既存制度を“転用”する方が現実的だ。
先生との相談もしやすくなるよね。
ボランティアや協力型でコストを抑える
有志を募って手伝ってもらう、地域や保護者の協力を仰ぐ、ボランティア形式で進めるという手も使える。
たとえばイベント準備を生徒で分担、飾り付けを親御さんにお願い、など。
お金をかけずに“人のつながり”で支えられる公約、魅力的でしょ?
小さく始めて拡大するステップ型構成
いきなり大きな約束をしないで、“小フェーズ”から始めて徐々に拡大する方法も有効。
「まずはクラス単位で試す」「半期だけ実験実施」など。
うまくいけば他学年にも展開。
この方法なら先生からも了承を取りやすくなるし、失敗リスクも小さい。
「インパクトを仕込む公約構成の“演出”テクニック」
いいアイデアを出しても、相手に響かなきゃ意味がないよね。
だから“演出”がカギを握る。
言葉の使い方、見せ方、差別化の工夫を取り入れて、あなたの公約を目立たせよう。
キャッチコピー、数字・期間、スケジュール、差別化要素――これらを駆使すれば、「この人になら任せたい」と思ってもらいやすくなるんだ。
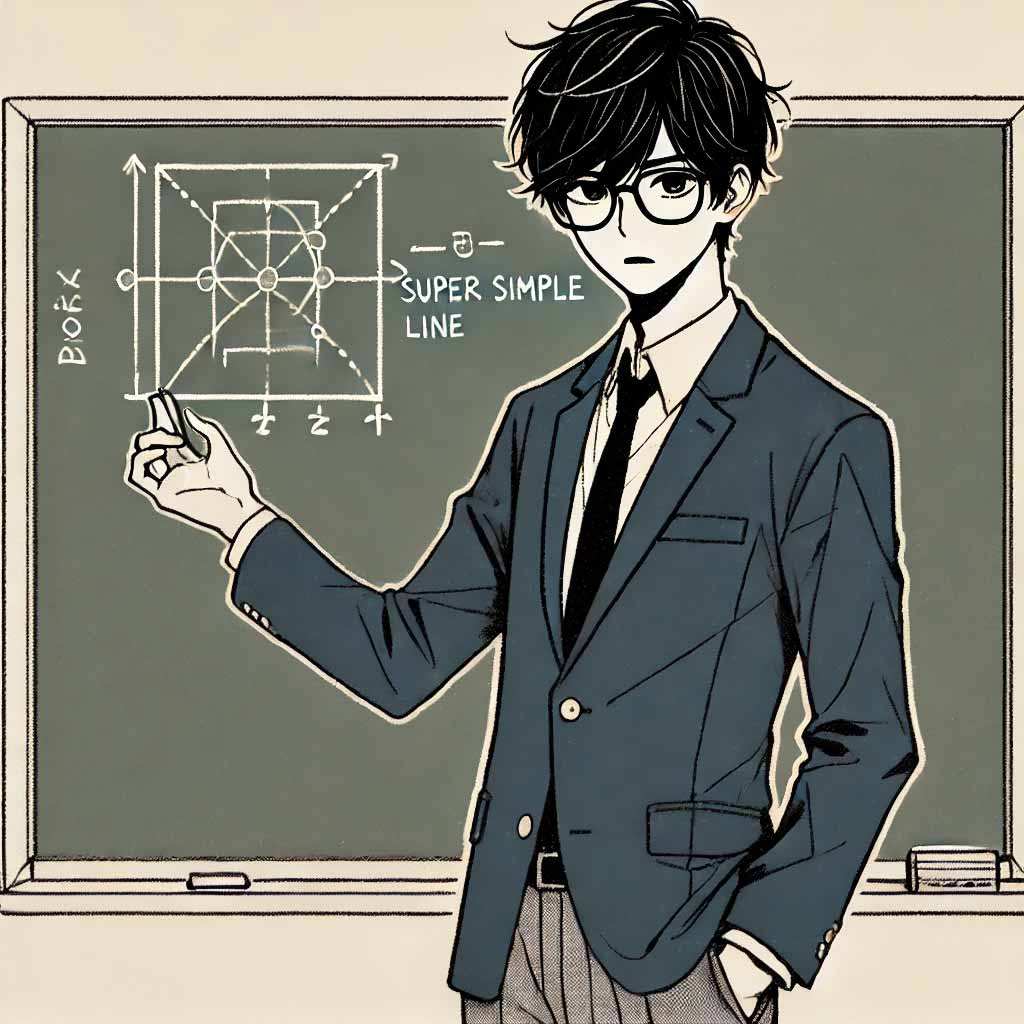
キャッチコピーで注目を引く方法
キャッチコピーは「何を掲げているか」が一瞬で伝わるフレーズ。
たとえば「空気を変える1分換気タイム」みたいな短く耳に残る言葉。
これが演説ポスターの目玉になる。
最初で心を引く役目を持たせよう。
数字・期間を明示して信頼感を出す
「毎月1回」「3か月で」「年間○回」など、数字や期間を明示すると、“具体性”と“責任感”が出るんだ。
「掃除強化します」よりも「毎週月曜に廊下掃除15分実施」などがいい例。
こういう具体性が、先生や生徒の「本当にできる?」という疑問を和らげてくれるよ。
ツメとして「実施スケジュール案」まで示す
公約の後に「いつまでに」「誰が」「どの順番で」実行するかをスケジュール案として示すと説得力アップする。
演説資料やポスターに簡単な実施表を入れるといいよね。
「まず調査、次に準備、最後に実行」みたいな段取りを見せる。
差別化要素を入れて他候補と戦う(“ウケ”を仕込む)
ほかの立候補者と差をつけたいなら、少し“ウケ”を入れた工夫を。
たとえば、おもしろネタ+真面目ネタを混ぜる、語呂合わせにする、キャッチカラーを入れるなど。
でも変にふざけすぎると信頼を失うから、ほどほどに。
“あなたらしさ”を出す差別化が勝負を決めるかも。
「実例から学ぶ:成功&失敗した公約ケーススタディ」
理論だけ聞いてもピンと来ないかもしれないね。
だから、実際に成功した公約と失敗した公約を見て、「なぜ成功したか」「なぜ失敗したか」を分析しよう。
そうすると、自分の公約に入れるべき要素、避けるべき要素が見えてくる。
リアルな事例は説得力があるからね。

成功例その1:環境改善系の丁寧公約
たとえば、「教室の換気時間を毎授業後5分入れる」「廊下にごみ箱を増やす」などの公約が、実際に受け入れられて成功したケース。
これらは“小さくても確実に変わる”タイプ。
生徒が日常で実感できる改善だから、信頼を得やすいんだ。
成功例その2:意見反映型・民主系公約
「年に2回意見箱でアンケートを取る」「生徒座談会を開く」など、公約自体が“声を聴く仕組み”になっているもの。
これは、生徒との距離を縮めて、信頼を作るタイプ。
実行後、生徒側の満足感も上がるから、結果的に学校生活の質向上にもつながるんだ。
失敗例その1:曖昧すぎて信頼を失った公約
「もっと楽しい学校にします」だけでは抽象的すぎて、何をするか見えない。
結果、「口だけでは?」と思われてしまって信用を失うことも。
約束だけ大きくて、具体性や実行計画が欠けていると危険。
失敗例その2:コスト過多で断念した公約
すごくいいアイデアでも、お金や時間が足りなくて途中で断念した例。
たとえば「クーラーを増設する」「備品を大量に購入する」など。
実施できなければ「公約破り」になってしまうから要注意だよ。
「公約案を出しても先生や生徒にダメ出しされた時のリカバリー法」
批判やダメ出しはつきもの。
でも、それを恐れてアイデアを出さないのはもったいない。
ダメ出しを前向きに受け止めて改善できる技術を持つと、公約案そのものも強くなるから。
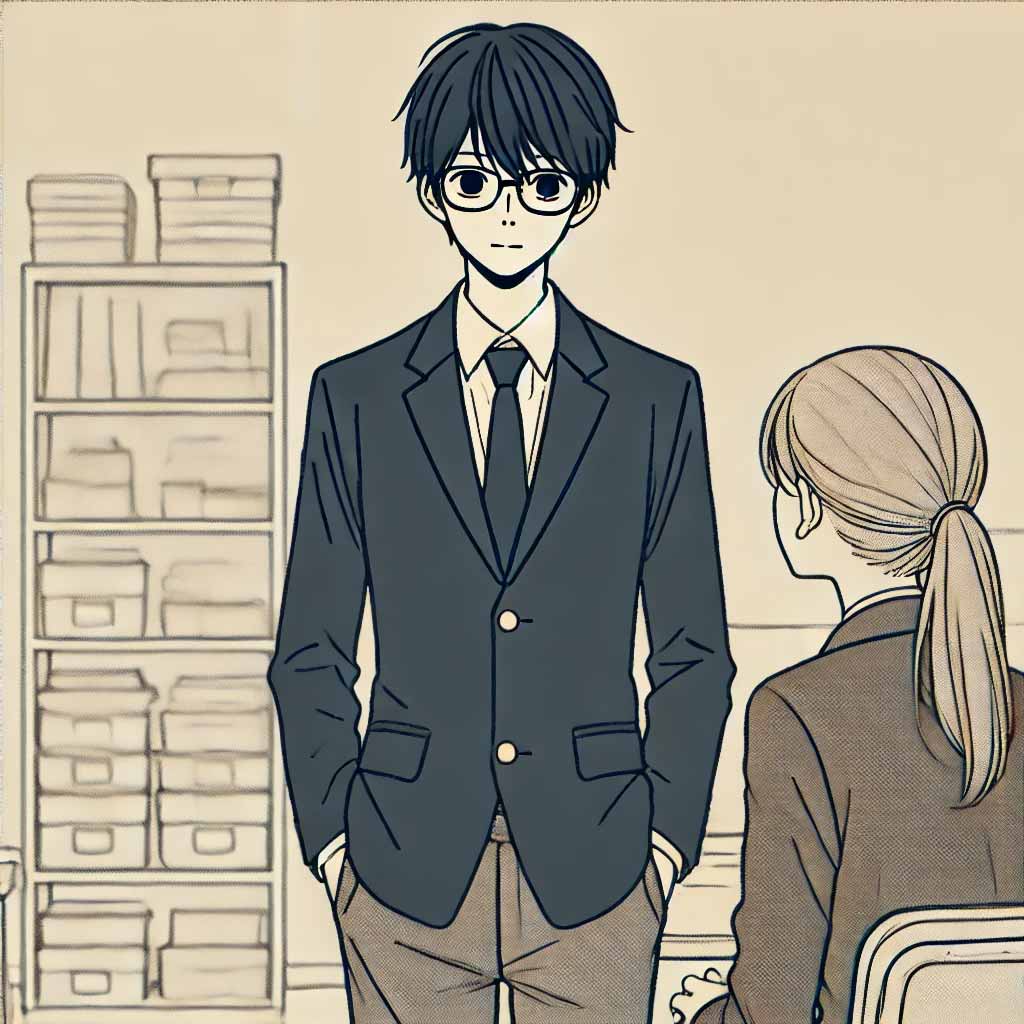
フィードバックを活かして“改変”の技術
ダメ出しをされたら、一旦受け入れて「どこがどうダメか」を整理する。
“完全変更”ではなく“部分改変”で応用する。
元の公約案を捨てず、批判をヒントに改善する発想力が強みになる。
妥協ラインをあらかじめ考えておくメンタル術
最初から“これは譲れないライン”と“妥協できるライン”を決めておくといい。
ダメ出しには、妥協する部分を先に認識しておけば動揺しない。
心が折れないように、自分の中で耐性を作っておこう。
“代替案”を複数準備しておく理由
最初の案だけだとダメ出しで止まるけど、代替案を複数持っておけば、話し合いで“この案ならいい”となる可能性が高い。
A案・B案・C案を用意しておき、フィードバックを受けて切り替える戦略だね。
批判への切り返し表現テンプレート
批判されたときの言い訳や反論文句も用意しておくといい。
例えば「コストの面については代替手段を検討します」「まず試験運用から始めます」など。
言葉で信頼をつなぎとめる術も大切。
よくある不安、ここで一気に解消しよう【Q&A】
公約は何個言えばいい?
A.多くても3つまでで十分。むしろ1〜2個のほうが信頼されやすい。
たくさん並べると「結局どれを本気でやるの?」と思われがち。
それよりも、確実にやり切れる公約を1〜2個出して、「これは自分が中心になって動きます」と言い切るほうが強いよ。
数より“実行できそう感”が大事。
会長じゃなくても大きい公約を言っていい?
A.言っていい。ただし“役職に合った言い方”にするのがコツ。
副会長や書記、会計でも、大きなテーマを扱ってOK。
ただし「全部自分が決めます」ではなく、「会長を支えながら」「記録や調整を通して」など、自分の役割に引き寄せた言い方に変えると一気に現実的になるよ。
お金がかかる案はどう言い換える?
A.「買う」じゃなく「工夫する」「試す」に言い換える。
「新しく買います」は、先生チェックで止まりやすい。
そんなときは、既存の物を活用する、まずは一部で試す、ルールや運用を変える、このどれかに置き換えてみて。
予算ゼロ〜少額でできる形にすると通りやすいよ。
校則に関わる内容はどこまでOK?
A.校則そのものを変える約束はNG。運用や話し合いはOK。
「校則を変えます!」はさすがに厳しい。
でも、実態をアンケートで集める、意見として先生に届ける、困っている声を見える化する、こうした“話し合いの場を作る”公約なら十分アリ。
攻めすぎないのが長く信頼されるコツだよ。
先生に「無理」と言われたらどう直す?
A.そのまま引っ込めず、「どうすればできるか」を聞く。
ダメ出し=失敗、じゃない。
「どこが難しいですか?」
「ここを変えたらどうでしょう?」
と聞いて、部分修正に持ち込もう。
先生と一緒に直した公約は、むしろ信頼度が上がる。
人気投票っぽくならない話し方は?
A.「楽しさ」より「理由」と「動き方」を多めに話す。
ウケ狙いだけだと軽く見られがち。
なぜそれが必要か、誰が困っているのか、自分は何をするのか、この3点を入れるだけで、話が一気に真面目になるよ。
笑いは“スパイス”くらいがちょうどいい。
友だちの公約とかぶったらどうする?
A.テーマが同じでもOK。やり方と立場で差をつけよう。
「意見箱」や「あいさつ運動」はかぶりやすい。
そんなときは、対象を変える、頻度や方法を変える、自分の役職目線に寄せる、これだけで別物になる。
大事なのは丸パクリしないことだけ。
当選後に公約が進まない時はどう報告する?
A.黙らない。進んでいない理由を正直に伝える。
進まないこと自体より、「何も言わない」のが一番信頼を落とす。
どこで止まっているか、なぜ難しいか、次にどうするか、これを短くでも報告しよう。
正直な報告=公約破りじゃないよ。
「公約を“見せ方”で差をつけるプレゼン戦略」
いい約束を言っても、見せ方がダサいと伝わらない。
視覚・媒体・プレゼンテーションで差をつける方法を使おう。
印象操作という言葉はあまり好きじゃないけど、見せ方を工夫するのは「伝える力」の一部だからね。
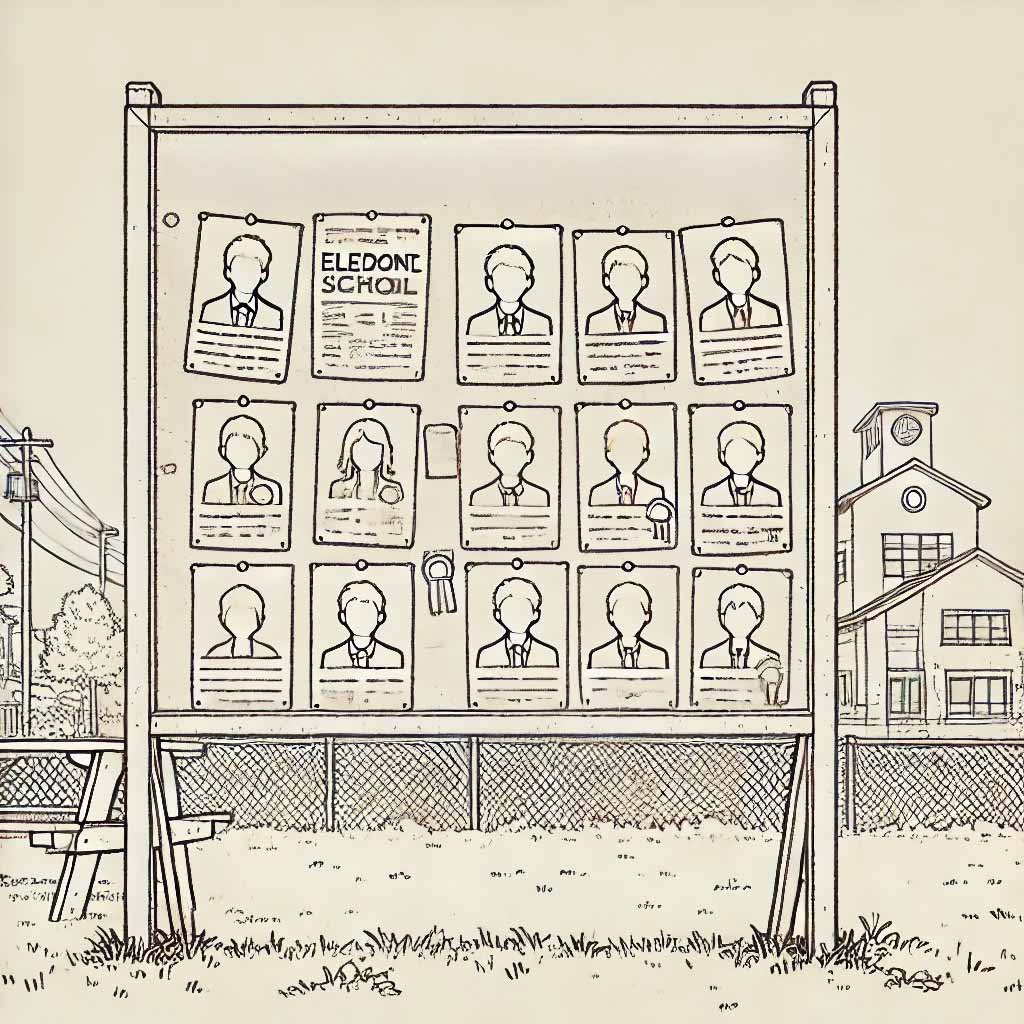
ポスターデザインのコツ(色・レイアウト・図)
ポスターに使う色・レイアウト・イラストがいい感じだと目を引く。
派手すぎず、読みやすさ重視。
見出し→キャッチコピー→要点→スケジュール案の流れを意識するといいレイアウトになる。
キャッチコピー vs サブ文言のバランス
キャッチコピーで興味を引いたあとに、サブ文言で補足説明を入れる。
「目立つ言葉」+「具体説明で安心感を出す」という組み合わせがベスト。
演説スライド・紙媒体の演出アイディア
演説用にスライド資料を作るなら、アニメーション少なめ・文字少なめ・図やグラフを使う。
紙媒体ならチラシ、ちらし、配布用ミニパンフレットも検討しよう。
手に取られやすいサイズや折り方もポイントになるよ。
SNS利用法:QRコード・動画・写真展開
今どきはSNSを使わない手はない。
ポスターに QR コードを貼って、公約詳細ページへ誘導。
短い動画を撮って「この公約を実行したらこうなる」イメージを見せる。
写真でビフォー/アフターを表現するのも強い手段になる。
「当選後に“公約破り”を回避するための設計法」
当選したらそこからが本番。
公約破りと思われないように、最初から実行性を考え、フォロー体制を整えておこう。
このセクションでは、実際に破られない設計のコツを教えるよ。

実行までのタスク分解・責任者明記
公約を分解して小さなタスクに落とす。
各タスクに期限と担当者を明示すると、実行が現実味を帯びる。
「いつ何を誰がやるか」が見えると、実行率が上がる。
進捗を可視化する報告手段(掲示板・Web)
進捗を見える形でみんなに報告する。
校内掲示板、学校 Web サイト、SNS など。
「今月はここまで進んだ」という報告を定期的にすることで、公約実行を実感してもらえる。
フォローアップ体制(PDCA回す仕組み)
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の流れを回す。
実施後、振り返りをして改善を続けていく。
そうすることで、公約をただ掲げただけで終わらせない強さが出る。
公約未達時の言い訳を作らない準備
予期せぬ事情で未達になることもある。
でも言い訳ばかりだと信頼を失う。
だから、未達になったときの代替案や改善案を事前に考えておく。
「まずはできなかった原因を報告し、そのうえで改案を発表する」スタンスを準備しておくといい。
まとめ
この記事では、「生徒会に立候補したいけど公約が思いつかない」という悩みに対して、公約が出ない原因、発想法、ジャンル別アイデア、実行可能性を担保する設計、公約の見せ方、実例、批判対応、公約破りを防ぐ設計法、などを全部取り上げたよ。
公約は「ただいいことを言う」だけじゃなく、「実行できるか」「伝わるか」「信頼を守るか」が勝負なんだ。
君らしい約束を、学校生活をより良くする活動を、公約という形で形にしてみてほしい。
そして、立候補するなら、公約を掲げた後は「誠実さ」で勝負。
君の学校に、「あの人のおかげで変わったな」と思われるプロジェクトを残してほしいな。

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。
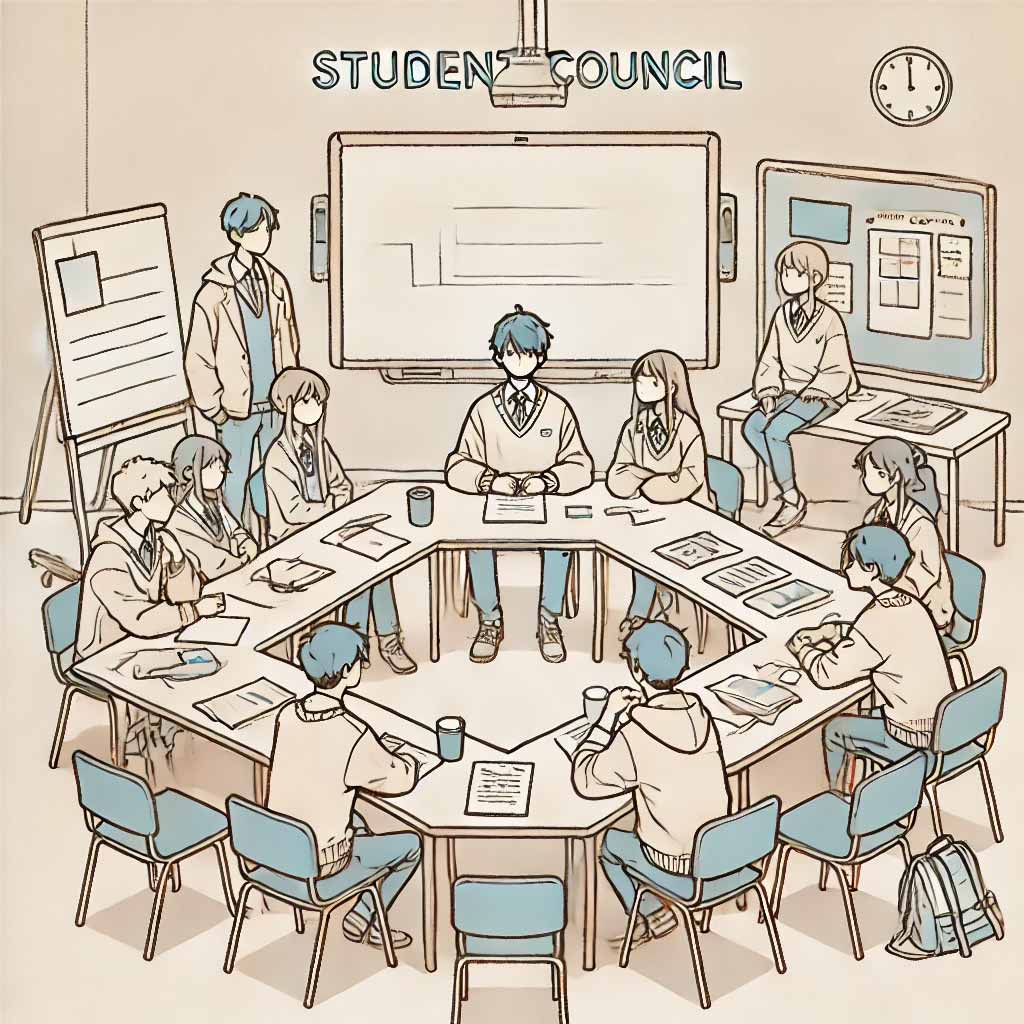
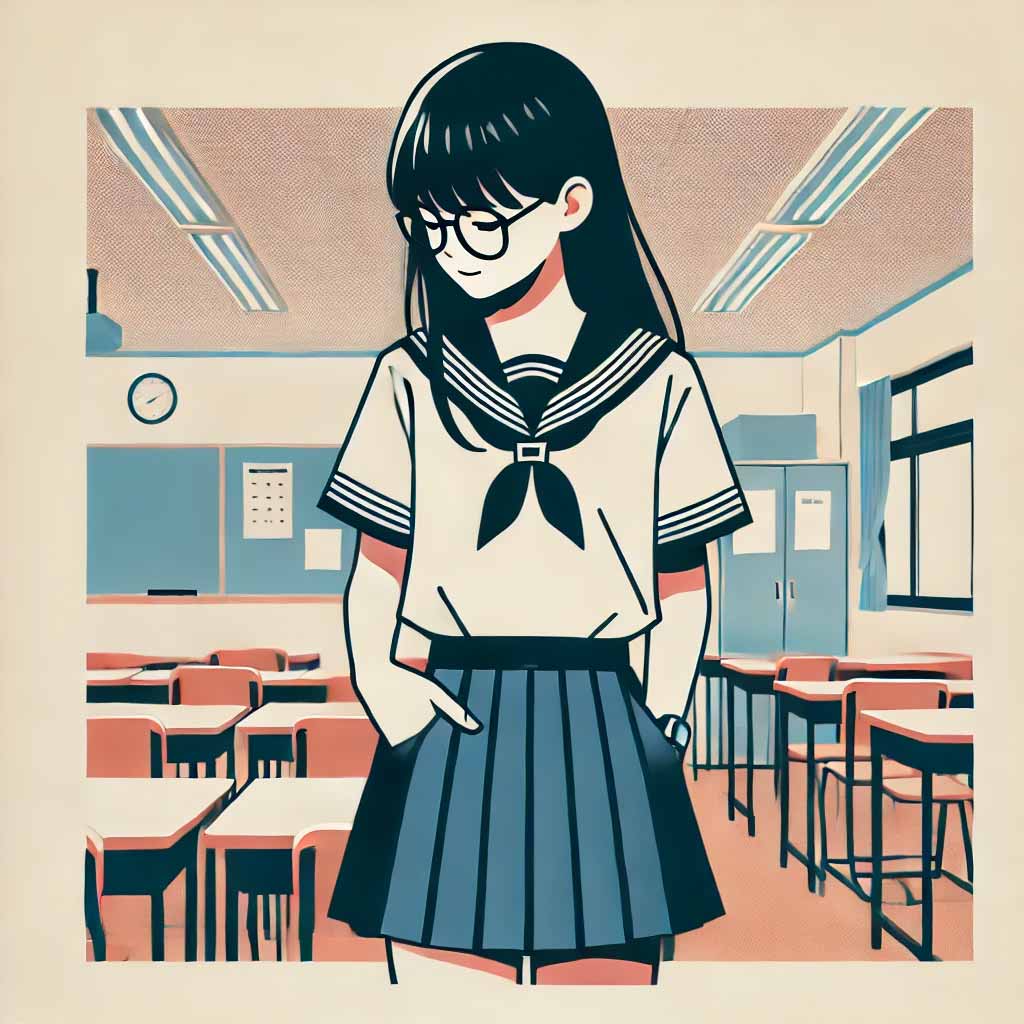





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません