生徒会選挙演説はどうやるの?
生徒会選挙演説の全体像—“当てにいく型”で勝ちにいく
演説は自己紹介、立候補理由、公約、締めの順で一本線にするのが王道だ。
骨組みがぶれると全体がふわふわして伝わらないから、最初に型を決めると安心だよね。
自己紹介では同じ生徒としての目線を見せ、立候補理由では経験に裏づけられた気づきを短く語ると信頼が生まれる。
公約は願望で終わらせず、実現までの段取りと数字を添えると候補としての格が上がるよ。
締めはお願いではなく共犯宣言で、みんなで作る学校だよね、と巻き込み型で終えるのがコツだ。
まずは当てにいく型で、当たり前に当ててから差を広げよう。

まずは骨組み:自己紹介→立候補理由→公約→締めの順で一本線
演説は起承転結より結論ファーストの流れが刺さる。
自分は誰か、なぜ立候補するのか、何を実現するのか、最後にどう一緒に進めるのかを一筆書きで示す。
聞き手は道筋が見えると安心して内容に集中できるんだよね。
骨組みは信頼の土台、まずここを固めよう。
「誰トク?」を明確に:ベネフィットを30秒で言い切る
聴衆は私たちに何の得があるのかを知りたい。
昼休みの活動を広げて参加しやすくする、意見箱をデジタル化して全体の声を拾うなど、学校や生徒に効く効果を短く言い切る。
三十秒で分かるベネフィットは最強のフックだよね。
数字と期限で盛る:公約は“何を・いつまでに・どう測る”
文化祭の新企画を三本、来年度の一学期までに試験導入、参加率40パーセントを目標など、数と期日と指標を置く。
測れる公約は実現の道筋が見えるから、候補の信用が上がるんだ。
評価方法を先に示すことも企画の一部だよね。
ラスト一行の魔法:お願いではなく“共犯宣言”で締める
ご清聴ありがとうございましただけで終わると他人ごとで閉じてしまうよね。
ここから一緒に動こう、私たちで楽しい学校を作ろう、と未来の主語を私から私たちに切り替えよう。
共犯宣言は聞き手を役員や活動の仲間に変える合図になるんだ。

冒頭と締めだけで七割決まる—記憶に残る出だし・刺さる着地
最初の三秒であなた誰問題を解決し、最後の十秒で一票の手を動かす。
冒頭は肩書きより原点エピソードが効くし、締めは行動の合図が効く。
拍手をもらう間と合図もテンプレにしておくと安定する。
出だしと着地が良ければ中盤の小さな揺れは気にならないということもあるよね。
三秒で“あなた誰”:肩書より“立候補の原点エピソード”
部活や委員会での小さな気づきを短く語ると人柄が見える。
例えば図書委員で意見が集まった体験を生徒会の活動に広げたいなど、理由と経験が一本線でつながるんだ。
肩書きだけより強い印象になるよ。
使えるフック集:質問・ギャップ・小道具
暑いよねから入る共感質問、見た目と中身のギャップを見せる一言、安全な文房具などの小道具。
校則に合わせて選び、演説会の空気を軽く温める。
フックは一つで十分、やり過ぎは逆効果だよ。
拍手の取り方:合図・間・お礼のひとことテンプレ
ここで拍手をくださいと明るく言い、半拍の間を入れて、ありがとうで締める。
合図と間は反応をそろえるための技術だ。
恥ずかしがらずにテンプレでいこう。

公約は“願望”じゃなく“計画”—実現性の見せ方講座
願望で終わる公約は絵に描いた餅だ。
予算と権限とルートを押さえ、段取りと指標を置き、反対意見の先回りまで用意して計画に仕上げよう。
実現までの地図がある候補は強いよ。
まったく違う話をするのではなく、学校の全体の流れに沿って進めるのが近道だ。
予算・権限・ルート:実現可否の三点チェック
いくらかかるのか、誰が決められるのか、どの順番で相談するのかを事前に確認する。
学年会や評議会や顧問の先生との連携を前提に置くと現実味が出る。
できることとできないことの線引きが明確になるよね。
進め方の地図:生徒会→評議会→顧問→学校判断の段取り
まず生徒会で企画案、次に評議会で意見集約、顧問の先生と実施方法の調整、学校判断で決定という順。
段取りが見えると実現をイメージできる。
演説中に地図を一言で示すと理解が早いよ。
指標を置く:アンケート、参加率、納期で“見える化”
賛成率、参加率、期日などの目標値を示すと進捗が測れる。
評価のものさしがあると説明がぶれない。
実施後のふりかえりにも使える便利な道具になるよね。
反対意見の先回り:FAQ台本で不安を先に潰す
時間が増えないか、予算は足りるのか、当日の運営は誰がするのかなど、よくある質問を先に答える。
不安を先消しすると合意形成が早い。
演説会でも安心感が伝わるだろう。

声・姿勢・時間配分—“伝わる”を作る実践スキル
声量より抑揚、姿勢は安定、時間配分は設計で決まる。
強弱と間と語尾の切り替えが聞きやすさを生むんだ。
立ち姿と手の位置と目線と呼吸で落ち着きが出る。
九十秒のタイムチャートを作り、原稿からカード、カードからノー原稿へ段階的に練習しよう。
声量より抑揚:強弱・間・語尾三種の切り替え
体育館で大声は反響して疲れるんだよね。
強調は強く、説明は静かに、結論前に半拍の間を置くようにしよう。
語尾はだ、だよね、じゃないを混ぜて単調回避だ。
抑揚の設計が伝わりを決める。
立ち姿の五ポイント:目線・手・足・台の使い方・呼吸
足は肩幅で安定、手は胸の高さで小さく、台には軽く触れる。
目線は前後左右に回し、呼吸はゆっくり深く。
これだけで緊張が落ち着くし、堂々として見えるよね。
九十秒タイムチャート:配分テンプレと練習メニュー
自己紹介十秒、公約四十秒、エピソード二十秒、締め二十秒の配分が基準。
ストップウォッチ練習で体内時計を合わせる。
配分を守ると内容が締まるんだ。
原稿→カード→ノー原稿へ:段階的に手放す練習法
全文原稿で内容を固め、キーワードカードで要点化し、最後はノー原稿で会話のように話す。
段階練習は緊張の負荷を少しずつ上げるから成功率が高い。
自然な語り口に近づくよね。

よくあるNGを秒速で回避—“もったいない”を即修正
抽象語、長文一息、功績の独り占め、語尾のマンネリは四大NGだ。
具体化、句点と改行、共同主語、語尾のバリエで一気に改善できる。
小さな修正が全体の印象を変えるのだ。
抽象語の沼:「学校を良くする」を具体に置き換える表
学校を良くするは意味が広すぎる。
昼休み図書室の開放、意見箱の常設、清掃の分担見直しなど、行動に落とす。
具体は共感の最短距離だ。
長文一息の罠:句点と改行、十五語ルールで息継ぎ
息を止めると聞き手が疲れるし自分も焦る。
十五語前後で区切り、句点で落とし、改行で見やすくする。
呼吸が整うと声も安定するよね。
他人の功績泥棒に見える言い回し→共同主語に直す
私がやったを連発すると独り占めに見える。
私たちで、委員会と一緒に、地域の方と協力してに言い換える。
協働の姿勢は信頼を生むのだ。
同じ語尾連発問題:語尾バリエの即席レシピ
ですます連打は退屈になる。
だ、だよね、かもね、じゃないを混ぜ、体言止めも一つ入れる。
リズムが出て耳に残るよ。

当日、時間を守る“タイムマジック”術
制限時間の遵守は信頼だ。
秒単位のリハ、短めに終える安全マージン、詰め込み抑制、緊急カットの四点で事故を防ぐ。
時間内で言い切る候補は強いよね。
秒単位で測るリハーサル法:ストップウォッチ必須
本番同様に計測し、冒頭と締めの所要秒数をメモする。
実測でズレを把握し、言い回しを微調整する。
体内時計の精度が上がるんだ。
予定より短く終える“安全マージン”の黄金比
制限より十秒から十五秒短く終える設計にする。
拍手や笑いで時間が増えても収まる。
余裕があると落ち着きが出るよね。
詰め込みすぎ防止チェック:削る勇気が勝負を分ける
言いたいことは多いが、全部は無理だ。
主目的に関係ない枝葉は前日カットしよう。
削る勇気が集中と伝達力を生むよ。
タイムオーバー時の緊急カット技
最後の段落を丸ごと飛ばす、エピソードを一つ省く、数字は後日掲示すると言って締める。
事前にカット位置を決めておけば焦らない。
被害最小で次へつないでいこう。

小道具&視覚資料で“目と心”に訴える
言葉に視覚を足すと理解が速い。
校則の範囲で小道具を選び、掲示は色と文字と配置を絞り、図解は一枚一メッセージにする。
扱いと片付けまで段取りに入れよう。
校則OKな小道具アイデア集
部の道具、学校名タオル、掲示見本など、安全で日常的な物だけにする。
主役は言葉、小道具は補助だ。
目立てば良いではないよね。
見やすい掲示資料の色・文字サイズ・配置
色は三色以内、文字は大きく、中央に情報を集める。
遠くからでも読めることが正義だね。
情報は削って要点だけにする。
一瞬で伝わる図解の使い方
円グラフや矢印の流れ図で現状と改善を示そう。
図解は一枚一テーマに絞るのがコツだ。
小道具の扱いと片付けの段取り
使う位置と戻す位置を決め、片付け役を一人頼む。
舞台の所作は印象に直結するからね。
スマートな撤収は活動の信頼だよね。

練習の質を劇上げする“反復メタループ”
反復は最強の先生だ。
録音して聞き返し、修正してまた録るを繰り返そう。
鏡とスマホを使い分け、一日五分を複数回回す。
模擬本番で緊張を再現するんだ。
録音→聞き返し→修正のループ回数目安
最低三周、できれば五周。
一周ごとに一個だけ直すと続けやすい。
自分の癖の自覚が最速の上達だよ。
鏡とスマホカメラの使い分け
鏡は姿勢と手、スマホは全体の流れと目線の軌道を確認する。
別視点で見ると客観的になれるよね。
改善点が具体になったらあとは直すだけ。
一日五分×複数回の分割練習が効果的
長時間より回数が記憶を定着させる。
朝一、昼休み、放課後で三回。
短く濃くを積むのがコツだよ。
緊張感を再現する模擬本番法
友達や先生の前で本番同様に立ち、合図と間も入れて通す。
失敗しても笑ってリスタート、成功体験を最後に作る。
本番で勇気が出るよね。

ライバル分析で演説差別化を図る
勝ち筋は自分だけ見ていても見えない。
動画やメモが残っているなら、過去の当選演説を分析し、同時期の候補の傾向を押さえ、飽きポイントを回避し、言い回しの被りを避けよう。
差別化は準備の産物だよ。
過去の当選演説から強みと弱みを抽出
良かった点は三つ、弱かった点は一つに絞ってメモする。
強みの継承と弱みの回避で完成度が上がっていくよ。
先人の知恵は資産だよね。
同じ公約をどう差別化するか
内容が似てしまうなら方法と数字で分ける。
期限、対象、評価の仕方で個性を付ける。
同じでも違って聞こえるのが技ってもんだ。
聴衆の飽きポイントを先に把握
長い説明、専門語、数字の連打は眠くなる。
そこはカットか図解に置き換える。
退屈の芽は事前に摘むのが賢いよね。
他候補の口癖やパターンを逆手に取る
ありがちな言い回しを避け、言葉を新鮮にする。
同じ語尾が続くなら自分は変化をつける。
小さな違いが記憶を作るのだ。

会場の雰囲気を読む“アドリブ力”
台本は基準、現場は生き物。
笑いが出たら半歩広げ、反応が薄ければ一言で立て直し、拾ったリアクションを返してから本題へ戻る。
機材トラブルも落ち着いて対処すれば評価は落ちない。
むしろ上がることもあるよ。
笑いが取れたら少し膨らませるタイミング
追い一文だけ足して温度を上げる。
時間を見てすぐ本線へ戻る。
欲張らないのがプロの所作だ。
反応が薄いときの立て直しフレーズ
少し難しかったかなや、ここだけ覚えてで空気を軽くする。
こういった自虐の一言もけっこう効く。
焦らず笑って再始動だ。
リアクションを拾って自分の流れに戻す技
今のうなずきがヒントだねと拾い、すぐに要点へ接続する。
会場と対話している印象が生まれるんだ。
信頼が積み上がっていくよ。
急な予定変更や機材トラブルへの即応
マイクが死んだら声量を上げ、カードを見て簡略版に切り替える。
段取り変更は落ち着いて一言説明する。
危機対応は実力の見せ場だよね。

選挙後のフォローで“信頼”を積む
当選しても落選しても終わりではない。
挨拶回り、初仕事、非支持層への礼節、掲示やSNSの報告で信頼を積む。
生徒会の役員は活動の継続で評価される。
次の挑戦の土台にもなるよね。
落選でも印象を上げる挨拶回り
投票ありがとう、学んだことを次に生かすと笑顔で伝える。
悔しさを前進の燃料にする姿は尊敬を呼ぶ。
次回の追い風になるのだ。
当選後の初仕事で公約の一歩を見せる
一週以内に小さな実行を出す。
意見箱の設置告知、アンケートの準備、企画の素案掲示など、目に見える一歩が信頼を生むよ。
動く人は強いよね。
投票してくれなかった層への接し方
選挙後は全員の役員だと示す。
反対意見にも礼を尽くし、説明と理解の橋を作ろう。
分断を作らない姿勢が活動をスムーズに進めるポイントになるよ。
SNSや掲示板での報告と感謝文例
短く感謝、次の行動、参加の呼びかけの三点を載せるようにしよう。
言葉は明るく丁寧に、個人情報と肖像の扱いは校則に従ってね。
報告は信頼の窓口だよね。

まとめ
生徒会選挙の演説は骨組みと生徒たちへのメリットで耳をつかみ、計画で信用を取り、声と姿勢と時間で伝達を整えよう。
生徒会選挙では、当たり前を当たり前にやる人が強いんだ。
キミの一歩を引き出す演説へ向かって頑張ろう!
※合わせて読みたい「生徒会の役割 各役員は何をするの?」

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。
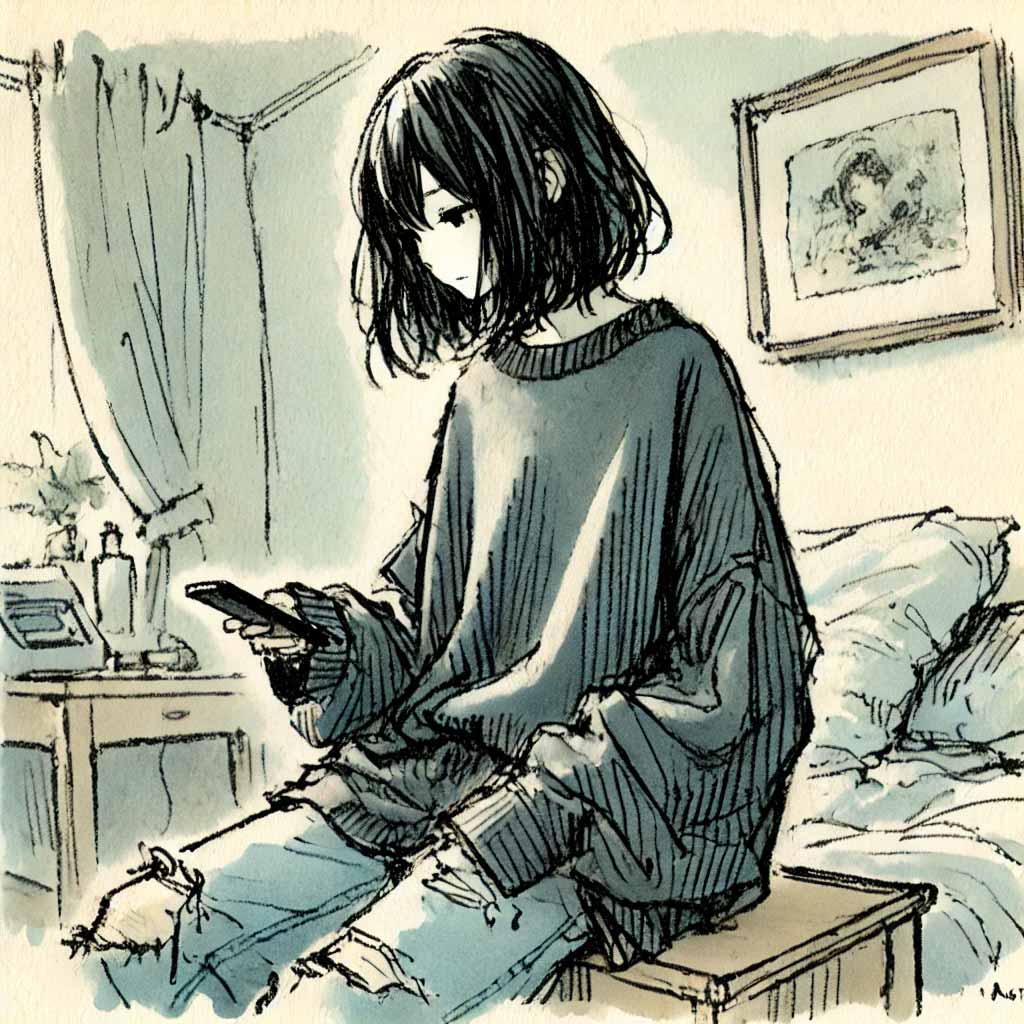






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません