世代による言葉の違い一覧 ママの言葉がわからないわけ
🔷 結論:
授業中や学校生活で交わされる言葉には、世代によって大きな違いがあるよね。
🔷 結論:
昭和の先生が使っていた表現が今の若い世代には通じないことも多いんだ。
🌟 重要ポイント(まずここを押さえる!)
- ● 理由:
世代ごとのズレは、意味を理解できないとちょっとした混乱を生むこともある。 - ● 具体例:
たとえば連絡の仕方や授業で使う道具。 - ● 今日からできる対策:
今回は、そんな学校や授業にまつわる「ズレ言葉」を紹介していくよ。
📘 この先を読むメリット
そのズレを笑って楽しむのか、誤解として問題にするのかは、相手との関係や状況次第。
まず、キミが聞いてもわからないかもしれない昔の言葉と現代での言い換えを時代ごとに一覧にしたよ。
昭和の言葉 → 今の言い換え(タップで開く)
| 昭和の言葉 | 今の言い換え | ひとことメモ(場面) |
|---|---|---|
| 黒板をけす | (電子黒板なら)画面を消す/消去する | 「物理的に消す」→「ボタンで消す」 |
| 提出箱 | 提出フォーム/オンライン提出 | 箱に入れる→送信する |
| 朝礼/終礼 | ホームルーム(HR)/ショートHR(SHR) | 学校用語の略語化 |
| 連絡網 | クラスLINE/学校アプリ/一斉連絡 | 電話で回す→通知で届く |
| 学級委員 | 学級係(学校による)/クラス委員 | 呼び方のゆれが出やすい |
| 放課後残る | 居残り(学校による)/放課後に残る | 言い方の好みの差 |
| 校内放送 | 校内放送/配信(校内放送アプリがある場合) | 学校によって現役 |
| 予鈴/本鈴 | チャイム/開始ベル | 時間管理ワード |
| アベック | カップル/恋人同士 | 恋愛の呼び名 |
| 本命 | 本命(現役)/ガチ恋(文脈次第) | 今も使うけど意味が広がる |
| 不良 | ヤンチャ系(やわらかく言うなら) | 強い言い方→マイルド化 |
| 優等生 | まじめタイプ/しっかり者 | ラベル感を弱める |
| 落ちこぼれ | 苦手がある/つまずきやすい | 今は避けたい表現 |
| ファミコン | 家庭用ゲーム機(まとめて言う) | 機種名が世代で変わる |
| カセット | テープ/(ゲームなら)ソフト | 用途で言い換えが変わる |
| ビデオ | 動画/映像/配信 | 「返す」が消えた世界 |
| レコード | 音源/アルバム(配信) | 媒体からサービスへ |
| テープ | 音声データ/録音データ | 巻き戻しが通じない |
| チャンネルを回す | チャンネル変える/切り替える | 回す動作が消えた |
| バッチグー | いいね/最高/よき | 褒め言葉の世代差 |
| ナウい | 今っぽい/トレンド | 時代感ワード |
| イケてる | かっこいい/いい感じ | 今も通じるが温度は変わる |
| こわい(=疲れた) | 疲れた/しんどい | 方言寄り。誤解が起きやすい |
| 了解だ | 了解/承知/OK(場に合わせる) | 丁寧さの調整が必要 |
平成の言葉 → 今の言い換え(タップで開く)
| 平成の言葉 | 今の言い換え | ひとことメモ(場面) |
|---|---|---|
| SHR | ホームルーム(HR)/SHR(学校によって現役) | 略語がそのまま残る学校も多い |
| プリント配布 | 資料配布/PDF配布/共有 | 紙→データ |
| 写メ | 写真(送る)/画像(送る) | メールが前提の言葉だった |
| 提出物 | 提出課題/提出データ | 媒体で呼び方が変化 |
| 居残り | 放課後に残る/補習(文脈次第) | 罰っぽく聞こえることも |
| カップル | カップル(現役)/付き合ってる2人 | 今も強い汎用語 |
| 告る | 告白する/気持ちを伝える | 大人の前では言い換えが安全 |
| リア充 | 楽しそう/生活が充実してる | 皮肉に聞こえることもある |
| オタク | 好きなものに詳しい人/趣味が深い | 相手によっては配慮が必要 |
| にわか | 最近好きになった/ライト層 | 悪く聞こえやすい |
| ゲームボーイ | 携帯ゲーム機/ゲーム機 | 固有名詞→総称へ |
| プレステ | ゲーム機(家庭用) | 世代で代表機種が変わる |
| MD | プレイリスト/音源データ | 録音文化→配信文化 |
| ガラケー | 携帯(昔の)/折りたたみ携帯 | スマホ前提の会話だと補足がいる |
| メールする | 送る/メッセする/連絡する | 手段が増えて動詞が抽象化 |
| w(笑) | (軽く)笑/(丁寧に)笑ってしまった | 相手を笑うに見えない配慮 |
| イミフ | 意味がよく分からない/意図がつかめない | 強く言うと刺さるので調整 |
| ググる | 調べる/検索する | サービス名依存を外す |
| コスパ | 費用対効果/お得 | 目上には言い換えると安全 |
| 了解しました | 承知しました(丁寧)/了解です(柔らか) | 相手・場面で選ぶ |
令和の言葉 → 今の言い換え(先生・親の前でも安全)(タップで開く)
| 令和の言葉 | 今の言い換え(安全表現) | ひとことメモ(場面) |
|---|---|---|
| Google Classroom | 学習アプリ/オンライン提出システム | 固有名詞→一般名詞にすると通じやすい |
| データ提出 | オンラインで提出/提出を送信 | 「出す」より具体化 |
| 既読スルー | 読んだまま返信がない/返事がまだ | 責め口調にならない言い換えが大事 |
| スタンプで返す | 短く返事する/リアクションで返す | 「軽い」印象を避けたい場面も |
| 欠席連絡アプリ | 欠席連絡のシステム/学校連絡アプリ | 学校ごとの名称差を吸収 |
| 推し | 好きな人(もの)/応援している存在 | 大人には補足があると通じる |
| ガチ勢 | 本気の人/真剣にやっている人 | ラベル感を弱める |
| にわか勢 | 最近好きになった人/ライト層 | 相手を下げない言い方に |
| 陰キャ/陽キャ | 内向的/社交的(ざっくりなら) | 決めつけに見えやすいので注意 |
| 距離感バグる | 距離感がつかめない/近すぎる・遠すぎる | 伝えるなら具体に寄せる |
| スイッチ | ゲーム機(家庭用) | 機種名を総称に |
| サブスク | 定額サービス/月額の配信サービス | 説明語を足すと世代を超える |
| 配信 | ネットで見る/動画サービスで見る | テレビ前提から外す |
| ストーリーに上げる | SNSに投稿する(24時間で消える投稿) | 大人には補足が効く |
| 自撮り | 自分の写真を撮る | 言い換えが簡単で強い |
| 草 | 思わず笑ってしまった/ちょっと笑った | 相手を笑うに見えない形へ |
| よき | いいね/いいと思う | フラットに言うと通じる |
| 神 | 最高/すごい/助かった | 場面に合わせて具体化 |
| エモい | 胸にしみた/感動した/雰囲気がいい | 何がエモいかを足すと完璧 |
| タイパ | 時間効率/短時間でできる | 目上には説明語が強い |
| り(了解) | 了解です/承知しました | 短すぎると軽く見える |
学校・授業シーンでズレる言葉辞典
「黒板をけす」から「電子黒板で消す」へ──道具が変わると動詞も変わる
昭和の学校と言えばチョークと黒板が当たり前だったよね。
先生が「黒板をけす」と言ったら黒板消しでゴシゴシする姿が目に浮かぶ。
ところが今は電子黒板やホワイトボードが主流。
タッチパネルでワンタッチ消去する世代には「けす」という動作が物理的な行動に結びつかないんだ。
若者にとってはボタンひとつ。
先生やベテラン社員が「黒板けして」と言っても、若い世代は「どこ触ればいいの?」って戸惑うケースもある。
生活道具の変化はことばの存在そのものを変えるんだ。
「連絡網」vs「クラスLINE」──伝達手段と敬語の温度差
昭和から平成にかけては電話の連絡網が大定番。
家にかけて「次の人に伝えてね」という社会経験を積んだ世代も多い。
当時は大人への敬語も練習になった。
ところが今はLINEグループや学校指定アプリが主役。
相手の年齢や立場に関わらずスタンプでOKなんだよね。
異世代間の会話では「そんな軽い表現でいいの?」とギャップが生まれることもあるけどね。
先生や保護者からすると「流行語みたいな返信は失礼」と感じる場合もある。
だからこそ、世代の違いを理解して調整する力が必要になるんだ。
「提出箱」vs「Google Classroom」──“締切”の体感差
昔は教室の後ろに課題の提出箱が置かれていて、期限内に自分で放り込むのが普通だった。
昭和的な「提出する」という行動には物理的な経験が伴っていたんだ。
一方、今の生徒たちはGoogle Classroomなどでデータを送信。
時間が0時を回った瞬間に「遅延」と表示されるシステムにビビることもあるよね。
先生側も昔は「まあ明日でいいか」と融通を利かせていたけど、デジタルは一方的に結果を突き付けてくる。
行動とワードの意味が変化したいい例だよね。
「朝礼・終礼」vs「SHR」──略語が分断を生むミニ辞典
かつては「朝礼」「終礼」が定番ワードだったけど、今の中学校では「SHR(ショートホームルーム)」が一般的。
ゆとり世代以降はこの言い方にすっかり慣れている。
でもベテランの先生や保護者が「朝礼」と口にしても若者はピンとこない場合がある。
異世代のセリフの中にあるちょっとした違いが「何それ?」となるのはおもしろい現象だよね。
こういう世代間の言葉のギャップは会話のズレを笑いに変えるきっかけになることも多いんだ。
※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」
SNS・チャットの略語“翻訳”
SNSやチャットでは、言葉の流行や使い方の変化が一番激しい場所だよね。
昭和世代がメールや手紙で伝えていたことを、今の若者はスタンプや一文字で表現してしまう。
社会の変化とあわせて、人々の発言のスタイルも変化してきた。
相手によっては失礼に感じられるケースもあるから、異世代での会話では“翻訳”が必要になるんだ。

「りょ/了解」──OKの強さとTPOを調整する
平成のメール文化では「了解しました」が当たり前。
職場でも家庭でも丁寧に伝えることが求められていたんだよね。
ところがSNS世代は「りょ」の一言で済ませることも多い。
若い世代にとっては便利な流行語でも、ビジネスの場では「軽すぎる」と思われることがある。
発言の意味は同じでも、相手や場面によっては誤解される可能性が高い。
使い方を調整して、仕事や学校のシーンではきちんと「了解」や「承知」を選んだ方がいいんだろうね。
「イミフ」vs「意味不明」──軽さ・距離感の違い
「意味不明」という言葉は、昭和や平成の時点から存在していた表現。
でも今の中学生は「イミフ」という省略を好んで使う。
短くすることで会話のテンポも軽快になるんだよね。
一方で年齢が上の世代には「なんでそんな変な読み方をするの?」と不思議に感じる人もいる。
表現の軽さは世代間ギャップを生みやすい。
お互いの価値観を理解すれば、単なる違いとして楽しめるのかもしれない。
「タイパ/コスパ」──効率ワードが会話を変える
コストパフォーマンス=コスパはすっかり定着したけど、令和の若者は「タイパ(タイムパフォーマンス)」をよく使うよね。
時間効率を重視する傾向が強い世代らしい。
大人の社会や仕事でも「時間をどう使うか」が課題になっているから、自然とこうした新しいワードが人気になるんだ。
ベテラン世代は「そんな言葉知らない」と思うけど、若者にとっては当たり前の会話。
異世代間でのやりとりでは「それどういう意味?」と聞ける勇気も必要だね。
「草/w」──笑いの表記史と“相手を笑う”にならない配慮
インターネット黎明期には「w」が笑いのマークだった。
当時のユーザーは「www」で爆笑を表現していたんだ。
今は「草」が主流。
日本語の読み方として「笑う」が草に似ているからという由来もある。
流行語は変わっても、笑いを表す存在はずっと続いているんだね。
でも「草」や「w」は相手をバカにしているように見えるケースもあるから注意が必要。
使い方を誤ると、会話がギャップだらけになってしまうよ。
恋愛・友情ワードの世代差
恋愛や友情を語るワードも、世代によって大きく変化してきたんだ。
日本の若者文化を振り返ると、時代ごとに流行語や呼び方が変わっているのがよくわかるよ。
今の中学生が何気なく使っている言葉も、数年後には死語扱いされる可能性もあるんだ。
恋愛や友情という生活の中で大切なテーマだからこそ、世代ごとの違いを知っておくと会話がもっと楽しくなるよ。

「アベック→カップル→リア充」──同じ意味でも見える景色が違う
昭和時代、恋人同士を「アベック」と呼んでいた。
フランス語が由来でおしゃれな響きがあったんだ。
当時の若い世代は憧れのワードとして使っていた。
でも平成になると「カップル」という表現が主流になり、リアリティを帯びた。
さらに令和では「リア充」が流行。
生活の様子や価値観を一言で表す便利な流行語として人気になった。
同じ恋愛でも時代ごとに言葉が違うのは、人々の社会経験や文化の傾向が変化しているからだよね。
「告白する→告る→DMで行く」──告白動線の変遷
恋愛のセリフも進化しているんだ。
昭和や平成では「告白する」が王道だった。
ドラマや漫画の影響もあって定番だったよね。
平成後半になると「告る」という略語が広がった。
より軽いニュアンスで、友達に話すときの会話に合っていたんだ。
令和になるとSNSが中心。
告白もDM(ダイレクトメッセージ)で済ませるケースもあるんだ。
恋愛という大事な物事の表現が変化したのは、生活やコミュニケーションの方法が変わったからじゃないかな。
「本命/推し」──恋と推し活の線引き
昭和の恋愛では「本命」という言葉がよく使われた。
平成でもバレンタインの文化と一緒に広まっていたんだ。
でも今の若者は「推し」というワードを多用する。
アイドルやアニメキャラに限らず、友達や有名人に対しても「推し」と呼ぶ。
恋と推し活は似ているようで少し違う。
表現の違いを理解しないと世代間で意味がズレるんだよね。
「推し」という存在は単なる人気だけじゃなく、価値観や経験を共有するシンボルにもなっているんだ。
「にわか/ガチ勢」──温度差ラベルの扱い方
趣味や友情を語るときによく出るのが「にわか」と「ガチ勢」。
昭和や平成にはあまりなかった区分けだ。
若い世代は「どれくらい本気か」をラベルで示したがるんだよね。
一方で、ベテラン世代からすると「そんな分け方必要?」と疑問に思うこともある。
世代間での使い方を間違えると相手に失礼になる可能性もあるよ。
ワードの違いは存在そのものよりも、どういう価値観の中で使われているかを理解することが大切なんだ。
遊び・趣味・デバイスで変わる言葉
遊びや趣味に関する言葉も、世代ごとに大きく変化してきたよ。
昔は存在していたけど今は死語になったものもあるし、逆に今の若者にとっては当たり前だけど、昭和世代には意味がわからない流行語もあるんだ。
生活の様子や行動の仕方が違えば、言葉も自然に変化する。
日本の文化や技術の進歩が、世代ごとの言葉の違いを生み出してきたんだろうね。

「ファミコン→スイッチ」──ゲーム世代で違う会話の単位
昭和や平成初期の若者にとって「ファミコン」は遊びの中心だった。
学校の先生が「ゲームばかりやって」と言うときは、この存在を指していたんだよね。
でも今の若い世代にとっては「スイッチ」が定番。
家庭用ゲーム機のワードが変わるだけで、会話の意味が全然通じなくなるんだ。
ファミコン世代の親が「ゲームカセット」と言っても、子どもは「ソフトのこと?」と首をかしげる。
世代間の違いを知っていれば、相手の言いたいことを理解できるようになるんだ。
「写メ→自撮り→ストーリー」──記録のしかたの言い換え
平成の頃には「写メを送る」が流行語だった。
携帯電話で撮った写真をメールすることが生活の一部だったんだ。
当時はそれだけで新鮮な行動だったよね。
でも今は「自撮り」や「ストーリーに上げる」が自然な使い方。
SNSの発展とともに、表現やセリフがどんどん変化してきたんだ。
異世代が一緒に会話をすると「写メって何?」とか「ストーリーってどの意味?」と疑問が生まれる。
読み方も違えば、価値観の差も見えてくる面白いケースだよね。
「MD・CD→サブスク」──“買う・借りる”から“聴き放題”へ
平成には「CDを買う」とか「MDに録音する」という文化があった。
これは当時の人気の行動であり、流行語にもなっていたんだよね。
でも今は「サブスク」が当たり前。
若者にとって音楽は買うものではなく、存在そのものが聴き放題のサービスに変わったんだ。
当時の世代からすると「月額で音楽が全部聴けるなんて信じられない」と驚くこともある。
時代によって表現が変わるのは、社会の変化と技術進歩の証拠だよ。
「レンタルビデオ→配信」──“返却期限”が消えた世界の用語
昭和後期から平成にかけては、レンタルビデオ店が若者の生活の定番だった。
友達と借りてきて、返却期限を気にするのが当たり前の経験だったんだ。
ビジネスとしてもレンタル業は大きな存在だったよね。
でも今の世代は配信サービスが中心。
「Netflixで見る」「アマプラで観た」という表現が自然に会話に出てくる。
返却という課題が消え、言葉も行動も変わった。
世代間で「ビデオ返した?」というセリフを使っても、若者には伝わらないんだ。
家庭・職場に潜む“おじ語/若者語”の橋わたし
家庭や職場では世代間の言葉の違いが特に目立つよね。
おじ語と呼ばれる古い表現がまだ残っている一方で、若者語は次々と生まれてくる。
異世代での会話では誤解が起きやすいけど、その違いを笑いに変えられれば人間関係もスムーズになる。
社員同士や親子間でのやりとりに役立つ言葉の橋わたしを見ていこう。

「バッチグー」⇔「よき」──褒め言葉の時代差
昭和や平成の世代にとって「バッチグー」は人気の褒め言葉だった。
当時は明るいセリフとして流行していたんだ。
でも今の若い世代は「よき」とか「神」という表現を使う。
意味は同じでも、響きやテンションが全然違うんだよね。
世代間で「バッチグー」と言われても、相手が若者ならポカンとする可能性大。
逆に「よき」と言われてもベテラン社員には理解できないこともある。
「なるはや」⇔「至急」──急ぎの強度を明示する
仕事の現場でよく使われる「なるはや」は平成に生まれたビジネス用語。
意味は「なるべく早く」だけど、強制力は弱いんだよね。
一方で「至急」は昭和世代からある硬い表現。
相手の発言をどう受け取るかは年齢や社会経験によって違うんだ。
同じ課題を伝えるにしても「なるはやで」と「至急で」ではニュアンスが変わる。
理解のギャップを埋めることが職場の会話をスムーズにするコツになるんだ。
「アポイント/アポ」⇔「予定入れる」──外来語の距離感
昭和のビジネス社会では「アポイント」という外来語が使われていた。
その後、平成の若者は「アポ」と略すようになった。
そして令和世代は「予定入れる?」というカジュアルな表現を好む。
ビジネスか日常かによって選ぶワードが違うんだよね。
世代間でのやりとりでは、相手に合わせて呼び方を変える柔軟さが必要になるよ。
「承知/了解/り」──承諾の丁寧さスライダー
「承知しました」は最も丁寧な承諾表現。
昭和や平成の職場で定番だったよね。
「了解しました」は少し柔らかいニュアンス。
さらに若者は「り」だけで済ませることもある。
発言の短縮が進むと、相手がどう受け止めるかが課題になる。
同じ意味でも、どの言葉を使うかで相手の理解は大きく変わるんだ。
学校での“禁止ワード”をTPO翻訳(先生・親の前バージョン)
学校や家庭で若者が使う流行語の中には、大人の前で使うとトラブルになるものもあるよね。
同じ意味でも、先生や保護者の前での表現は変える必要がある。
異世代とのコミュニケーションで大切なのは、相手に応じた表現選び。
会話の中で必要な翻訳を覚えておくと、誤解や衝突を減らせるんだ。

「草」は「思わず笑ってしまった」に変換
若者は「笑った」を「草」と表現するけど、先生や年配の人には意味が通じない。
さらに、草を連発すると「相手をバカにしているの?」と誤解されることもあるんだ。
だから大人の前では「思わず笑ってしまった」と丁寧に言うのが安全。
表現の使い分けは社会に出ても役立つスキルになるよね。
「エモい」は「胸にしみた/感動した」に変換
「エモい」は若い世代に人気の流行語だけど、昭和世代の先生や親には意味が伝わらないことが多い。
感情の動きを表す便利な言葉なんだけど、相手によっては「意味不明」と感じるケースもあるんだ。
そんなときは「胸にしみた」とか「感動した」に翻訳すれば、相手にちゃんと伝わる。
異世代との会話では意味を正しく届けることが大事なんだよ。
「キモい」は“事実+感情”で丁寧に言い換え
「キモい」は軽いノリで使いやすいけど、先生や親に聞かれると強い拒否表現に取られる可能性がある。
相手を傷つけやすいワードでもあるよね。
だから「こういう理由でちょっと苦手」とか「雰囲気が怖い」と説明を加えると安心される。
若い世代にとっては当たり前の表現でも、大人の世界では誤解を招く存在になるんだ。
「ガチ」は「本気で/全力で」に置き換え
「ガチ」は若者語の代表ワードだよね。
友達との会話では自然に使えるけど、先生や保護者の前では「本気で」や「全力で」に言い換えるといい。
意味の違いを理解しておかないと、相手に伝わらないこともある。
社会人になってからも同じで、ビジネスメールに「ガチでお願いします」と書いたら絶対に誤解されるだろうね。
方言か世代差か? を見分けるコツ
世代による言葉の違いと方言の違いは、けっこう似ている部分があるんだ。
相手が別の地域の人なのか、ただ年齢が違うだけなのかで、会話の解釈が変わってしまうケースもある。
昭和世代が普通に使っていたワードを、令和世代が方言だと思い込むことだってあるんだよね。
生活や社会の中で使い方を観察して、意味を取り違えないことが大切になる。

「机をつる=机を運ぶ」──地域差の典型
関西の学校では「机をつる」という表現が一般的。
でも東京の若い世代が聞いたら「釣る? 魚?」と意味がわからなくなる。
これは世代差じゃなくて方言のケースだね。
先生や職場の社員が何気なく使うと誤解が起きやすい。
だから全国で暮らす人々との会話では「机を運ぶ」と言い換えるのが安全。
異世代でも異地域でも、意味を共有する工夫が必要だよ。
「なおす=片づける」──“修理”と誤解されがち
西日本の多くでは「なおす=片づける」という意味がある。
当時の人々にとっては自然な表現だったんだ。
でも東京の若者にとって「なおす」は「修理する」の意味が強い。
だから「机をなおして」と先生に言われて「壊れてないけど?」と混乱することもある。
世代間ギャップよりも地域差の方が大きい場合もあるんだよね。
「こわい=疲れた(方言)」──感情語のズレ
東北地方などでは「体がこわい」と言えば「疲れた」という意味。
当時からある地域限定の使い方だけど、若い世代には伝わらないことが多い。
「怖い」と同じ発音だから余計に誤解を招くんだ。
方言か世代差かを見分けるときは、状況や相手の年齢、地域を考えて判断する必要があるよね。
「ほかす=捨てる」──まずは辞書より“地域の人”に聞く
関西弁では「ほかす=捨てる」という意味がある。
世代に関係なく地域で受け継がれてきた表現だ。
でも標準語しか知らない若い世代が聞くと「ほかす? ほっとく?」と理解できない。
こういうときは辞書だけに頼らず、地域の人に直接意味を聞くのが一番。
言葉は存在そのものが地域の経験や価値観に根ざしているからだ。

まとめ
世代による言葉の違いは、ただの死語リストや流行語紹介にとどまらないよ。
学校や職場、家庭やSNSなど、生活のさまざまな場面で意味や使い方がズレてしまうケースがあるんだ。
そのズレを笑って楽しむのか、誤解として問題にするのかは、相手との関係や状況次第。
会話にユーモアを添えれば、世代の違いはむしろ話題のタネになるんだ。
異世代の人々と話すときに「これって意味わかる?」と聞いてみるのも、楽しいコミュニケーションのひとつになるんじゃないかな。
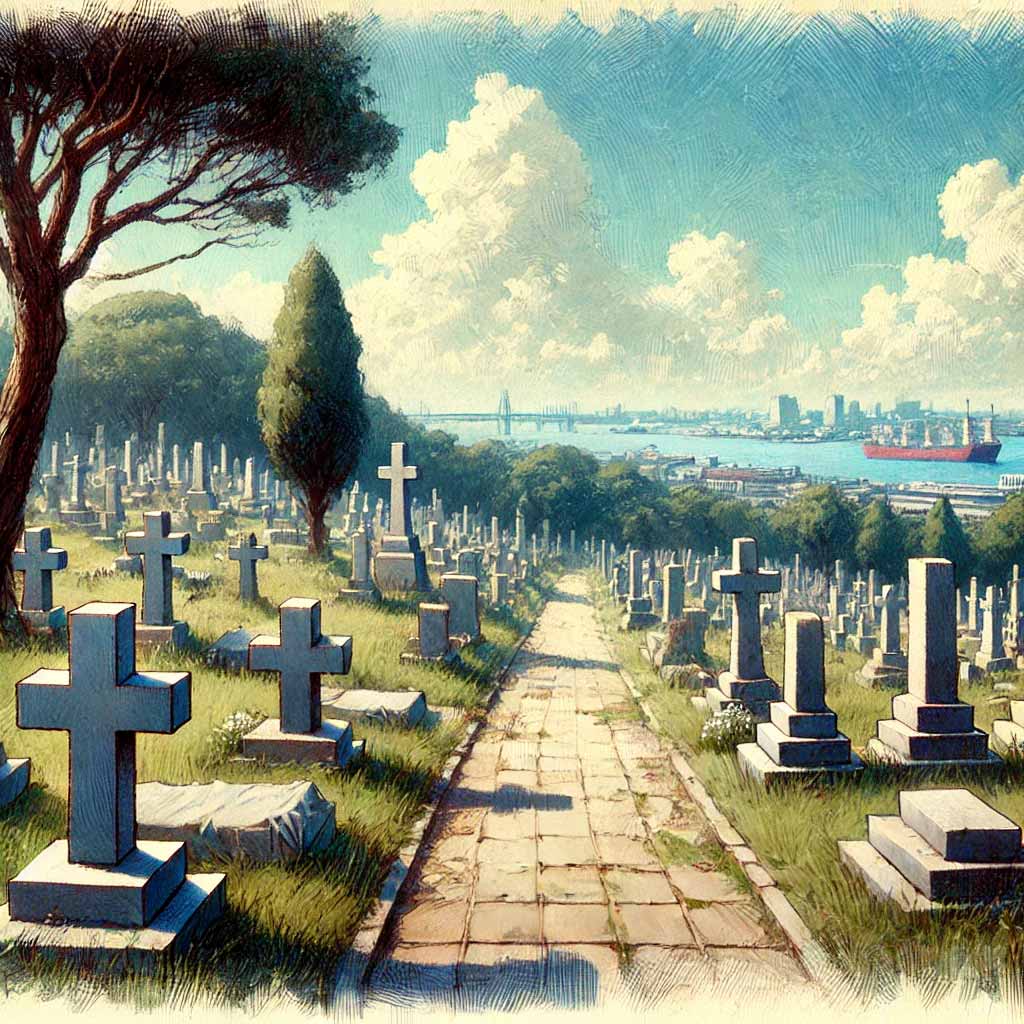
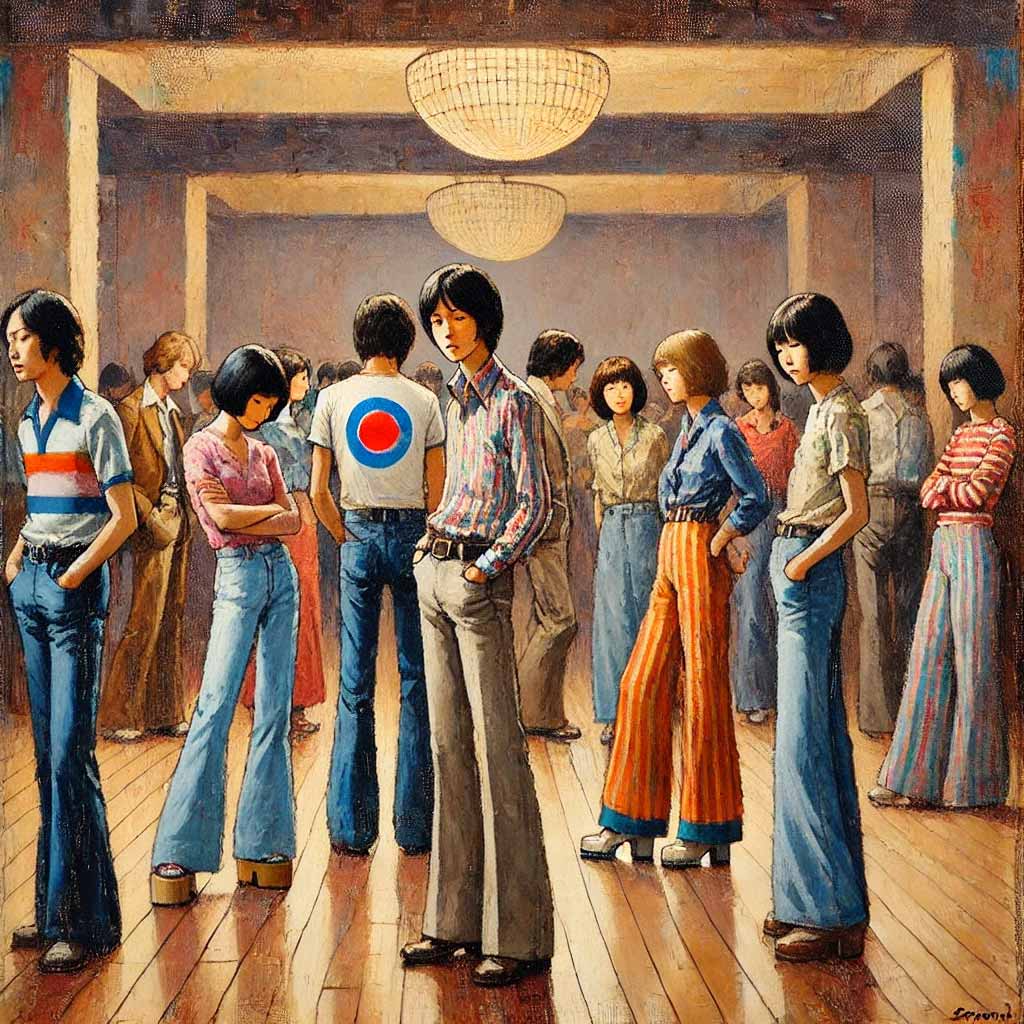





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません