昔の言い方 親世代が使ってた死語と今どき言葉の違い
昔の言い方 5つのQ&A
💬 Q1 昔の言い方ってどの範囲?江戸まで行くの?
江戸時代みたいな古文は今回は外す。テレビや漫画、学校や部活動の空気から生まれた表現を中心に見るから、中学生でも意味がつかみやすいんだ。
💬 Q2 昭和の代表ワードって何がある?
💬 Q3 平成の口グセやネット前夜語も知りたい
バラエティ発の決め台詞は「アウト〜!」が鉄板。強調は「チョー○○」、語尾は「〜じゃね?」が流行ったんだ。初期ネット語なら「キリ番」「厨房」みたいな掲示板由来の表現があるよ。
💬 Q4 今どきの言葉に置き換えるなら?
💬 Q5 うまい使い方と注意点は?
先生への提出物や公的文書では使わない、ここはきっちり線引きしよう。 親や祖父母の言葉はリスペクトして聞き取り、ネタ化はやさしく。方言や地域差もあるから、クラスの空気を読みつつ場面に合わせて使うのがコツだよね。
昔の言い方=「親世代のレトロ語」って何者?範囲を先に決めとこ
「昔の言い方」ここでは、身近でリアルな、親や先生が学生だったころに普通に使っていた言葉のこと。
昭和や平成初期に流行した言葉は、今の中学生からすると「何それ?」ってツッコミどころ満載。
でも不思議と意味は分かるから、日本語の面白さを知るきっかけになるんだよ。
ここでは、親世代の流行語や死語を取り上げて、今どきの言葉と比べながら紹介していくよ。
学校や部活の空気、友達との会話、テレビ番組から生まれた言葉まで幅広く見ていこう。

江戸までは行かない 昭和〜平成初期に限定する理由
「昔の言い方」とは言っても、古典に出てくる難しい日本語やシソーラス辞典に載ってる古語を紹介してもピンと来ないよね。
だって授業中の質問じゃないんだから。
ここでは昭和〜平成初期のリアルな表現を中心にする。
テレビや漫画、部活動のハナシから広がった言葉は、意味が分かれば「なるほど!」と納得できる。
それが中学生にとっても一番面白い学び方だと思うよ。
「死語」と「まだ通じる古めの言い回し」の線引き
「死語」と呼ばれるものは、もうほとんど誰も使っていない日本語。
例えば「チョベリグ」は平成世代なら笑うけど、今の学校では聞かないよね。
逆に「ダチ」や「バリバリ」は先生や仕事の場面でまだ耳にすることもある。
だから完全に消えた言葉と、まだちょっと残ってる表現を分けて考えるとわかりやすい。
言葉の寿命も流行と同じで短いことが多いんだ。
大人が言いがちワードあるある
先生がつい口にする「バッチグー」、お父さんが真面目な顔で言う「イカす」、テレビのバラエティで連呼された「アウト〜!」。
こうしたフレーズは、当時の番組や文化に直結している。
質問に対する回答として軽い合図で使われたり、部活の掛け声になったりもした。
つまり死語はただの笑いネタじゃなく、時代の空気を映す大切な記録でもあるんだよね。
この記事で扱うジャンル一覧(挨拶・学校・モノ・気持ち)
昔の言い方を全部集めるのは無理だけど、ここでは大きく四つに分けて紹介していくよ。
1つ目は挨拶や日常のやりとり。
2つ目は学校や部活での使い方。
3つ目は生活のモノの呼び方。
4つ目は感情を表す表現。
どれも中学生に身近で「へえ!」と思えるはずだよ。
昭和レトロの昔の言い方|今きくと逆に新鮮な4選×用法
昭和の言葉って、今の中学生からすると「え、それ本気で使ってたの?」と笑ってしまうようなものが多いよね。
でも同時に、日本語の柔らかさや、時代ごとの空気感がぎゅっと詰まっている。
テレビ番組や雑誌、学校の先生の口グセから広まったものも多いから、親に聞けば「懐かしい!」と盛り上がるかも。
しかも今あえて使うと、逆に新鮮に感じられて会話のネタになる。
ここでは昭和を代表する4つの昔の言い方を取り上げて、それぞれの意味や使い方を紹介していくよ。

かっこいい=「イカす」「ナウい」使い分けのツボ
「イカす」という言葉は昭和の若者が「最高にかっこいい」と思ったときに使った表現だ。
英語の「cool」に近いニュアンスで、ファッションなどをほめる時によく出てきたんだよね。
一方で「ナウい」は「今っぽい」「流行している」という意味。
でも現代で使うと「ダサかわいい」雰囲気になっちゃうのが面白い。
先生や親が冗談まじりに「ナウいね」と言ってるのを聞いたことある人もいるかもしれない。
同じ「かっこいい」でも、時代が違うとこんなに違う表現になるんだ。
元気・勢い=「バリバリ」「ガンガン」いつ言う?
昭和の部活や仕事の世界でよく聞かれたのが「バリバリ」。
「バリバリ働く」「バリバリ練習する」といった感じで、とにかく勢いを示す表現だった。
今でいう「全力で」「ガチ勢」みたいなノリに近いかもね。
似たような言葉に「ガンガン」もあって、音の強さがそのまま勢いを表す。
「ガンガン攻めろ!」と今、先生に言われたら、ちょっと昭和感があるよね。
勢いを見せたいときにピッタリの昔語だったんだ。
OK合図=「バッチグー」「了解!」の温度差
親世代が使いがちなのが「バッチグー」。
これは親指を立てるジェスチャーとセットで使うのが定番だった。
「問題なし!」「完璧!」という意味で、まさに今の「神」や「それな」に近い。
でも「了解!」と言うとちょっと堅く響くのに対して、「バッチグー」は笑いが混ざる。
その軽さが友達同士での会話にピッタリだったんだ。
今でも冗談で使えば、クラスで笑いが取れるかもね。
友達=「ダチ」「マブダチ」微妙に違うニュアンス
昭和〜平成初期にかけて「友達」を指す昔の言い方といえば「ダチ」。
これは気軽でフランクな響きで、仲間意識を強める表現だった。
さらに「マブダチ」となると「親友」「特別な友達」という意味合いになる。
「親友」と言うより、ちょっとヤンチャな雰囲気が漂うのが特徴だね。
今の中学生が使う「リア友」や「ガチのトモ」と同じ位置にあたる。
友達関係の濃さを言葉で表現するのは、いつの時代も変わらないんだよ。
※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」
平成の昔の言い方|ギャル語&バラエティ発の口グセ編
平成になるとテレビや雑誌の影響力がさらに強くなって、ギャル文化やバラエティ番組から新しい言葉がどんどん生まれたんだ。
今の中学生からすると「何それ!」と笑ってしまうフレーズが盛りだくさんだけど、当時は真剣に使われていた。
携帯電話が広まり、ネットも少しずつ一般に広がったことで、新しい日本語の波が押し寄せてきた。
平成の昔の言い方は、カジュアルでユーモラスなものばかりで、今の学校でネタにすると爆笑必至だよ。

最高!=「チョベリグ」とその逆の「チョベリバ」
平成の代名詞ともいえるギャル語が「チョベリグ」。
「超ベリーグッド」の略で、最高にいい!って気持ちを表す時に使われたんだ。
逆に「超ベリーバッド」が「チョベリバ」で、最悪の意味。
雑誌やテレビの影響で全国の中高生に広がった。
今で言う「神」や「最強」に近い言葉だよね。
ただし今口にすると、逆にウケ狙いにしかならないのが面白いところ。
それはダメ=「アウト〜!」バラエティの決め台詞
平成初期のバラエティ番組では「アウト〜!」が大流行。
ルール違反や面白い失敗をしたときに、司会者や芸人が叫ぶのが定番だった。
このフレーズは学校でも部活でもまねされて、友達同士で冗談に使われるようになったんだ。
今の「終了〜」「オワコン」に近い感覚かな。
テレビ文化が作った日本語の勢いを感じる表現だよね。
かわいい系=「チョー○○」「〜じゃね?」世紀末の語感
平成の女子高生が好んだのが「チョーかわいい」「チョー楽しい」みたいな言い回し。
「超」という強調を何にでもつけて盛り上げるのが流行だった。
同時期に「〜じゃね?」という語尾も人気で、軽く同意や確認をするときに多用された。
この口調はSNSにも残っていて、今でも真似すると独特の平成っぽさが出るんだよ。
今の「エモい」「尊い」と同じく、感情を一気に盛るための日本語だったんだ。
ネット前夜=「キリ番」「厨房」初期ネット語の遺伝子
平成後半になると、ネットの掲示板文化から新しい言葉が出てきた。
「キリ番」とはアクセスカウンターがゾロ目や1000番ぴったりの番号を踏むこと。
「厨房(ちゅうぼう)」は中学生を揶揄するネットスラングで、当時は挑発的に使われたんだ。
今はSNSが中心だから「いいね数」「バズる」に置き換わったけど、根っこは同じ。
つまり日本語の変化は、ネットとともに進化してきたんだよね。
今どき語への変換表|同じ意味でも言い方チェンジ
昔の言い方をただ笑うだけじゃもったいない。
実は、意味そのものは今の日本語にもちゃんと生きていて、言葉のスタイルだけが変わっているんだ。
「イカす」と言っていた気持ちは、今なら「エモい」や「尊い」にすり替わっているし、「バリバリ」は「無双」や「ゴリる」に進化している。
こうして並べてみると、同じ感情や状況を表すために、人はいつも新しい言葉を作り出しているのがわかるよ。
ここでは代表的な昔語と、今の言葉への変換を紹介するから、自分の会話でも遊び感覚で試してみてほしいな。

「イカす」→「エモい」「尊い」:褒めの方向性をマッピング
「イカす」は昭和の若者が「かっこいい!」「最高!」と褒めるときの表現だった。
それが令和では「エモい」「尊い」に移り変わっている。
音楽や恋愛の話題で「イカす」なんて言った親世代は、今の中学生なら「エモすぎ」「尊い」に置き換える。
褒めの気持ちは変わらないけど、響きが変わるだけで時代感が全然ちがうよね。
「バリバリ」→「無双」「ゴリる」:勢いの表現アップデート
昭和の先生が「バリバリやれ!」と部活で叫んだとき、それは「全力でいけ!」という意味だった。
令和のゲーム文化から出てきた「無双」や「ゴリる」も同じく勢いを表す言葉。
「無双状態」は誰にも止められない強さを意味し、「ゴリる」は力技で押し切るニュアンスがある。
言葉は変わっても、部活動や勉強で勢いを求める場面はずっと同じだよね。
「ダチ」→「リア友」「フレ」:関係の距離と媒体の違い
昔は「ダチ」と言えば、放課後に一緒に遊ぶ友達のことだった。
でも今は「リア友」と「フレ(フレンド)」に分かれている。
「リア友」は学校や部活などリアルで会う友達を指し、「フレ」はゲームやSNS上の友達のことを指すんだ。
昔の「ダチ」が万能だったのに対し、現代では関係性ごとに細かく言い分けるのが特徴だね。
「バッチグー」→「それな」「神」:即同意の軽快さ
「バッチグー」は昭和の軽い同意表現。
親指を立てながら「完璧!」って返すのが定番だった。
今なら「それな」や「神」が同じ役割を果たしている。
「それな」は同意を一言で伝える便利ワード。
「神」は「完璧!最高!」というニュアンスを一発で示す。
こうした即答ワードは、LINEやSNSで短くやり取りする今の時代にぴったり合ってるんだよね。
言葉が変わる理由|メディア・暮らし・学校の三点セット
昔の言い方と今どきの言葉を比べると、笑えるだけじゃなくて「なぜ変わったのか?」という疑問がわいてくるよね。
その背景には、大きく分けて三つの理由があるんだ。
ひとつはテレビやSNSといったメディアの影響。
もうひとつは暮らしの道具や文化の変化。
そして最後は学校生活そのもののアップデート。
この三点が重なって、言葉の意味や表現はどんどん入れ替わっていく。
つまり昔の言い方は、ただの死語じゃなく、時代を映す鏡みたいな存在なんだよね。

みんな同じTVを見る時代→SNSバラバラ時代の影響
昭和や平成初期は、家族全員が同じテレビ番組を見ていた。
だから芸人や司会者の決め台詞が一気に広まり、学校中で同じ言葉が飛び交ったんだ。
でも令和はSNSやYouTubeで一人ひとりが違うコンテンツを見る時代。
だから流行する日本語も細かく分かれ、クラスで通じるものと通じないものが混ざっている。
みんな同じハナシ題材を持たないから、死語になるスピードも速いのかもね。
モノの変化:ポケベル→ガラケー→スマホと言い方の連鎖
道具の進化も言葉を変える大きな要因だ。
ポケベル時代には「打ち間違いで意味不明」なんてネタがあったし、ガラケー時代には「着メロ」「写メ」という言葉が生まれた。
そしてスマホ時代になると「スクショ」「通知オフ」「スタンプ」と新しい日本語が次々に誕生。
道具が変われば表現も変わるのは当たり前。
だから昔の言い方を知ると、その時代の暮らしまで見えてくるんだ。
学校文化:制服・部活・先生語のアップデート
学校の中でも言葉は進化する。
昭和の部活動では「根性」「バリバリ」が当たり前だったけど、今は「効率」「モチベ」という表現に切り替わっている。
制服だって昔は「詰襟」「セーラー服」だけだったのが、今はブレザーや自由度が高い服装に広がった。
そうなると自然に使う日本語も変わるんだ。
先生の口調も時代で変化していて、昔の説教は「君たちは〜せねばならん!」だったのが、今は「どうする?やれる?」みたいに柔らかくなっている。
礼儀と距離感:敬語の緩さ・フランクさの時代差
昭和の頃は、先生や先輩に対して厳しい敬語を使うのが常識だった。
でも今は距離感が近くなって、「先生〜、これっていいんですか?」と軽い聞き方をすることが増えた。
敬語の緩さは、社会全体のフランクな雰囲気を映しているんだ。
もちろん礼儀は必要だけど、言葉が柔らかくなった分、質問もしやすくなったというメリットもあるよね。
こうして時代の空気と一緒に、昔の言い方から今どきの言葉に切り替わっていったんだ。
生活とモノの呼び方が変わった!家電・IT・食べ物の昔語
昔の言い方は、人の気持ちや挨拶だけじゃなく、家電や食べ物の呼び方にもあふれているんだ。
親や祖父母が口にする「帳面(ちょうめん)」なんて単語、今の中学生が聞くと完全に暗号だよね。
でも当時は生活に密着したリアルな表現だった。
モノの名前はその時代の文化や技術の進歩を映すから、呼び方を追いかけるだけで暮らしの歴史が見えてくるんだよ。
ここでは家の中、通信や乗り物、ファッション、食べ物の呼び方を取り上げて、昔と今の違いを見比べてみよう。

家の中:台所→キッチン/居間→リビング/えもんかけ→ハンガー
昔の家では「台所」「居間」と呼ぶのが当たり前だった。
でも今は「キッチン」「リビング」に言い換えられて、ちょっと洋風でオシャレな感じになったよね。
昔の家では洋服を掛ける道具を「えもんかけ」と呼んでいた。
今の子が聞いたら絶対「ハンガーでしょ!」と笑うに違いない。
身近な道具の呼び方ひとつで、暮らしの時代感がガラッと変わるんだよ。
乗り物・通信:改札パンチ→IC/ポケベル→通知/留守電→ボイスメモ
昔は駅の改札で駅員さんが切符に「パンチ」を入れていた。
それが今ではICカードをピッと通すスタイルに変わったよね。
通信も同じで、昭和はポケベル、平成はガラケー、令和はスマホで通知が当たり前になった。
「留守電」という言葉も、今は「ボイスメモ」や「録音」に変わっている。
モノが進化すると同時に、言葉も自然に変化するのがよく分かるよね。
ファッション:背広→スーツ/Gパン→ジーンズの世代差
大人が「背広」と言うと、今の若者はちょっとギョッとするかも。
でも昔は「スーツ」よりも一般的な表現だったんだ。
同じく「Gパン」も昭和では普通の呼び方だったけど、今は「ジーンズ」の方がオシャレに聞こえる。
こうしたファッション用語の変化は、カタカナ語の浸透とともに進んできたんだ。
世代ごとに違う日本語が飛び交うのは面白いよね。
食の言い回し:コーラ→炭酸/サイダー→?地域で割れる呼称
飲み物の呼び方にも世代差がある。
「コーラ」をまとめて「炭酸」と言ったり、「サイダー」を地方によって「ラムネ」と呼んだりするんだ。
昭和の子供達は駄菓子屋で瓶のラムネを飲むのが定番だったけど、今はペットボトルや缶が主流。
食べ物の言い回しは地域性とも重なっているから、同じ日本語でも違って聞こえるのがまた楽しいところだね。
使いどころと注意|“レトロ語”を会話でおもしろく活かす
昔の言い方を知っていると、親世代と話が盛り上がるだけじゃなく、友達同士の会話でもネタになるんだ。
でも使い方を間違えると、「何その変な日本語?」と突っ込まれてしまうこともある。
だからこそレトロ語は、ツッコミ待ちのボケとして活用したり、家族とのハナシで笑いを取ったりするのがちょうどいい。
ここでは会話にうまく取り入れるコツや、注意した方がいい場面を紹介していくよ。

ツッコミ待ちで使う:「ナウい」は自虐かボケに限定
「ナウい」を真顔で言うと、クラス全員がシーンとなる可能性が高い。
でも逆に、わざと古臭い言い方をしてボケると面白いんだ。
「この靴ナウくない?」と笑いながら言えば、「古っ!」とツッコミが返ってくる。
使うなら自虐かボケ専用と割り切るのがコツだね。
書き言葉NG・OKの線引き:先生や公的文書では避ける
レポートや先生への提出物に「バッチグー」と書いたら怒られるのは当たり前。
昔の言い方はあくまで会話で遊ぶための言葉。
仕事や学校の正式な書き物には絶対に使わない方がいいよね。
「言葉には場面がある」ってことを意識しておくのが大事なんだ。
家族インタビュー:親の口グセを安全にネタ化するコツ
お父さんやお母さんに「昔どんな言葉を使ってた?」と聞くだけで、面白いハナシがたくさん出てくる。
その中から特に笑える表現を家でネタにすると盛り上がるんだ。
ただし、バカにするような笑い方をするとケンカの元になるから注意。
「その表現かわいいね」と褒める気持ちで会話すれば、親子の信頼も深まるよ。
クラスの空気を読もう:からかいといじりの境界線
レトロ語を使うとクラスで笑いが起きるけど、やりすぎると「空気読めてない」って思われることもある。
例えば、体調不良で休んだ友達に「チョベリバじゃん!」なんて言ったらさすがにアウト。
部活動や練習のときも、真剣な場面では控えた方がいい。
空気を読む力があると、昔の言い方もおもしろい武器になるんだ。
地域差もおもしろい!方言×レトロ語の交差点
昔の言い方と方言が合わさると、さらにユニークな表現が生まれるんだ。
同じ「昔の言い方」でも、地域によって響き方やニュアンスが変わるのがおもしろいところだよね。
関西のノリの強い言葉、東海地方の独特な呼び方、東北や九州のていねいな敬語表現など、地方ごとに味がある。
祖父母世代が話す老人語も、笑いながら聞けば日本語の多様性に気づけるチャンスになる。
ここでは地域差をふまえた昔語を見ていこう。

関西のノリ言葉:「しばくぞ」「アカン」強さと愛嬌
関西弁はテレビの影響で全国にも広まった。
「アカン」は「ダメだ」と同じ意味だけど、ちょっとユーモラスで柔らかい。
「しばくぞ」なんて強烈に聞こえるけど、本気で怒ってるわけじゃなくツッコミとして使われることも多いんだ。
標準語にはない愛嬌があって、死語にはならず今も健在だね。
東海の「ケッタ」問題:自転車の呼び方タイムスリップ
愛知や岐阜のあたりでは、自転車のことを「ケッタ」と呼ぶ。
これは「蹴って走る」から来た表現で、今の中学生には新鮮に聞こえるだろうね。
昔の部活動では「ケッタで集合な!」なんて会話が普通にあったんだ。
今はほとんど使われなくなったけど、地域限定の死語ってちょっと面白いよね。
東北・九州の敬語ニュアンス:ていねいさの方向が違う
方言の中には昔からの敬語表現が残っているものもある。
東北では「〜さま」づけが多かったり、九州では「〜なさる」が日常で使われたりするんだ。
これらは標準語の日本語に比べて、どこか昔っぽい響きを持っている。
学校や仕事の場では使わないけど、親や祖父母の会話で耳にする人もいるんじゃないかな。
祖父母語=「老人語」を笑わず観察するリスペクト
祖父母世代が口にする「めんこい(かわいい)」や「はらから(兄弟)」といった言葉。
中学生からすると完全に「何それ?」って感じだろう。
でも老人語はその人の人生や時代背景を映している大切な日本語なんだ。
笑うのではなく、興味を持って聞くと会話のネタになるし、信頼も深まるよね。
方言と昔語のミックスは、家族とのハナシを盛り上げる宝物みたいなものだよ。

まとめ
昔の言い方を振り返ると、日本語の意味や表現がどれだけ移り変わってきたかが見えてくるんだ。
イカすもチョベリグも、今となっては笑える死語だけど、当時はみんな本気で使っていた。
その背景にはテレビや部活動、友達関係、生活の道具など、いろんな事情が関わっている。
そして今の「エモい」「神」だって、いつかは「昔の言い方」として紹介される日が来るかもしれない。
つまり言葉は流行のサイクルを生きていて、時代ごとに姿を変える生き物なんだよね。
親や先生が口にする言葉に「古っ!」と笑いながらも、「なるほど」と理解できたら、それだけで会話が豊かになる。
英語に翻訳できない日本語の独特な表現もあるし、シソーラスでは拾えないニュアンスもある。
だから質問と回答を繰り返しながら、昔語と今語をつなげて楽しむのがいちばんだと思うよ。
※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。
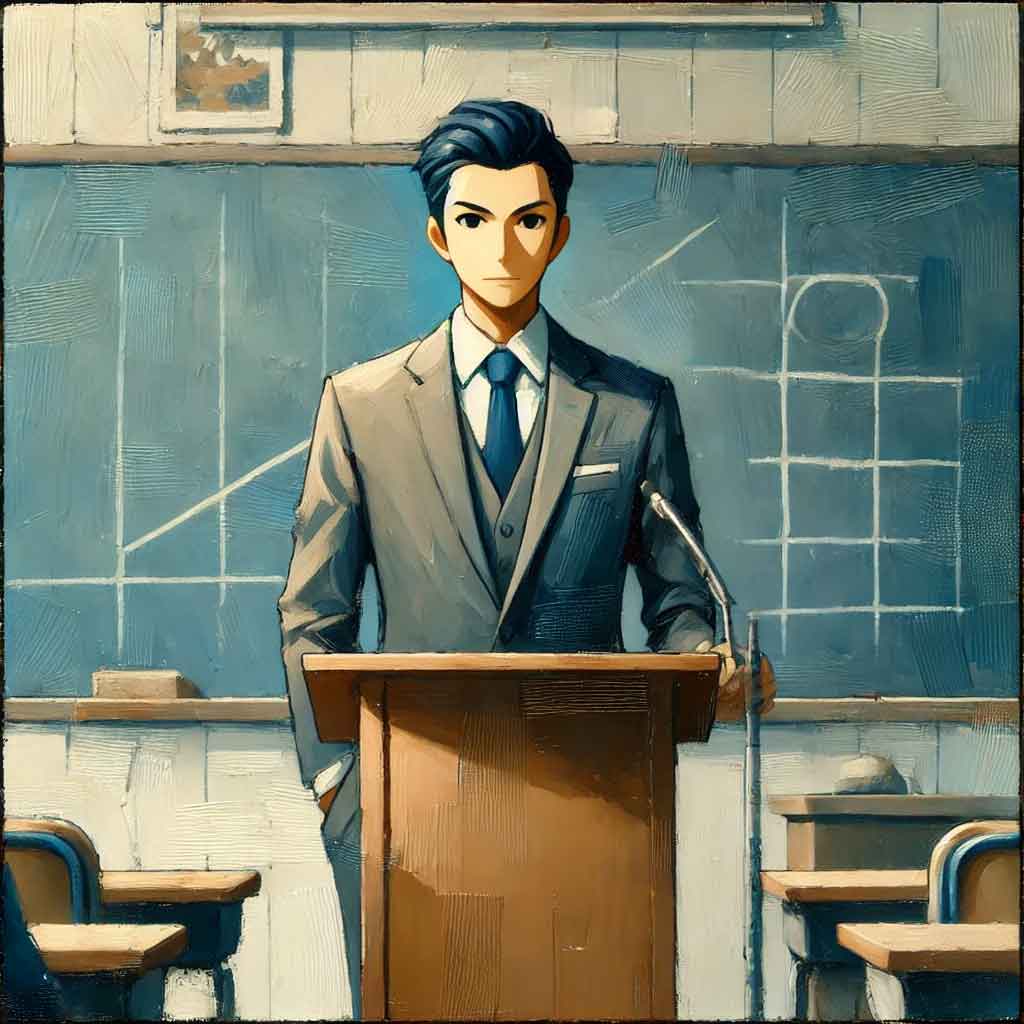
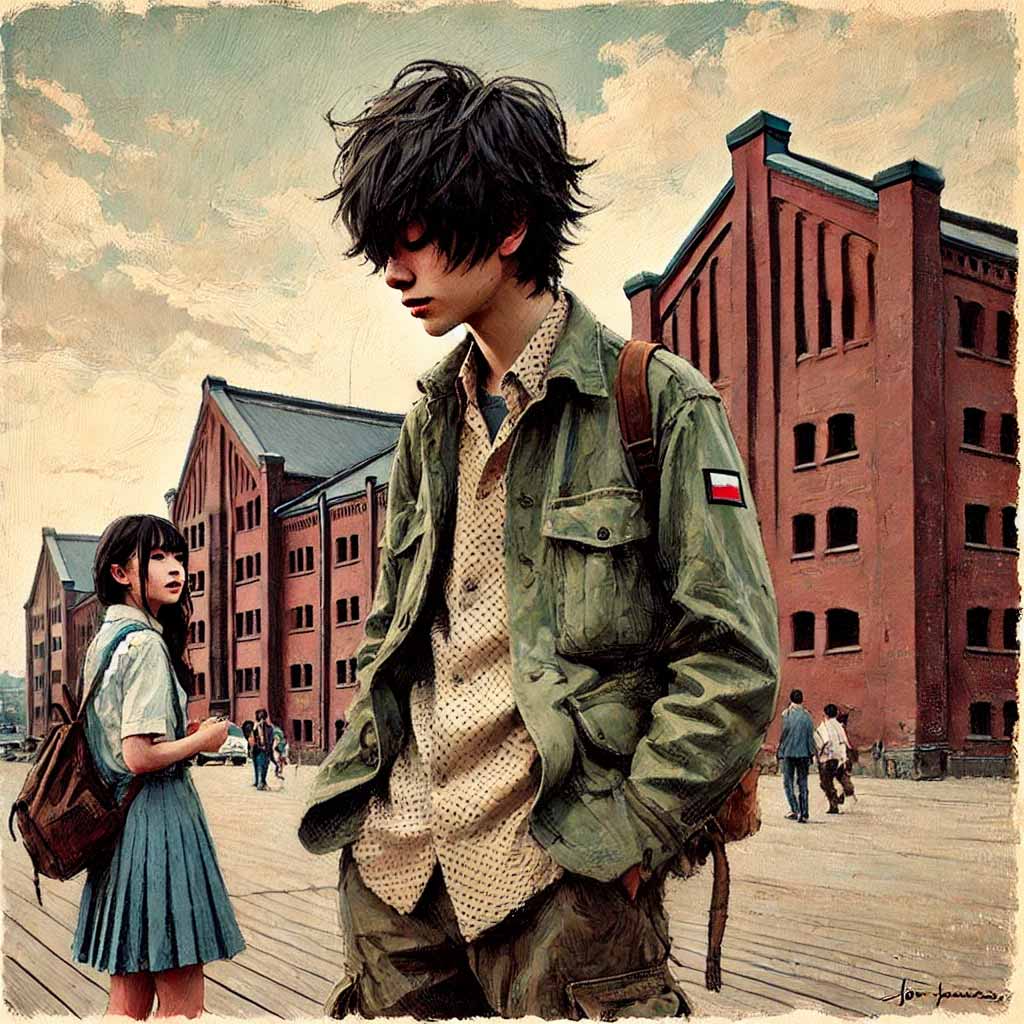


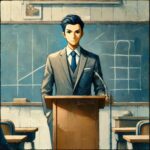


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません