厨二病と中二病 違いは? こんな場合はどっち使う? サンプル付き!
結論:読み方は同じ。
でも「厨二病」のほうが皮肉が強い。
中二病=思春期の「背伸びあるある」を笑う言い方。
厨二病=ネット由来で「イタさ」を強めてからかう言い方。
迷ったら、学校や日常では「中二病」が無難。
「厨二病」は相手を傷つけやすいから、使う場面は選ぼう。
中二病 厨二病の違い
| 項目 | 中二病 | 厨二病 |
|---|---|---|
| 発祥 | ラジオ | ネット |
| ニュアンス | あるある | 皮肉・揶揄 |
| 使われ方 | 日常会話 | ネット |
| 印象 | 笑える | 痛い寄り |
こんな場合、どっち使うの?サンプル
「中二病」と「厨二病」、意味の違いは分かったけど、実際の会話では「で、どっち使えばいいの?」って迷うこと、あるよね。
言葉そのものは似ていても、使う場面を間違えると、冗談のつもりが相手を傷つけてしまうこともある。
ここでは、よくあるシーン別に、どっちを使うのが無難かを整理してみよう。
友達同士で軽くイジりたいとき
この場合は、基本的に「中二病」が安全だ。
「また中二病発動してるじゃん」くらいなら、冗談として受け取ってもらいやすい。
思春期あるある、という共通認識があるから、笑って流せる可能性が高いんだよね。
逆にここで「厨二病」を使うと、ちょっとトゲが強く聞こえることもあるから注意。
学校やクラスの会話で話題にするとき
このシーンでもおすすめは「中二病」。
先生やクラスメイトがいる場では、皮肉が強い言葉は誤解を生みやすい。
「中二のころって、誰でも中二病あるよね」くらいの言い方なら、場の空気も壊しにくい。
日常会話では、「中二病=成長途中」くらいの認識がちょうどいい。
ネットやSNSで評価・ツッコミを入れるとき
ネット上では「厨二病」が使われることが多い。
掲示板やコメント欄では、「その設定、厨二病すぎる」みたいな言い回しもよく見かける。
ただしこれは、あくまでネット文化の中での使い方。
本人に直接言うと、思った以上にキツく伝わることがあるから気をつけたい。
キャラや作品の設定を語るとき
この場合は、使い分けがポイント。
愛着や分析の文脈なら「中二病」。
ネタとして笑うなら「厨二病」。
たとえば、「このキャラ、中二病っぽくて魅力あるよね」は好意的。
「設定盛りすぎて厨二病だな」はツッコミ寄り。
同じ内容でも、言葉ひとつで印象が変わる。
自分の過去を振り返るとき
自分自身について話すなら、ほとんどの場合「中二病」でOK。
「昔の自分、完全に中二病だったわ」という言い方は、自虐としても成立する。
「厨二病だった」と言うと、自分をかなり強くディスってる印象になるから、
ネタにしたいなら中二病のほうが使いやすい。
他人を評価・批判するとき
ここは一番注意が必要な場面だ。
基本的には使わないのが正解。
どうしても使うなら、「中二病」までにしておこう。
「厨二病」は、相手を下に見るニュアンスが強く、トラブルの火種になりやすい。
笑いにしたいつもりでも、受け取る側はそう感じないこともあるからね。
厨二病と中二病の違いって何? そもそも定義されてるの?
「中二病」と「厨二病」って、どっちも聞いたことあるけど、同じ意味じゃないの?
そう思ってる中学生も多いはず。
でも実は、このふたつにはちょっとした「違い」があるんだ。
まず読み方はどっちも「ちゅうにびょう」って読むけど、文字に注目してみると、「中」と「厨」で意味がガラッと変わってくる。
「中二病」は、ラジオ番組から生まれた言葉で、ちょっと思春期の“背伸び”をネタにした感じ。
一方で「厨二病」は、インターネット掲示板で生まれたスラングで、ちょっと“イタさ”を強調したニュアンスがある。
どちらも中学生のころの「ありがちな言動」から来てるけど、使われる場面や、言われたときの印象はちょっと違う。
言葉っておもしろいよね。
似てるようで、じつは深い意味の違いがあるってわけ。

厨二病と中二病、読み方はどう違うの?
読み方は、どちらも「ちゅうにびょう」だ。
でも、文字を見てわかるように、「中」はそのまま「中学二年生」の略。
「厨」のほうは、ちょっと違う意味が込められてる。
実はこの「厨」って文字は、「中坊」のネットスラング「厨房」から来ている。
ネットスラングで「厨房」っていうと、「イタい中学生」や「マナーが悪いユーザー」を指して使われることが多かったんだ。
そこから、「中二病よりもっとイタい」人を揶揄する意味で、「厨二病」って表現ができたんだよね。
つまり、「読み方」は同じでも、漢字のチョイスでニュアンスがまるで変わるってわけ。
言葉って奥深いよなあ。
そもそも発祥はどっちが先なの?
発祥が先なのは「中二病」だ。
この言葉が初めて登場したのは、1999年の伊集院光さんのラジオ番組『深夜の馬鹿力』なんだよ。
「あるあるネタ」として、中学生特有のカッコつけた言動を笑いに変えるコーナーから生まれたんだ。
たとえば、「哲学語ってみたり」「妄想で自分を特別な存在に見せたり」ってやつ。
そのあと、「厨二病」は2000年代前半に、ネット掲示板やブログで使われるようになっていった。
つまり、「厨二病」は「中二病」を元にして、よりネットっぽく、より皮肉っぽく育った後輩って感じかも。
発祥をたどると、やっぱり最初に流行ったのは「中二病」なんだよね。
ネットスラングとしての変遷は?
ネットスラングとしての変化もなかなか興味深いよ。
最初は「中二病」がラジオ発のネタだったけど、ネットに広まると「厨二病」という言葉が現れて、より直接的な「イタさ」や「自己愛」を意味するようになっていった。
2ちゃんねるでは、独自の世界観にどっぷり浸ってるユーザーが「厨二病乙」とか「DQNと紙一重」って言われたりしてたんだ。
このあたりから、単なる思春期ネタじゃなく、ちょっとキツめの皮肉も含むようになってくる。
今ではTwitterやTikTokでも「#中二病」ってタグが付いた動画があるし、用語や態度も時代に合わせてアップデートされてる。
たとえば「黒歴史」「俺ルール」「特殊能力設定」なんてのも、いまだに中二ワードとして健在。
ネットスラングって進化する生き物みたいなもんだな。
実生活での使い分け、されてる?
実際の生活で「中二病」と「厨二病」がどう使い分けられてるかっていうと、たしかに場面によって違いがある。
学校では「中二病」って言い方のほうが一般的かも。
たとえば、「またあいつ中二病発動してるよ~」なんて笑って言えるような場面だね。
でも、ネットやオタク系の会話の中では、「厨二病」って書き方のほうが登場頻度が高い。
とくに、キャラ設定にこだわるタイプとか、ファッションや発言がちょっと過激な人を指して「厨二くせえ」って言ったりするよね。
本人は本気でも、周囲はちょっと引いてたりするってパターンも多い。
だから、表記の違いは、けっこう「周りからどう見えるか」の温度差を表してるのかも。
使い方には気をつけよう。

厨二病の「厨」ってなにさ? 意味を掘ってみよう
「厨二病」って書かれてると、まず「厨」って字が気になるよね。
これ、料理をする「厨房(ちゅうぼう)」の「厨」だけど、もちろんキッチンの話じゃない。
ネットスラングで「厨房」ってのは、「中学生」や「子どもっぽい人」をバカにするときに使われてた表現なんだ。
つまり「中坊→厨房→厨」って変化して、いつの間にか「イタいネットユーザー」って意味で使われるようになったってわけ。
その流れを引き継いで、「厨二病」は「ちょっとイタい中学生気質の発言や行動」って意味になっていった。
このへんの言葉の変化って、なかなかクセがあるけど、面白さもあるよね。
じゃあなんで「中二病」じゃなくて「厨二病」ってわざわざ書き換えられたんだろう?
それは、より「痛い」「イタい」って印象を強調したかったからだと思うんだ。
「中二病」は比較的ライトなからかいで済むけど、「厨二病」はより突っ込んだ皮肉が入ってる。
つまり、本人の気持ちと周囲の評価にギャップがある状態が、文字にも表れてるってこと。
中二病が「笑える勘違い」なら、厨二病は「ちょっと引かれる勘違い」みたいなもの。
言葉ひとつで印象がガラリと変わるから不思議だ。
それに「厨二病」って言葉が生まれた2000年代初頭は、ネットがちょうど拡大してた時代。
匿名掲示板が流行してて、自由に妄想を語る文化も盛んだった。
「世界が偽りに見える」とか、「オレにしかわからない真実がある」みたいな“邪気眼”スタイルのキャラ設定が、ネットではそこそこウケてた。
でもそれが行き過ぎると「アイタタ…」な扱いになる。
この「イタさ」と「独自世界観」が合わさって、厨二病って言葉にまとめられたんだろうな。
さらに言うと、「俺って特別」っていう感覚は、たぶん誰しも一度は持つものだと思うんだ。
ただ、それが暴走すると「キャラづけ」や「用語」が極端になる。
「黒い翼が疼く」とか、「俺の右目には封印された力が…」みたいなセリフ、どこかで聞いたことあるでしょ?
このへんが厨二病っぽい典型例。
ファッションだって、やたら黒尽くめだったり、レザーのロングコートを羽織ったり。
本人は本気だけど、周囲から見るとちょっと浮いてる。
それでもそういう時期を経て、みんな大人になっていくもんなんだよね。

中二病の拡大 メディアとの関係
この流行をさらに押し上げたのが、アニメや漫画の存在だった。
たとえば『涼宮ハルヒの憂鬱』や『中二病でも恋がしたい!』なんかは、中二病キャラの代名詞とも言える作品。
どちらも、自分だけの世界観を持っていて、ちょっと変わった発言をしたり、普通の生活に“異能”っぽい設定を持ち込んだりしてる。
それが視聴者の中高生に響いたんだよね。
「こんなキャラ、クラスに一人はいそう」って感覚があったから、リアルにも感じられたし、親しみも持たれたんだ。
とはいえ、「中二病」って言葉には「病」ってついてるけど、本当の病気ではない。
あくまで思春期の“通過儀礼”的な言葉なんだ。
精神科で診断されるような「症状」じゃないし、病名として医学的に存在してるわけでもない。
ただし、「自己中心的な世界観に没入して、周囲が見えなくなる」って意味では、大人から見て“ちょっと問題”とされることもある。
でもそれもまた、成長過程のひとつとして見守る必要があるかもしれない。
最近では、SNSで自分の“黒歴史”をネタとして晒す風潮があって、「中二病だったころの自分」にツッコミを入れる文化も生まれてる。
たとえば、「昔のTwitterアカウント名が『闇の堕天使』だった」とか、「日記に“世界は偽りだ”と書いてた」とか。
こういった行動は、もはや誰かに揶揄される対象というよりも、笑って振り返る“あるある”になってきてる。
中二病は、時代とともに“恥ずかしい過去”から“共感できるネタ”へと変化してるってことだね。

タイプ別診断!あなたはどの中二スタイル?
中二病って、ひとくくりにされがちだけど、実は細かく分類できるんだ。
ざっくり言えば4タイプくらいあって、それぞれがけっこう個性的なんだよね。
邪気眼系
まずは「邪気眼系」ってやつ。
これは、自分の中に“特別な力”が眠ってると信じていて、「右目には封印された魔力が…」とか言い出すタイプだ。
手に包帯を巻いてることもあるし、やたらとポエムを書くのもこのタイプに多い。
ちょっとマンガのキャラに影響されすぎてる感じもあるけど、妄想の世界に入り込む力はすごい。
でも、現実と空想のバランスは大事だぞ。
能力妄想型
次に「能力妄想型」。
これは邪気眼と似てるけど、もう少しリアル路線。
たとえば「オレのIQは180」とか「本気を出せばスポーツでも学力でもトップになれる」みたいなアピールをするタイプ。
実際の実力がどうかはさておき、本人の中では完璧に筋が通ってる。
「まだ本気を出してないだけ」っていうのが決まり文句なんだ。
このタイプは、将来大成するか、ただの口だけ番長で終わるか、けっこう分かれるところかも。
自称リアリスト系
三つ目は「自称リアリスト系」。
「俺、現実しか見ないから」とか、「感情よりも合理性を重視してる」とか言いがちなタイプだね。
とにかく大人ぶりたくて、「感情的になるやつ、マジ無理」って他人を否定しがち。
でも、よく見るとそういう本人が一番感情に振り回されてたりもする。
「現実しか見てない」と言いつつ、けっこう妄想してたりね。
このタイプは、「冷めた自分」を演出したい願望が強いタイプとも言える。
中二病の中でも、いちばん“他人に見せる態度”を気にするやつかもしれないな。
俺ルール型
最後は「俺ルール型」。
このタイプは、自分だけの法則やルールを作って、それに周囲を巻き込もうとするタイプ。
「オレは朝日を浴びると力が減るから朝練は無理」とか、「教科書はオレ流で使う」とか、完全に自分ワールドで生きてる。
しかもそれを“恥ずかしい”とは思ってなくて、むしろ“かっこいい”と信じてるから手強い。
ときには学校のルールにも反発して、「俺は俺のルールで動く」なんて言い出したりする。
でも、周りから見ればそれはただの“めんどくさいやつ”になってることもあるから注意だ。

厨二病と中二病、どっちがより「痛い」認定されがち?
「痛い」って言われるのは、どっちの言動だろう?
「厨二病」と「中二病」、じつはこの2つ、他人からの“見え方”にけっこう差がある。
大人から見ると、「中二病」は「思春期あるある」って感じで、ちょっと笑って見守れるレベルなんだよね。
でも「厨二病」は、もっと過激で、自分の世界観に他人を巻き込もうとする傾向がある。
たとえば授業中に急に詩を書いたり、何かのセリフを真顔で言いだしたり。
その「本人は本気、周囲は困惑」みたいなズレが、“痛さ”として目立つわけだ。
SNSの時代になってからは、「痛い言動」がより可視化されやすくなった。
TwitterやTikTokで、中二的なアピールをしちゃうと、すぐに拡散されちゃうんだよね。
自分の“世界観”を動画で演出したり、意味深なポエムを投稿したり。
本人は「カッコいい」と思ってるかもしれないけど、見てる側は「えっ…」ってなることも多い。
そしてそれが「晒し」や「黒歴史」として残ってしまう。
この“記録が消えない”ってところも、今どきの中二病の難しさだと思うよ。
それに「恥の概念」がどこにあるかも、痛さの判断基準になる。
「昔の自分を見返すと赤面する」っていうのは、わりと健全なんだ。
でも、「今も本気で俺は選ばれし存在」と思ってるなら、それは厨二病の可能性大。
「恥ずかしさを感じられるか」は、自分を客観視できるかどうかってこと。
だから、同じ“イタいセリフ”でも、言う人の“意識”によって痛さのレベルが全然違ってくる。
その違い、案外大事かもな。
ただし、最後にひとつ言っておきたいのは、「痛い=ダメ」ってことじゃないってこと。
「笑って済ませられる中二病」って、実はとても価値がある。
自分の過去を受け入れて、ネタにできるって、成長の証だと思うんだよね。
逆に「止まらない厨二病」は、現実と妄想の間に壁を作って、他人と距離をとってしまうこともある。
だから大事なのは、自分の“過去のカッコつけ”を笑えるかどうか。
そこが「中二病」と「厨二病」を分ける、大きな境界線なんじゃないかな。

実は奥が深い? 厨二・中二文化の正体とは
「厨二病」や「中二病」って、ただの笑い話と思われがちだけど、実はけっこう奥が深い文化だったりもする。
なぜなら、これってある種の「成長の通過儀礼」なんだよね。
思春期の不安定さや、自分の存在をどう表現するかっていう“もがき”がそのまま形になってる。
つまり、「中二感」っていうのは、自分自身の内面との対話だったりするわけ。
だから、ある程度の“黒歴史”を通らないと、大人になれないとも言えるかもね。
実際、大人になってから振り返ると、「あのときの自分、痛かったけど面白かった」って思えるものだし。
それに、痛いってことは「創造力がある」ってことの裏返しでもある。
自分の中に“世界観”を作るって、めちゃくちゃクリエイティブな行為だ。
たとえば、異能力バトルの設定を考えたり、自作の詩を書いたり、ファッションに独自のこだわりを持ったり。
これって、発想力と表現力のかたまりなんだよね。
ただ、それがちょっと空回りしてるだけ。
でも、そこを否定してしまったら、若い感性が育たなくなる。
だから、大人は中二病を笑うんじゃなくて、「お、面白いこと考えてるな」って受け止めるくらいがちょうどいいのかもしれない。
そしてこの文化、意外にも文学や音楽との親和性が高い。
詩的な表現とか、孤独感とか、絶望からの再生とか、まさに中二的なテーマが芸術の根っこにあるんだよね。
思春期のころに聴いた音楽や読んだ小説が、今も心に残ってるって人、多いんじゃない?
バンドの歌詞に共感したり、ダークな物語に没頭したり。
それが「中二っぽい」と笑われたとしても、自分を支えてくれた“何か”であることは間違いない。
つまり、中二病はサブカルの栄養源とも言える。
創作と自己投影の境界線も、ここではあいまいだ。
自分が作ったキャラに、自分自身の願望を込めるってこと、よくあるよね。
「強くて孤独で理解者が少ないけど、実は誰よりも優しい」みたいなキャラ設定。
まさにそれ、中二病のエッセンスが詰まってる。
でも、その自己投影こそが物語を生む原動力なんだ。
だから、中二病は恥じゃなくて、“創作のスタートライン”なのかもしれない。

じゃあ今どきの中高生はどう使ってる?令和版「中二感」
中二病って、昔の話だと思ってない?
いやいや、令和の中学生や高校生にも、しっかり“中二感”は生きてるんだよ。
ただし、表現の仕方がちょっと変わってきてる。
たとえば、TikTokやInstagramでは、自分の“闇属性”をあえて演出する動画がバズったりするんだ。
「陰キャ風メイク」とか、「闇堕ちダンス」なんて言葉も出てきてるくらい。
昔のような詩やセリフじゃなく、映像や音楽で“厨二っぽさ”を見せるスタイルが主流になってきてる。
自己演出の方法が、より洗練されてるとも言えるかもね。
中二用語も、実はけっこうアップデートされてる。
「俺の右腕が疼く」みたいなベタなセリフは、今では逆に“ネタ”として使われることが多い。
それよりも「闇堕ち」「異能力」「運命背負いし者」みたいな表現が今風。
しかも、それを完全に本気ではなく、半分ネタとして言ってるケースがほとんど。
「イタい自分もコンテンツ化する」っていう感覚なんだろうね。
これは、令和世代ならではのSNS文化の影響が大きい。
「黒歴史」って言葉、今でも使われてるよ。
ただし、ちょっとニュアンスが変わってきた感じがある。
昔は「恥ずかしくて封印したい過去」って意味だったけど、今では「笑える思い出」として堂々と公開する人も多い。
たとえば、「中一のときに“堕天使○○”って名乗ってた黒歴史」とか、「中二のころに自作詩を朗読してた動画」なんてのも、自ら晒しちゃうんだ。
それって、ある意味すごくポジティブ。
過去の自分をネタにできる強さって、見習いたいよね。
じゃあ、先生や親からはどう見えてるのか?
これはちょっとリアルな話。
学校の先生や保護者は、中二病的な言動に対して「成長の一部」と受け止めることもあれば、「ちょっと心配だな」と思うこともある。
授業中に突然詩を書いたり、発言が妙に哲学的だったりすると、「あれ、どうしたの?」ってなるよね。
でも、それが一時的なもので、本人が楽しんでやってるなら、温かく見守る先生も多い。
実際、中学生のうちは“いろいろ試したいお年ごろ”だから、ちょっとくらいイタくても大丈夫。
それを経て、自分らしさを見つけていけばいいんだよ。
Q. 「中二病」って、実際に病気なの?
A. ちがうよ。医学的な病名ではないんだ。
思春期によくある「背伸び」や「自分探し」を、少しユーモラスに表した言葉だよ。
Q. 大人になっても「中二病」っぽさが残ることはある?
A. あるある。
世界観づくりや強いこだわりとして残る人もいる。
それが創作や仕事に活きる場合も多いよ。
Q. 「中二病っぽい」って言われたら、どう受け取ればいい?
A. 言い方次第だけど、多くは軽いツッコミ。
深刻に受け止めすぎず、「まあそんな時期だよね」くらいで流してOKだよ。
Q. 中二病っぽい言動は、直したほうがいいの?
A. 無理に直す必要はないよ。
ただ、周りが困っているサインがあれば、少しだけ距離感を意識するとラクになる。
感性そのものは、悪いものじゃないからね。

まとめ:厨二病と中二病、使い分けるべき?笑って済ませよう?
ここまで見てきたとおり、「中二病」と「厨二病」は、似ているようでちょっとずつ違う。
発祥も違えば、使われる場面も違うし、言葉に込められた“揶揄”の度合いも微妙に違うんだ。
「中二病」はラジオ発、「厨二病」はネット発。
「中二病」は成長の一部としての背伸び、「厨二病」はちょっと他人を困らせがちな“こじらせ”ってイメージが強いよね。
でも、どっちも“自分探し”の過程であることは間違いない。
そして何より大事なのは、その経験をあとから笑って話せるかどうかってこと。
中学生って、いろんなことを考える時期だ。
自分ってなんだろうとか、他人にどう見られてるんだろうとか。
そんな不安やモヤモヤを、世界観にしたり、セリフにしたり、ファッションにしたりして表現するのが、中二病の正体なんだよね。
それを“恥ずかしい過去”として押し込めるのもいいけど、ネタとして笑って受け入れるほうが、ちょっと楽になる。
だって、それがあったから今の自分がいるんだから。
だから、「中二病だからダメ」とか、「厨二病は恥だ」とか、そういう決めつけはしなくていい。
むしろ、そこにある“創造力”や“表現欲”をうまく使えたら、それは立派な才能になる。
作家やアーティストだって、みんな昔は中二病だったかもしれないし、今もその感性を大事にしてる人だって多い。
思いっきりこじらせて、思いっきり恥をかいて、それを面白く話せるようになったら、もうそれは大人の階段をのぼってる証拠だよね。
というわけで、「中二病」と「厨二病」、どっちを使うかは自由だけど、大事なのは“自分も他人も笑顔になれる使い方”をすることだと思うんだ。
あなたの「イタい過去」も、「ちょっと面白い思い出」として、きっと誰かの心に残る日がくるかもしれないよ。

プロフィール
1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。
このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。
経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。




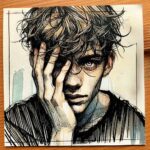


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません